あす2023.3.11の書評兼討論の会のために、メモを公開しておきます。全くの走り書きで済みませんが・・・
もっと細かい頁参照コメントは、明日行ないます。
(三浦俊彦)
三冊それぞれの脱構築を行なう。(「脱構築」という語自体、悪しきジェンダー論の源流となっているポストモダニズムの匂いがして好ましくないのだが)。
三つの脱構築は単純であり、共通の構造を持っている。端的に「文面上の主張を、実際の論理的な帰結が裏切っていること」(の摘出)だ。
『美とミソジニー』は、化粧を「男性の利益のための女性抑圧装置」として提示しているが、本書の主張を認めると化粧は逆に「女性の利益のための男性制御装置」であることが見えてくる。化粧がフェミニズム的に脅威となるほど女性に負担を強いるものであるならば、男性は負債を負うこととなり、深田えいみ、大島麻衣のような主張が成立することになる。すなわち、男が金を出した場合にはプラマイゼロになっただけであり、余剰としてのセックスについての交渉の主導権は女性が男性と対等に持つこととなる。デートにおける売買春構造を崩し、女性に性的自由を獲得させる兵器こそ(本書の表層の主張に反し、深層の論理にしたがえば)化粧であり、反機能的ファッションではないだろうか。
(ただし、化粧を「セックスの代理的表象」として捉えれば以上の「女性主導戦略」のロジックは成り立つものの、化粧を「セックスの等価物」として実体化する立場に立つと、化粧することは男にセックスを与えたも同然となり、デート即買売春、というロジックが復活することになるだろう・・・)
『ジェンダーと脳』は、脳機能の性別本質主義を否定している。それと同時に個人の社会的な性別越境を肯定している。この二つの立場は反本質主義で一致するように見えるが、それは表面上のことにすぎない。脳機能の反本質主義は、個人レベルでは生殖器以外の男女の差異を否定し、統計的差異のみを認めるため、「個人の社会的性別越境」は無意味である、と判定せねばならないはずである。この簡単なロジックから逸脱し、無反省にトランスジェンダリズムのトレンドをなぞっている点で、本書は自然科学者のナイーブな思索欠乏症候群のサンプルとなっている。
『分析フェミニズム基本論文集』の第一論文・第二論文は、「女性とは何か」の改良的探究を採用しているが、「改良的であることは改良を妨げる」という皮肉な事実を立証してしまった感がある。女性の被抑圧性・従属性の現実を重視するあまり、それを理論的な「女性の定義」に組み込んでしまうという誤謬を犯したのだ。改良的探究のためには、社会が改良される前ではなく、改良された後の記述を定義として採用しなければならないはずだろう。しかし改良後の女性の状態を定義とすると、改良前の社会で女性が置かれた現実を軽視している見掛けが生じてしまうので、活動家としては堪えられない(ここが政治的スタンスの弱点である)。そこで短絡的に「重視したい現実を理論的にも重視することの表明として定義に組み込む」という誤謬を犯してしまう。自らの理論的姿勢が、自らの実践的機能を裏切ってしまうのである。
第五論文も同様。「異人種間には単なる異質性には還元できないヒエラルキーがある」という、法的にも倫理的にも公式に否定されていながら実質的には何となく成立しているように皆感じている偶然的事態を、重視するあまり人種の定義的本質に組み込んでしまい、人種フェチを他のフェチとは異なる倫理的含意を持つ不正な嗜好として糾弾する羽目に陥っている。この論考を真に受けて異人種への性的嗜好を自粛したりすれば、異人種間の交流が抑止されることとなり、むしろヒエラルキーの固定につながるという実践的逆効果が生じてしまう。
以上のような、各論文に共通する「実践的重視を理論的重視へと短絡的にスライドさせたことからくる実践的悪影響」は明瞭である。編訳者解説にそのあたりの指摘が全く見られないのは不可解としか言いようがない。
総合的にまとめると、
●「化粧は女性に無用の負担を強いる」という事実を、表面的にとれば女性抑圧と見なせるが、その自己抑圧の負担を債権として転用する可能性にも目を向ける必要がある。男性に経済的債務を負わせつつ、性的平等を主張するための道具となりうる、と。この性的平等は、性的関係で女性のみが生物学的負担を負うという不平等な宿命を是正する可能性がある。
表面上の論理に囚われる誤謬は、ジェンダー全般の論題について蔓延している。「男女の心理的(非身体的)区別を過大評価しないことが大切」という教訓と、「個人が心理的性別帰属を横断したり、男女いずれでもない心理的性別を称したりする風潮」とは表面的に合致するがゆえに、論理構造を考えずに短絡的に直結させるという誤謬である。
この誤謬は、「ジェンダー」「人種」が社会研究のために重要な概念だからという理由で、ジェンダーや人種の区別を現実に尊重し永続させなければならないかのように扱う短絡的なアイデンティティ・ポリティクスと同根である。
学問的な重要性と、政治的・倫理的な有益性とは全く別。(「差別」「戦争」「貧困」を考えよ)
ジェンダー学はジェンダー唯名論と当然のことながら両立する。心理学が心の消去主義と両立し、倫理学や美学のような価値論が価値の反実在論や非認知主義と両立するように。
三冊とも、表面上の論理に囚われたことによる自己否定的メッセージを確証した書、と位置づけたい。クリティカルシンキングの素材として使える有益な資料である(テキストとしてでなく批判対象として)。ただ、とくに『分析フェミニズム基本論文集』は、以上指摘したような単純な誤謬を警告して回ることこそ分析哲学の一つの役割であるにもかかわらず、自ら誤謬を実演し、自己フォローなしで終わっている点で、遺憾としか言いようがない。たとえば、「トランス女性(が抑圧されているという)問題を、フェミニズムにとって周縁的にしてはならない」という未分析の前提を一度も疑わないというのは分析哲学としてあるまじき態度である。「男性中心的で性差別主義的な枠組みに依拠した前提に疑問を突きつけ」(p.269)のような定型文が無自覚に頻用されるレベルにとどまり続けたところも分析哲学らしくなく・・・、残念ながら政治にかかわると堕落するのは分析哲学も例外にあらずという見本が、この『分析フェミニズム基本論文集』だったかもしれない。
第二巻を編集するさいは、素朴なジェンダー実在論だけでなく、(フェミニズムの本来の立場だったはずの)ジェンダー唯名論の立場からの論考も収録して、総合的にメタレベルでの思考(すなわち議論)を促すような論文集にしてくれることを望みたい。












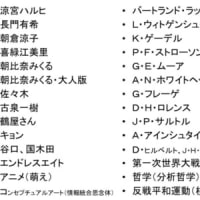
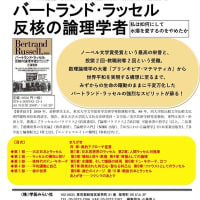
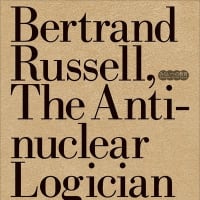
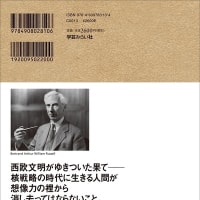




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます