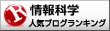我が家は、明智光秀の側室の子が山城国の神社に匿われて生き延びた子孫と伝わっています。いくつかの伝承品があったのですが、そのうちの短冊には「山あいの霧はさながら海にして波かときけば松風の音」という和歌が書かれていました。という話を先日の講演会で初めてご披露して、「霧といえば丹波の霧が有名ですので、この側室は丹波の亀山城にいたのでしょう」と説明しました。
>>> 経営視点で観る本能寺の変講演
これを聞いた歌手で作詞家の明智ガラシャさんから「波かときけばとあるので、波の音の聞こえるところにいた側室のことを思って詠んだ和歌と思われます。さらに松風とあるので私を待っているあなたを想うというメッセージでしょう」と流石は作詞家というコメントをいただきました。
坂本城のあった琵琶湖の波は結構高いと有名なので、側室は坂本城にいたことになりそうです。正室は既に亡くなっているので、不思議な話ではありません。そうすると、側室は誰の縁者だろう?子が匿われたという山城国の神社はどこだろう?と想像が膨らみます。

ガラシャさんのコメントに触発されて、少し調べてみました。
着物の文様として波と松を組み合わせたものが目出度いものとして用いられているそうです。波は、広い海がもたらす恩恵を感じさせる図柄で、幾重にも無限に重なる波の文様に未来永劫の人々の幸せと、永遠の繁栄の願いが込められた吉祥紋様、松は風雪に耐え、厳寒や酷暑にも常緑を保つことから長寿延命の印とされた。四季を通して葉の色が変わらないことから「常盤木(ときわぎ)」と呼ばれ、縁起の良い木として吉祥のシンボルにされてきました、とのことです。
これを元に考えを膨らませると、側室とその子の長寿と幸せへの祈願を籠めた和歌のように思えます。さらに、考えを膨らませると、波(海)と松の名所である「天橋立」に側室と子が関係しているのではないかとも思えるのです。
いずれにせよ、先祖のおかげて400年以上も家系が続いていることにあらためて感謝です。
>>> 経営視点で観る本能寺の変講演
これを聞いた歌手で作詞家の明智ガラシャさんから「波かときけばとあるので、波の音の聞こえるところにいた側室のことを思って詠んだ和歌と思われます。さらに松風とあるので私を待っているあなたを想うというメッセージでしょう」と流石は作詞家というコメントをいただきました。
坂本城のあった琵琶湖の波は結構高いと有名なので、側室は坂本城にいたことになりそうです。正室は既に亡くなっているので、不思議な話ではありません。そうすると、側室は誰の縁者だろう?子が匿われたという山城国の神社はどこだろう?と想像が膨らみます。

ガラシャさんのコメントに触発されて、少し調べてみました。
着物の文様として波と松を組み合わせたものが目出度いものとして用いられているそうです。波は、広い海がもたらす恩恵を感じさせる図柄で、幾重にも無限に重なる波の文様に未来永劫の人々の幸せと、永遠の繁栄の願いが込められた吉祥紋様、松は風雪に耐え、厳寒や酷暑にも常緑を保つことから長寿延命の印とされた。四季を通して葉の色が変わらないことから「常盤木(ときわぎ)」と呼ばれ、縁起の良い木として吉祥のシンボルにされてきました、とのことです。
これを元に考えを膨らませると、側室とその子の長寿と幸せへの祈願を籠めた和歌のように思えます。さらに、考えを膨らませると、波(海)と松の名所である「天橋立」に側室と子が関係しているのではないかとも思えるのです。
いずれにせよ、先祖のおかげて400年以上も家系が続いていることにあらためて感謝です。