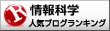前回は信憑性ある土岐明智氏の系図の復元を行いました。
★ 明智系図の歴史捜査5:土岐明智氏系図の復元
そこには、光秀へのつながりが付けられていません。残念ながら現時点では信ぴょう性ある史料が見付かっていませんので、一旦、捜査の結論をそこで打ち止めてけじめをつけておきました。
さて、ここから次のステップです。今回から「光秀とその子」の系図を追ってみます。
A系の系図に光秀とその子の書かれた大変興味深い系図があります。それが「明智系図の歴史捜査1」に書いたA5続群書類従・明智系図です。
この系図は上野沼田藩土岐家に伝わる公式の系図、つまりA2寛永諸家系図伝・土岐系図の頼典の次に光秀の父・光隆、光秀、光秀の兄弟、光秀の子を「書き足した」ものです。「書き足した」にカッコを付けたのは、後程説明しますが意味があります。
書いた人物は光秀の子を自称する京都妙心寺瑞松院の僧・玄琳(げんりん)です。寛永八年(1631)六月十三日の光秀五十回忌に玄琳(65歳)が弟の喜多村彌平兵衛に贈ったものと書かれています。
書き足された部分は次の通りです。
光隆-光秀--女子・菅沼定盈妻
信教 女子・櫻井家次妻
康秀 女子・織田信澄妻
女子・細川忠興妻
女子・筒井定次妻
女子・川勝出羽守妻
僧玄琳
安古丸(山崎合戦討死)
僧不立(音羽川辺横死)
女子・井戸三十郎妻
十内(坂本城自害)
自然(坂本城にて死)
内治麻呂(喜多村彌平兵衛)
光秀の子に他の史料では確認できない子がたくさん書かれていますが、織田信澄妻、細川忠興妻、自然(丸)の3人は確認できます。明智秀満(三宅弥平次)の妻が他の史料で確認されていますが、この系図には書かれていません。男児では玄琳・喜多村彌平兵衛以外は全員死んだことになっています。なぜ二人だけが生き残っているのか不自然な感じもします。
子にはいろいろ疑問がありますが、この系図が決定的におかしいのは光秀の二人の弟です。信教は筒井順慶、康秀は三宅彌平次左馬助だと書かれているのです。そのような史実はなく、要は出鱈目です。
加えて、この二人の名前が問題です。土岐氏の通字である、「光」も「頼」も付いていません。土岐氏のネーミング・ルールさえ知らない人物が命名したのです。
高柳光寿『明智光秀』にも「(玄琳は)まことに怪しからぬ男。この系図は悪意ある偽系図」と一刀両断に書かれています。
ところが、この系図には「偽系図」と切り捨てられない大いなる謎があります。
それは、この系図がA2寛永諸家系図伝・土岐系図より先に作られていて、しかも「書き足した」以外の系図部分においては記載内容がA2よりもはるかに詳しいのです。その部分についていえば、むしろA2の方がこの玄琳作の系図を見て作ったとしか言いようがないのです。
この系図の方がはるかに詳しく書かれていることが何かというと、それが『土岐文書』と呼ばれる沼田藩土岐家に伝わる古文書群を系図の該当する人物の説明として書き込んだ注記です。明らかに玄琳はこれら古文書の原文を読んで写し取っています。A2ではタイトルしか書かれていない古文書の全文が書き込まれたりしているのです。
『土岐文書』に裏付けられた信ぴょう性の高さと書き足し部分の出鱈目さ。このギャップは何なのでしょうか。次回、これを推理してみます。
>>>つづく:玄琳作明智系図の謎解きへ
**************************************
『本能寺の変 四二七年目の真実』のあらすじはこちらをご覧ください。
また、読者の書評はこちらです。
>>>トップページ
>>>『本能寺の変 四二七年目の真実』出版の思い
【参考ページ】
残念ながら本能寺の変研究は未だに豊臣秀吉神話、高柳光寿神話の闇の中に彷徨っているようです。「軍記物依存症の三面記事史観」とでもいうべき状況です。下記のページもご覧ください。
★ 本能寺の変の定説は打破された!
★ 本能寺の変四国説を嗤う
★ SEが歴史を捜査したら本能寺の変が解けた
★ 土岐氏とは何だ!
★ 土岐氏を知らずして本能寺の変は語れない
★ 長宗我部氏を知らずして本能寺の変は語れない
★ 初公開!明智光秀家中法度
★ 明智系図の歴史捜査5:土岐明智氏系図の復元
そこには、光秀へのつながりが付けられていません。残念ながら現時点では信ぴょう性ある史料が見付かっていませんので、一旦、捜査の結論をそこで打ち止めてけじめをつけておきました。
さて、ここから次のステップです。今回から「光秀とその子」の系図を追ってみます。
A系の系図に光秀とその子の書かれた大変興味深い系図があります。それが「明智系図の歴史捜査1」に書いたA5続群書類従・明智系図です。
この系図は上野沼田藩土岐家に伝わる公式の系図、つまりA2寛永諸家系図伝・土岐系図の頼典の次に光秀の父・光隆、光秀、光秀の兄弟、光秀の子を「書き足した」ものです。「書き足した」にカッコを付けたのは、後程説明しますが意味があります。
書いた人物は光秀の子を自称する京都妙心寺瑞松院の僧・玄琳(げんりん)です。寛永八年(1631)六月十三日の光秀五十回忌に玄琳(65歳)が弟の喜多村彌平兵衛に贈ったものと書かれています。
書き足された部分は次の通りです。
光隆-光秀--女子・菅沼定盈妻
信教 女子・櫻井家次妻
康秀 女子・織田信澄妻
女子・細川忠興妻
女子・筒井定次妻
女子・川勝出羽守妻
僧玄琳
安古丸(山崎合戦討死)
僧不立(音羽川辺横死)
女子・井戸三十郎妻
十内(坂本城自害)
自然(坂本城にて死)
内治麻呂(喜多村彌平兵衛)
光秀の子に他の史料では確認できない子がたくさん書かれていますが、織田信澄妻、細川忠興妻、自然(丸)の3人は確認できます。明智秀満(三宅弥平次)の妻が他の史料で確認されていますが、この系図には書かれていません。男児では玄琳・喜多村彌平兵衛以外は全員死んだことになっています。なぜ二人だけが生き残っているのか不自然な感じもします。
子にはいろいろ疑問がありますが、この系図が決定的におかしいのは光秀の二人の弟です。信教は筒井順慶、康秀は三宅彌平次左馬助だと書かれているのです。そのような史実はなく、要は出鱈目です。
加えて、この二人の名前が問題です。土岐氏の通字である、「光」も「頼」も付いていません。土岐氏のネーミング・ルールさえ知らない人物が命名したのです。
高柳光寿『明智光秀』にも「(玄琳は)まことに怪しからぬ男。この系図は悪意ある偽系図」と一刀両断に書かれています。
ところが、この系図には「偽系図」と切り捨てられない大いなる謎があります。
それは、この系図がA2寛永諸家系図伝・土岐系図より先に作られていて、しかも「書き足した」以外の系図部分においては記載内容がA2よりもはるかに詳しいのです。その部分についていえば、むしろA2の方がこの玄琳作の系図を見て作ったとしか言いようがないのです。
この系図の方がはるかに詳しく書かれていることが何かというと、それが『土岐文書』と呼ばれる沼田藩土岐家に伝わる古文書群を系図の該当する人物の説明として書き込んだ注記です。明らかに玄琳はこれら古文書の原文を読んで写し取っています。A2ではタイトルしか書かれていない古文書の全文が書き込まれたりしているのです。
『土岐文書』に裏付けられた信ぴょう性の高さと書き足し部分の出鱈目さ。このギャップは何なのでしょうか。次回、これを推理してみます。
>>>つづく:玄琳作明智系図の謎解きへ
**************************************
『本能寺の変 四二七年目の真実』のあらすじはこちらをご覧ください。
また、読者の書評はこちらです。
>>>トップページ
>>>『本能寺の変 四二七年目の真実』出版の思い
 | 本能寺の変 四二七年目の真実明智 憲三郎プレジデント社このアイテムの詳細を見る |
【参考ページ】
残念ながら本能寺の変研究は未だに豊臣秀吉神話、高柳光寿神話の闇の中に彷徨っているようです。「軍記物依存症の三面記事史観」とでもいうべき状況です。下記のページもご覧ください。
★ 本能寺の変の定説は打破された!
★ 本能寺の変四国説を嗤う
★ SEが歴史を捜査したら本能寺の変が解けた
★ 土岐氏とは何だ!
★ 土岐氏を知らずして本能寺の変は語れない
★ 長宗我部氏を知らずして本能寺の変は語れない
★ 初公開!明智光秀家中法度