昨夜は、区内でインクルーシブ保育を実践されている方々のお話を伺うという、大変貴重な席に同席をしていました。
分け隔てなく子どもが安心できる居場所をつくり、個性を大切にして行きたいという理念と事業運営のバランスを取る難しさ、子どもや保護者と直接接し必要とされている事を実感しているものの、提供するには幾重にもハードルがある事など。

事前に調べてみると、関連した動きがありました。
本年8月には厚生労働省から「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令案(概要)」が発表されました。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000239975
その中でインクルーシブ保育に関連し、「保育所等の設備や職員を活用した社会福祉サービスを必要とする児童等の社会参加への支援が進むよう、設備運営基準及び家庭的保育事業等基準を見直し、必要な保育士や面積を確保することを前提に、利用児童の保育に支障が生じない場合に限り、職員の兼務や設備の共用を可能とするため、今般この規定に例外規定を設け、保育所及び家庭的保育事業所等については他の社会福祉施設を併設する際に特有の設備・専従の人員についても共用できることとする改正を行う。(抜粋)」とあり、
これまでの分離から共生に舵を切って行くこと。
本年9月には、国連から「特別支援教育の廃止」を勧告されたことなどは大変大きな出来事ですが、報道ではあまり触れる事が出来無かったのは歯がゆい思いです。
以前、杉並区の小中一貫校建設時に、特別支援教室の完全に近い分離が、子どもたちの成長に悪影響を与えると心配された区民の方から、改善を求める陳情が出され、審査をさせて頂いたのを思い出していました。
迷いながらも、現行を支持し、引き続き当事者の意見を聞きながら、必要があれば改善を求めました。この経緯を以下のブログに纏めてあります。「必要があれば改善」とはしたものの、その間も子どもたちにとっては大切な成長の時期であり、迷った末の決断でした。
山本あけみブログ 2018.9.22 https://blog.goo.ne.jp/akemiyamamoto/e/fb45efe64de4145bb91ad275cad0b81a
インクルーシブ保育や教育は、これまでの分離をして充実を目指す方向性からは真逆であって、自治体の判断だけでは実現できないと考えています。国制度を変更し、基準や規制、そして補助スキームが変わらなければ、自治体は動けない。でも、必要性を直に感じ、実践している現場からは国は遠く、今ある課題解決までの道のりが遠い。
日本の国が抱える閉塞感や生きづらさという大問題は、個人の問題ではなく、国そのものの制度が作り出しているものでは無いのか。常に持っている疑問が、少しづつ確信に変わっています。
昨夜の実践者の方々の話し合いを眩しく拝見しながら、自治体議員は、暮らしの中から課題を見出し、解決までの道のりを見通し賛同者を増やしながら、少しずつ前進していく事が責務であり、私もその部分での実践者でありたいと考えていました。













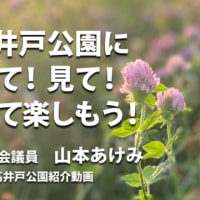






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます