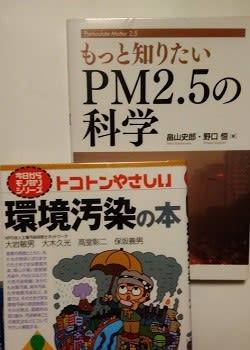散歩がてら雨の中で咲く草花などを見てみようと出かけた。草花たちも、何となく重く冷たそうだった。

雨水を背負ってグニャと首を垂れていた。只でさえ、終わりの時期で傾いているのに地面につきそうなくらい垂れていた。花びらも下を向いていた。茎には触れば落ちそうな水滴が多数ついている。触るとしずくになって落ちた。

大分色づいてきたまゆみの実にはコスモスの茎から垂れ下がるものよりも大粒の水滴がついている。レンズのように透明だ。やがて落ちるのだろうか、水滴が揺れているように見えた。
インターネットで特別に「雨に咲く花」があるのかと探したが、昔流行した雨に咲く花という歌のサイトが並ぶ。井上ひろしさんの「およばぬことと・・・・」という、歌詞とメロディーが浮かんだ。雨に咲く花という名の花はなさそうだ。その季節の雨の中の花すべてを言うのかな。

石の乱積みの擁壁の下に、石と他の雑草に隠れるようにして咲いている野菊。花と葉に小さな水滴がついていた。


水滴はあまり目立たない。何しろ鈴なりになる赤い実が目立つピラカンサ。その赤が雨によりひときわ映えて見えた。これは雨に勝つ存在かもしれない。

萩の葉に無数にたまる水滴。

草木ではないが、大きな岩の表面に雨筋が流れた軌跡が見える。まるで涙のようだ。

手前の大きな葉はしだれ桜の葉。垂れさがるしずくには、背景にある、枯れつつあるリョウブの葉が映っていた。
今日のテーマ―は、雨に咲く花のつもりだった。勇んで外出したが見る人間の心が冷たい雨にめげていたためか、花、本来の華やかな美しさは見いだせなかった。カメラは濡れる。雨合羽のフードをかぶると、耳がふさがれ道路を走る車の音が聞こえづらくなる。のんびりと花を見ていられない。気疲れする。
ドライブだったら少しは良い風景を見つけることができるかと思い、買い物がてら通常の店より遠いところに行った。道すがら、雨でスリップしたのか、小さな交通事故現場に出会った。次第に雨脚も強くなり、ワイパーもハイスピードにしなければならなかった。
雨は、水は、絶対必要だ。水があるから生命をはぐくんでいる。そのことは分かっているのだが、雨はやはり気持ちを消沈させる。
東京では、最高気温が14℃強だった。10月に15℃を下回ったのは46年ぶりとのこと。
今夜は押し入れからこたつを出し、温まることにした。

雨水を背負ってグニャと首を垂れていた。只でさえ、終わりの時期で傾いているのに地面につきそうなくらい垂れていた。花びらも下を向いていた。茎には触れば落ちそうな水滴が多数ついている。触るとしずくになって落ちた。

大分色づいてきたまゆみの実にはコスモスの茎から垂れ下がるものよりも大粒の水滴がついている。レンズのように透明だ。やがて落ちるのだろうか、水滴が揺れているように見えた。
インターネットで特別に「雨に咲く花」があるのかと探したが、昔流行した雨に咲く花という歌のサイトが並ぶ。井上ひろしさんの「およばぬことと・・・・」という、歌詞とメロディーが浮かんだ。雨に咲く花という名の花はなさそうだ。その季節の雨の中の花すべてを言うのかな。

石の乱積みの擁壁の下に、石と他の雑草に隠れるようにして咲いている野菊。花と葉に小さな水滴がついていた。


水滴はあまり目立たない。何しろ鈴なりになる赤い実が目立つピラカンサ。その赤が雨によりひときわ映えて見えた。これは雨に勝つ存在かもしれない。

萩の葉に無数にたまる水滴。

草木ではないが、大きな岩の表面に雨筋が流れた軌跡が見える。まるで涙のようだ。

手前の大きな葉はしだれ桜の葉。垂れさがるしずくには、背景にある、枯れつつあるリョウブの葉が映っていた。
今日のテーマ―は、雨に咲く花のつもりだった。勇んで外出したが見る人間の心が冷たい雨にめげていたためか、花、本来の華やかな美しさは見いだせなかった。カメラは濡れる。雨合羽のフードをかぶると、耳がふさがれ道路を走る車の音が聞こえづらくなる。のんびりと花を見ていられない。気疲れする。
ドライブだったら少しは良い風景を見つけることができるかと思い、買い物がてら通常の店より遠いところに行った。道すがら、雨でスリップしたのか、小さな交通事故現場に出会った。次第に雨脚も強くなり、ワイパーもハイスピードにしなければならなかった。
雨は、水は、絶対必要だ。水があるから生命をはぐくんでいる。そのことは分かっているのだが、雨はやはり気持ちを消沈させる。
東京では、最高気温が14℃強だった。10月に15℃を下回ったのは46年ぶりとのこと。
今夜は押し入れからこたつを出し、温まることにした。