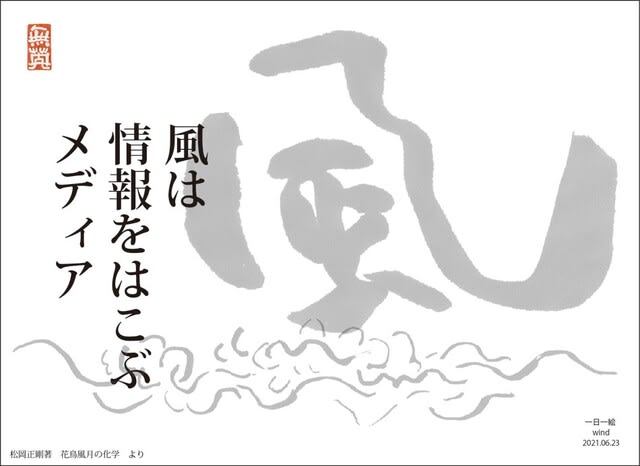ぎぃーぎぃーと流氷の鳴く厳冬期
遙か沖一直線の流氷を
オホーツク人は待ち焦がれをり
・・・・・・・・・・・

先週、日本列島は10年に一度という寒波に包まれた。
道内でも列車の運休や航空便の欠航が目立ち、事故も多発した。
被害を受けた方々にはお見舞い申し上げたい。
大寒は過ぎても、節分までは寒の内。
用心は怠れない。
「たましひの繭となるまで吹雪けリ」斎藤玄。
魂が繭の中に籠ろうとするほどの吹雪とは。
函館生まれの俳人の句からは、北国に生きるものこそが抱く厳かな冬の感覚が伝わってくる。
「繭」は本来夏の季語で、ふわふわとした温かいイメージが付随する。
繭からつくられる絹織物は保温性と吸湿性に優れており、肌にも優しい。
カイコのように繭に包まれぬくぬくと冬を過ごしたい。
ただし、カイコの繭が暖房のためと考えるのは人間の勝手な解釈らしい。
しなやかな糸を吐く目的をカイコ自身は知らず、生体内に遺伝的に組み立てられた本能がそうさせているのだとか(伊藤智夫著「蚕はなぜ繭をつくるか」)
成長に必要なクワの葉に対する食欲は旺盛である。
2、3日で体重が倍になるほどの速さでむさぼる。
よく食べ、よく寝て、しかも生産性が高い。
人間として見習いたいものである。
この冬がことさら厳しく感じるのは、物価高とは無縁ではあるまい。
不用意に出かければ財布の中身が寒さを増す。
荒天時は、不要不急の外出を控える必要もある。
繭ごもりを決め込んでじっと春を待つとするか。(北海道新聞卓上四季2023.1.30より)
・・・・・・・・・・・
繭ごもりを決め込むといっても冬の北海道は暖房が欠かせないので、この電気と灯油の値上がりは非常に厳しいものがあります。
北海道には光熱費の減税をお願いしたいものです。
電気料金は特に電力会社が絶対損をしない仕組みを考えて電気料金を徴収しているのに、と思います。
~~~~~~~~~~~
一月も今日で終わりですね。
網走は今が厳冬期。
一日も早く流氷が来て、海にめぐみをもたらしてくれることを願います。
そして海明け後は豊かな海産物が捕れますように。