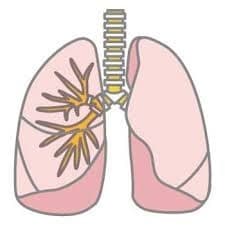
こんにちは。
記事の更新が少し遠のいてしまいました。
今回はDuchenne型筋ジストロフィー(以下、DMD)児の呼吸リハビリテーション(以下、呼吸リハ)の開始時期について、少しお話をしてみたいと思います。
DMD患児への呼吸リハは、「神経筋疾患・脊髄損傷の呼吸リハビリテーションガイドライン」をはじめ、DMDの呼吸リハについて書いている総説・解説の多くで「%肺活量(以下、VC)50%以下あるいはVC1500ml以下」などの基準が書かれています。
最近はステロイド治療の進歩もあり、この基準に照らして考えると呼吸リハ自体の導入年齢が遅くなっている傾向もあるような気がします。
そもそもこれらの基準はこの値を下回ると、最大呼気流速(以下、PCF)が有効な咳嗽力であると言える160L/minを下回るという報告から来ています。
有効な咳嗽力が低下すれば、誤嚥や窒息、肺炎といったリスクが高まるため、この基準を目安に介入を進める事は間違いでないですし、これまでのDMD患者に対する呼吸リハはその基準に基づいてある程度の成果を挙げてきたと思います。
ですが、私はずっと疑問に感じていました。
それまでは積極的に呼吸リハをする必要はないのか?と。
今回お話するのは、もうちょっと早めに呼吸リハを始めてもいいのでは?という内容です。
本当に理論上の話でしかないので、何の根拠もないことを改めてここに記しておきます。
それでは長くなりましたが、さっそくお話をしていきたいと思います。
まず基本的に肺の成長に関して触れていきたいと思います。
肺は胎児のときにはだいたい妊娠7週ごろから形成が始まり、24~26週あたりで構造が完成します。そして28週ごろに肺胞がスムーズに拡張するために必須である肺サーファクタントというものが産生されるようになります。この際に呼吸様胸郭運動が胎児にも認められ、胸郭が拡大するとともに気管内腔および肺実質との圧力勾配が発生します。この圧力勾配が肺成長と気管支分岐を進めていくと言われています。つまり肺の成長には機械的刺激が大事ということです。

これは出生後も同様で、胸郭の骨化、肋間筋筋緊張亢進、呼吸筋による胸腔内陰圧増加により、胸郭が拡大する外方向に対する抵抗力は増加します。その結果、胸郭の中にある肺が大きく広がるように陰圧を高く受けるため、発達中の肺には大きな機械的刺激が増加します。これは思春期成長に先立って急激に始まり、胸骨の縦方向の成長による胸郭拡大・呼吸筋力増強に伴い、肺にかかる陰圧が増加して肺活量も増加します。肺活量は身長に比例することが言われており、そしていわゆる成長期を過ぎた後も肺の成長は続き、一般的に肺活量は19歳頃にプラトーを迎えると言われています。ここで肺の成長は止まりますが、成熟肺でも機械的刺激が肺の再成長の主要な刺激になることが、犬を用いた実験的肺切除モデル等で示されています。
現在、DMD患者に行われているような強制吸気(以下MIC)の効果は、このようなモデルにも基づいて説明ができるのかもしれません。
さてここでDMD患者の呼吸機能についてもお話をしたいと思います。
DMD患者の呼吸不全の特徴は、いわゆるⅡ型呼吸不全(拘束性換気障害)で呼吸筋の筋力低下や脊柱変形による胸郭運動の障害などにより進行し、肺活量の低下を認めていく点にあります。そして肺活量の増加は過去の報告では10歳頃をピークに、その後は年間8~8.5%減少していくと言われています。
この呼吸不全の原因としては呼吸筋の筋力低下やそれに伴う深呼吸・欠神の減少が言われており、他にもDMD児は低身長の傾向があるため、体格による肺活量の制限もあるかと思われます。
長々と話してしまいましたが、要は肺の成長には肺に陰圧をかけて機械的刺激をかける必要があるにも関わらず、DMD児達は十分に深呼吸や欠神を行えないために肺に対する機械的刺激が不十分になっているのではないか?ということが、今回の言いたいことです。
しかし私が調べた限りではこのような報告は見当たらず、実際のところはわかりません。
ただもし予防的にアンビューバッグを用いたMICなどにより肺の成長を促せるとすれば、長期的に呼吸機能についての予後が改善される可能性があります。
ついでに自分の経験上、予防的に介入をした子はVCが上昇し、呼吸機能が良好である印象があります。ただ身長が大きく伸びたことによる影響も考えられるので、こういった体格の変化について補正して、きちんと調べなければわかりません。
今後、そういったこともぜひ調べていけたらと思います。
最後までお読みいただいてありがとうございました。
C5(PT)
東埼玉病院リハビリテーション科ホームページはこちらをクリック









