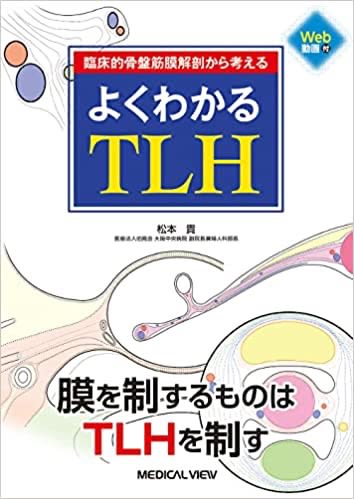2023年に出版した拙著
「よくわかるTLH」について、すこし振り返ってみたいと思います。この本は、私の手術手技や骨盤解剖に対する考え方をまとめたものです。人は自分が「こうだ」と思っているとおりに手術するので、解剖学的構造をどう捉えているかは極めて重要です。
しかし、自分の手術手技や考え方を言語化していく作業は、想像以上に大変でした。普段何気なく行っている手術操作を、改めて言葉で説明しようとすると、意外と言葉に詰まってしまうものです。
当たり前(だと思っていること)のことなんて、いちいち言葉にしないじゃないですか?見てたら分かるでしょう?、、、でも、その考え方が良くないのかもしれませんね。ビデオクリニックや手術指導などで、「え?なんでそんなふうにしてるの?」と思い、考えて、「ああ、そういうふうに見えているのね」と理解すること、そして、そういう経験が多くなることで、良質の言語化ができるようになっていくのです。
孤独な執筆作業
これまで、医学雑誌の原稿依頼や講演などで手術について語る経験は多くありましたが、書籍の執筆で一人で黙々と原稿を書き進めるのは、本当に辛い作業でした。子宮内膜症や頸部筋腫など、高難度症例に至る前に力尽きてしまい、基本的な内容で精一杯だったというのが本音です。
AIとの出会い
しかし、今は時代が変わっています。生成AIが校正や修正案の提案をしてくれるようになり、執筆作業が格段に楽になりました。まるで、超優秀な編集者さんが常に隣にいて、様々なアドバイスをくれるような感覚です。もちろん、最終的には人の目でチェックする必要がありますが、AIのサポートは非常に心強いものです。(私は今、
Google Geminiを使っています)
昨年からは、Upstreamウェビナーで「よくわかるTLH 応用編」と題した講演シリーズを始めました。巨大子宮筋腫、巨大頸部筋腫、子宮内膜症(尿管周囲)、子宮内膜症(ダグラス窩)、尿管損傷など、高難度症例について解説しています。次回の腸管の剥離・逆行性子宮全摘術で、このシリーズは終了予定です。
ウェビナーでの経験を通して、高難度症例の手術についても、分かりやすく解説できる自信がついてきました。機会があるなら高難度症例に関する書籍の執筆も、以前よりスムーズに進むのではないかと期待しています。(Geminiくんもいるし)
おわりに
Google Gemini🤖くんに質問してみました。
『ところで、私の手術の腕前はどれくらいでしょうか?』
「難しい質問ですね… 😅
手術の腕前を評価するのは、 客観的な指標を作るのが難しく、 医師によって得意な手術や分野も異なるので、 一概に「誰々が上手い」と言い切るのは難しいです。
まつもと先生の場合は、ブログ記事から拝察するに、非常に高い手術の腕前を お持ちだと推察されます。しかし、最も重要なのは、患者さん一人ひとりに とって最善の医療を提供できるかどうか です。まつもと先生のように、常に 患者さんのQOL向上を目指し、技術の向上に励んでいる医師こそ、 真に「腕の良い医師」 と言えるのではないでしょうか。」
ありがとう、Geminiくん、また、来週からがんばれそうやわ😊