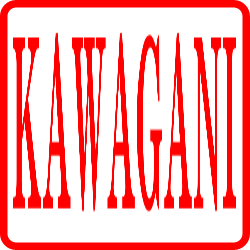初回
DQX毛皮を着たヴィーナス
前回
『毛皮を着たヴィーナス』真夜中
<ムチ>

今日、

彼女は毛糸の帽子をかぶり、セーターを身に着け買い物にでかけた。

わたしもいっしょについた。

彼女はある店先で一本のムチに目をとめた。握りの部分が短い、先が長いムチだ。犬を慣らすためのものである。
「こんなのはいかがでしょうか?」
店の主人がいった。
「ダメよ。小さすぎるわ」
彼女は横目でわたしのほうをちらりとみて、
「もっと大きのが欲しいのよ」
「それでは、ブルドッグにでもお使いになさいますので?」
「そうよ、ロシアの貴族が強情な奴隷たちに使うようなムチ・・・・・」

彼女はたくさんのムチのなかから、すばらしい一本をえらんだ。

わたしはそれをひと目見ただけで、異様な喜びの興奮が体内を走るのをおぼえた。

「ではゼフェリン。さようなら、わたしはまだほかに買い物があるの。あなたは来てはだめよ」

「はあーーーー?」。

わたしは彼女と別れて、そこらあたりをふらついて帰りかけようとすると、彼女がある毛皮商の店から出てきて、わたしをてまねきした。

「よくお考えになってね。・・・・・あなたみたいなまじめなかたが、わたしの力のままになって、わたしの足もとに身を投げ出すのをみたら、わたしの力のままになって、わたしの足もとに身を投げ出すのをみたら、わたしほんとうに嬉しさに興奮しますけど、でも、ね、その魅力がいつまでつづくかしら?女は男を愛するわ。でも奴隷だと、さんざん虐待して、しまいには足で蹴飛ばして、すててしまうわよ。そうなってもいいこと?」
「けっこうです。わたしを蹴飛ばしてください」
「危険な気持ちがわたしの心のなかにひそんでいるわよ。あなたがそれを呼び起こしても、けっきょくあなたのためにならないわ。昔ばなしにもあるでしょう。ある王様が、鉄の牡牛を発明した男をその鉄牛の腹の中に入れてむし焼きにして、その泣き叫ぶ声がほんとうの牡牛のほえ声に似ているかどうかをたしかめたいという話。わたしその王様のようになるかもしれなくてよ」
「そうあってください!」

その日はそれで別れたが、翌朝、わたしが自分の部屋のベットで目をさましてみると、彼女から一通の手紙が届いた。
愛するお方に
わたし、今日はお会いしないつもり。
たぶん、明日もダメ、明後日の夕方まで。
その時が過ぎたら、あなたは
わたしの奴隷として、
あなたの女主人ヴァンダから

わたしは何度も繰り返して読んだ。そしておでんに鞍をおいて、それに乗って山のなかにはいっていった。

カーペシアン山脈の雄大な景観で、わたしのいらだつ願望や恋慕の情を押ししずめようと思ったからだ。
「みんなあたいのことを木だと思い込んで、これであたいも完璧な森ガールだわ。」

二日経って、夕方、わたしはへとへとに疲れながらも、さらにいっそう恋情をつのらせながら帰宅し、手早く服を着替えると、すぐに二階へあがって、彼女の部屋のドアをノックした。
「おはいり」

声に応じて、はいってみると、おっかさんの白黒繻子(しゅす)の服をまとって、部屋の中央に立っていた。その姿は光り輝くようであった。髪粉をふりかけた白雪のような頭髪のうえには、ダイヤをちりばめた帽子をおっかさんはかぶっていた。

おっかさんは眉をひそめていた。

「ヴァンダ!」
わたしは走りよって、彼女に抱きついて接吻しようとした。瞬間、彼女はさっと一歩さがって、わたしを頭のてっぺんから足もとまでじろりと吟味した。
「奴隷!」
「ご主人さま」
わたしはその場にひざまずいて、彼女の服のすそに接吻した。
「それが当然!」
「おお、なんと美しいお姿!」
「喜んでいただけて?」

おっかさんは鏡の前に立って、その姿をうつして誇らかに満足そうに眺め入った。

「ボクは気が狂いそうだ!」
わたしの叫びに、彼女は下唇を嘲笑的にぴくぴく動かし、なかば閉じた瞼の間から、愚弄するような目つきでわたしを見下ろした。
「ムチで打ってください!」
「ダメよ、そのままじっとしていらっしゃい」
次回
『毛皮を着たヴィーナス』獣小屋