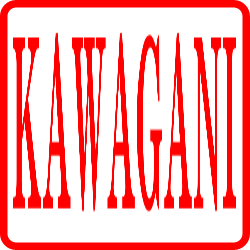初回
DQX毛皮を着たヴィーナス
前回
『毛皮を着たヴィーナス』あらくれ
<王子>

「ゼフェリン。キミとヴァンダの関係はどこにあるんだ?」

「王子になっただっち」
「王子?・・・・・」

今日、ロシアの王子が街の散歩道にはじめて姿を現した。
「もうじき退院ですね」
「リハビリするだっち」
運動家らしい体格と立派な容貌と堂々たる態度をしていたので、人々の注目の的になった。女性たちがどきもをぬかれて、ぽかんと口をあけて眺めている間を、彼は憂鬱げに歩いていた。

彼には二人の召使いが従っていた。一人は黒人で赤い繻子(しゅす)の盛装をし、もう一人はサルカシア人で、きらきらする制服で身をつつんでいた。

王子は、すれちがいざまヴァンダに目をとめ、冷たい刺すような目つきで、彼女を追った。彼女が通り過ぎてからも、彼は彼女の後ろ姿を見送っていた。
彼女は、晴れやかな緑の目でむさぼるように王子をみた。そして二度目に彼に出会ったときは、たくみな媚態を示して、しだいに彼に近づいた。わたしは窒息するばかりであった。帰路、わたしがそれを指摘すると、彼女は眉をよせて、

「あなたはわたしに、なにを要求なさるの。あの王子は、わたしが好きになれる人よ。わたしを恍惚とさせてしまったんですもの。それにわたしは、あなたとお約束したとおり、自由なのよ」
「それでは、もうボクを愛していないのですか?」
わたしはがく然とした。
「いいえ、愛しているわ。愛しているのはあなただけよ。でも、わたしの機嫌をとってくれるような王子さまが、現れたらしいわね」
「ヴァンダ」
「あなたはわたしの奴隷よ。わたしはヴィーナス、毛皮を着たヴィーナス、そうじゃなくって?」
「・・・・・毛糸の」
「え?なんですって?!」
わたしは彼女の言葉におしつぶされてしまった。
彼女の冷ややかな態度は鋭い短剣のようにわたしの心を突き刺した。

「すぐにあの王子の名前とお住まいと境遇をしらべておいで」
「しかし」
「命令をききなさい」

彼女の声は、午後にならないうちにしらべあげて、彼女に報告した。彼女は肘掛け椅子に身をもたれながら、微笑を浮かべて直立不動の姿勢のわたしから報告をきくと、満足そうに軽くうなずいた。

「足台をもってきて」
彼女の命令に従って、わたしは彼女の足もとへ足台を運んできて、ひざまずいたまま、
「結局、どうなるのでしょう?」
と悲しげにたずねた。

「まだなにもはじまってやしないじゃないの」
彼女は、ふざけたように笑いだした。
「あなたは予想以上に無情です」
わたしは不愉快な気持ちをぶちまけた。

「まだなんにもやってやしないのよ。それなのに、どうしてそう無情よばわりをなさるの。あなたの理想をかなえてあげて、あなたを足でふみつけ、ムチで打ったら、なにか起きるとおっしゃるの?」
「あなたは、ボクの夢をあまりにもまじめに取りすぎます」
「まじめにとりすぎてどうしていけないの。お芝居や茶番劇なんか、わたし大嫌いよ」

「ヴァンダ、ボクのいうことをよく聞いてください。ボクとあなたは、無限に愛し合って非常に幸福です。それなのにあなたは、出来心のために、二人の未来を犠牲にするのですか?」
「出来心じゃないわ」
「それじゃ、なんですか」
「たぶん、わたしの性質のなかにひそんでいたなにかよ。あなたがそれを呼びさましさえしなかったら、けっして表面へあらわれてこないものよ。でも、今ではもうダメ。力をもった衝動となって、わたしのからだじゅうにあふれてしまっているわ。いまさら、あなたがそれを取り消したいといいだしてもダメよ。あなたはそれでも男なの?」

「ボクの大好きな、かわいいヴァンダ!」
わたしは彼女をなだめすかして接吻した。
「あなたは男じゃなかったの?」
「それなら、あなたは?」
「わたしは強情よ。わたしには空想なんかないわ。実行力もないわ。でもこうときめたら、わたし、やりぬくわよ。もういいから、出て行ってちょうだい!」
「ヴァンダ!」
わたしと彼女は立ちあがって、顔と顔をつき合わせた。

「いまはじめて、あなたには、わたしというものがわかったのね。それなら、もう一度いうわ。わたしは無理じいにあなたを奴隷にするつもりじゃないから、いやならいやといってもいいわ」
「ヴァンダ!」
わたしは興奮のあまり、目に涙をためて、
「ボクがどんなにあなたを愛しているか、あなたには知らないのですか?」
「はっきり、きめてちょうだい。無条件で、奴隷をつづけるの?」
「もしも、ボクがいやといったら?」
「そのときは・・・・・」

彼女は冷ややかな態度で、両腕を乳房のうえあたりに組み、邪悪な薄笑いを浮かべて、ぐいと一歩詰め寄ってきた。その様子は暴虐な女性そのものであった。慈愛も親切もなにもない激情の女だった。

「それなら、それでもいいわよ」
「怒っているんですね。わたしを罰するつもりでしょう」
「違うわ。縁を切っていただくだけ、わたし、いつまでもあなたを縛ってなんかおきはしないわ。あなたはもう、自由よ」

「ヴァンダ、ボクがこんなに恋い募っているのに・・・・・」
「そうね、あなたはわたしを崇拝していらっしゃるわね。でもあなたは卑怯者で、ウソつきで、約束を破る人よ、さっさと出ていってちょうだい」
彼女はわたしに軽蔑のまなざしを投げつけた。
「ヴァンダ!」

「悪者」
「・・・・」

わたしは返す言葉もしらず、心臓のなかで血汐が煮えたぎる思いで、彼女の足もとに身を投げ出して泣きふせった。
「その涙もいっしょに出て行っていただくわよ」
彼女は悪魔的に笑いだした。

「ああ、後生ですから、そういわないでください」
わたしは我を忘れて哀願した。そして彼女の膝にすがりついて、彼女の手に接吻した。
「わかったわ。あなたは奴隷になって、わたしのムチを味わうのね。あなたは蹴られれば崇拝し、虐待されればされるほど、わたしを尊敬するのよね、犬みたいな性質。こんどは、わたしというものをあなたにわからせてあげるわよ」

そういって彼女は荒々しくわたしを引きよせ抱きしめ、涙のうちに微笑しながら、わたしの両目の涙を唇と舌で吸いとりはじめた。

次回
『毛皮を着たヴィーナス』交換