知床観光船沈没事故5・検証◇船舶管理者の安全意識が緩むのは国交省の緩い検査

■まともな船舶検査が行われないほどの検査体制・人員確保の脆弱さが事故の遠因に
 事故後半年が経過したが、投稿者はさらに追及したい。沈没により多くの死者・行方不明の方が発生したことに対し、今までは知床遊覧船側・管理者(社長)の瑕疵を述べてきた。社長を擁護する気は全くないが、ここからは背景にある国交省の船舶全般の監査・検査体制の甘さを捉える。さらには安全より利益優先の新規参入業者を許した、国による「規制緩和」(次号説明)がもたらした影響を説明する。投稿者が、新聞やTVニュースなどをまとめた。まず国交省による旅客船や貨物船の運航事業者に対し、海上運送法(下表・左)によって3年に1回ペースで定期監査を行っている。しかし実態は、十分な監査がなぜ行われていない。表・右の通り2020年度に全国の定期、事故が起きた場合の特別監査を合わせて1919件実施され、行政指導15件・行政処分は2件だった。処分に至るケースは少なく、業者名公表を伴う安全確保命令に留まり、過去10年で事業停止0件、許可取り消しは2件に過ぎない。監査は、各地の運輸局職員が事前に事業者と日程調整して実施される。現に知床遊覧船の元従業員は、「突然、抜き打ちで来る訳ではないので、その時だけどうにかすればいいという、緩い雰囲気だった」と話す。これほど“緩く甘い” 監査なので、船舶管理者の安全意識は薄くなるのは当然だ。船舶管理者の安全意識が緩むのは、国交省の緩い検査が遠因になっている。
事故後半年が経過したが、投稿者はさらに追及したい。沈没により多くの死者・行方不明の方が発生したことに対し、今までは知床遊覧船側・管理者(社長)の瑕疵を述べてきた。社長を擁護する気は全くないが、ここからは背景にある国交省の船舶全般の監査・検査体制の甘さを捉える。さらには安全より利益優先の新規参入業者を許した、国による「規制緩和」(次号説明)がもたらした影響を説明する。投稿者が、新聞やTVニュースなどをまとめた。まず国交省による旅客船や貨物船の運航事業者に対し、海上運送法(下表・左)によって3年に1回ペースで定期監査を行っている。しかし実態は、十分な監査がなぜ行われていない。表・右の通り2020年度に全国の定期、事故が起きた場合の特別監査を合わせて1919件実施され、行政指導15件・行政処分は2件だった。処分に至るケースは少なく、業者名公表を伴う安全確保命令に留まり、過去10年で事業停止0件、許可取り消しは2件に過ぎない。監査は、各地の運輸局職員が事前に事業者と日程調整して実施される。現に知床遊覧船の元従業員は、「突然、抜き打ちで来る訳ではないので、その時だけどうにかすればいいという、緩い雰囲気だった」と話す。これほど“緩く甘い” 監査なので、船舶管理者の安全意識は薄くなるのは当然だ。船舶管理者の安全意識が緩むのは、国交省の緩い検査が遠因になっている。

 他方、国交省は小型旅客船について船舶安全法(表・左)に基づいて、5年に1度の船舶検査も行う。国の代行機関として、小型船舶検査機構(JCI)が対応する。JCIは全国31か所・140人しかいない。しかも2020年度の対象船は約32万隻(検査は5年に1度)。検査員は業務用車で現場に赴き、1日平均3.2隻、154㎞を移動する強行軍。3分の2が春から夏に集中し、その時期は1日4.6隻の検査に膨れる。船体・機関・無線設備・救命設備などを確認するが、ある船の所有者は「検査は資料や法定備品が揃っているかを調べ、すぐ終わる」。投稿者としてはおそらく形式な検査、目視(見ただけ)など検査にも匹敵しないものだと思われる。短時間で数をこなさなければならず、消化できないはず。検査体制が、極めて脆弱だ。TVでお馴染みの東海大の山田吉彦教授は、「検査数に対しJCIの人員が追い付いていない」「監査も抜き打ちじゃないと意味をなさない」と指摘する。しかし国交省は19年に150人いた検査員を、今年度138人に削減しようとする逆行計画だ。海難事故の弁護士は、「忙しく、”まともに”検査をやっていられない」とも言う。こうした国交省の無責任かつ、まさしく”お役所仕事”な検査体制が、巡り巡って重大な海難事故を起こしたとも言える。
他方、国交省は小型旅客船について船舶安全法(表・左)に基づいて、5年に1度の船舶検査も行う。国の代行機関として、小型船舶検査機構(JCI)が対応する。JCIは全国31か所・140人しかいない。しかも2020年度の対象船は約32万隻(検査は5年に1度)。検査員は業務用車で現場に赴き、1日平均3.2隻、154㎞を移動する強行軍。3分の2が春から夏に集中し、その時期は1日4.6隻の検査に膨れる。船体・機関・無線設備・救命設備などを確認するが、ある船の所有者は「検査は資料や法定備品が揃っているかを調べ、すぐ終わる」。投稿者としてはおそらく形式な検査、目視(見ただけ)など検査にも匹敵しないものだと思われる。短時間で数をこなさなければならず、消化できないはず。検査体制が、極めて脆弱だ。TVでお馴染みの東海大の山田吉彦教授は、「検査数に対しJCIの人員が追い付いていない」「監査も抜き打ちじゃないと意味をなさない」と指摘する。しかし国交省は19年に150人いた検査員を、今年度138人に削減しようとする逆行計画だ。海難事故の弁護士は、「忙しく、”まともに”検査をやっていられない」とも言う。こうした国交省の無責任かつ、まさしく”お役所仕事”な検査体制が、巡り巡って重大な海難事故を起こしたとも言える。










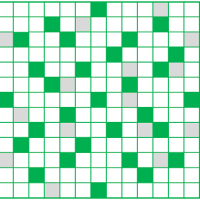











 1月 ベスト10
1月 ベスト10 










 2月のピックアップ!
2月のピックアップ!














