奈良市職員兼業疑惑で病気休暇は夏に集中、市長「異常です」
9/8(金) 19:28配信 毎日放送
毎日放送
奈良市の職員が病気休暇中にプールの売店で兼業をしていたのではないかという疑惑。調査にあたった奈良市が8日会見を開き、直近の4年間は病気休暇が夏に集中していたと明かしました。
「はい、いらっしゃーい!ラーメンどうですかー!」(職員)
奈良市環境部の職員が病気休暇中に妻が経営するプールの売店で働き、兼業をしているのではないかという疑惑。
Q.(店の業務)していますよね?
「してないです。教えるのは教えてます」(職員)
Q.店頭で声を出すのも指導?
「当たり前です。『いらっしゃいませ』は言ってもらわないと」(妻)
兼業は、地方公務員法などで原則禁じられています。仲川げん奈良市長は8日の会見で、うつ病という医師の判断は適正であると確認したうえで、今年を含め直近の4年間は夏に集中して休暇を取っていたことを明かしました。
「昨年がトータルで89日休暇を取得。このうち7月8月で41日。おととしは89日のうち47日が7月、8月」(仲川げん奈良市長)
計画的に休んだかは現在情報収集中だということですが…
Q.夏に集中していることはどう感じる?
「異常ですね、一市民の感覚とすれば」(仲川げん奈良市長)
異常という認識を示しましたが、職員の行為が兼業かどうかの判断はまだできないと、言葉を濁しました。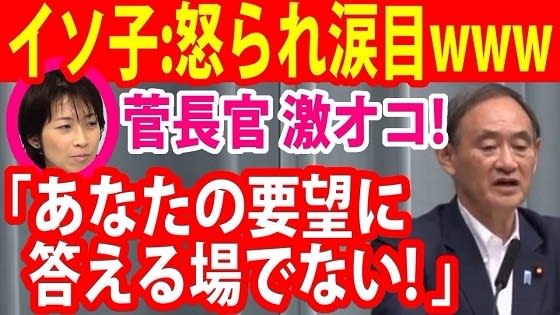

9/8(金) 19:28配信 毎日放送
毎日放送
奈良市の職員が病気休暇中にプールの売店で兼業をしていたのではないかという疑惑。調査にあたった奈良市が8日会見を開き、直近の4年間は病気休暇が夏に集中していたと明かしました。
「はい、いらっしゃーい!ラーメンどうですかー!」(職員)
奈良市環境部の職員が病気休暇中に妻が経営するプールの売店で働き、兼業をしているのではないかという疑惑。
Q.(店の業務)していますよね?
「してないです。教えるのは教えてます」(職員)
Q.店頭で声を出すのも指導?
「当たり前です。『いらっしゃいませ』は言ってもらわないと」(妻)
兼業は、地方公務員法などで原則禁じられています。仲川げん奈良市長は8日の会見で、うつ病という医師の判断は適正であると確認したうえで、今年を含め直近の4年間は夏に集中して休暇を取っていたことを明かしました。
「昨年がトータルで89日休暇を取得。このうち7月8月で41日。おととしは89日のうち47日が7月、8月」(仲川げん奈良市長)
計画的に休んだかは現在情報収集中だということですが…
Q.夏に集中していることはどう感じる?
「異常ですね、一市民の感覚とすれば」(仲川げん奈良市長)
異常という認識を示しましたが、職員の行為が兼業かどうかの判断はまだできないと、言葉を濁しました。
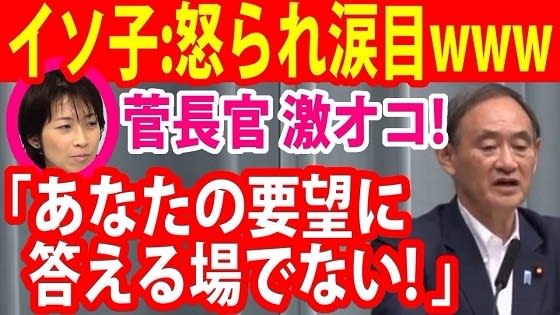














 威圧は出来るが、対艦ミサイルが発達してる現代戦では、軍艦は殆ど無力。
威圧は出来るが、対艦ミサイルが発達してる現代戦では、軍艦は殆ど無力。





