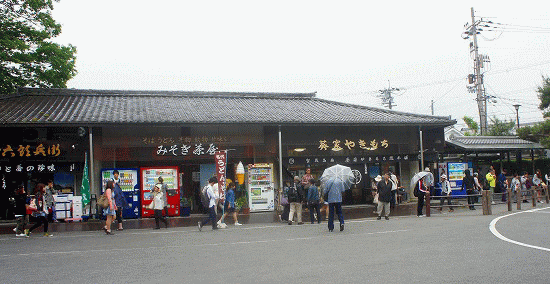
 25/15℃
25/15℃
柳出町からバスに乗ると堀川通を北に上がり、上賀茂神社の近くのバス停を降り前にスーパーがあったのでお茶を買い出るとポツリと雨が降り出してきたが神社へ行くと、ここも人が多い。 神社の鳥居前には茶店があるが茶店はリフォームされていた。 昔のようにアウトドアーで子座布団のある腰掛で「上賀茂名物やきもち」食べたのが懐かしい。

焼きもちを4個買い先ほど買ったお茶で食べたが、やはり京都の菓子甘味少なく美味しい、「焼きもち」は上賀茂神社「御手洗団子」は下鴨神社が発祥地だと云う人もいる。 「葵祭り」はこの両神社の祭りだ。 この山城の国は神武天皇の天神系氏族、賀茂族の勢力地で神武天皇臣下戸として「賀茂別雷大神」として祀られ、京都で最古の神社といわれている。 また、朝廷から最高位である正一位の神階を受けている神社である。

雨足が少し強くなったので女性は傘を指して本殿・拝殿へ向かった。 上賀茂神社には本殿、権殿以外に大小さまざまな社殿があり、いろいろな神様をお祭りしています。これらの社殿の多くは国宝や重要文化財に指定されている。 白い立派な神馬がいた。拝殿は参拝の人で溢れているので遠くから参拝した。 葵行列が来るまで2時間近くあり、境内を流れる川沿いに歩いた。

画像の境内を流れる明神川沿いは時代劇の男女の密会や隠密間者の連絡、それを追う者との小競り合いシーンでよく出てくるロケ地である。

神社境内を抜けると明神川など、社家町界隈の風情がり、土塀の内側には染屋、和風美術などの工房があるようだ。
どこかで見たような看板が目に付いたが昨年「京のお漬物」でTVでドキュメント放映されたのをおみだした。 京都の名産としてお土産に人気の 「すぐき漬け」や「さんしょしぐれ(ちりめん山椒)」などの京漬物や佃煮を販売している店である。

「すぐき」は上賀茂神社で栽培したのが発祥とされており「柴漬け、「千枚漬け」と合わせて京都の伝統的な三大漬物と呼ばれており、京都の友人から正月用としていただいたが、酸味が苦手な我輩には口に合わない。 家内は「筍の漬けもの」と「京風煮豆」を買ってきて、家で食すと京都ならではの味付けで煮豆は大豆でもう1袋買えばよかったと残念がっていた。 焼きもちの前は臨時バス停で四条河原町行きに乗ったが、バスは千本通りを通ったのだが、街の様相がすっかり変わっており、「千中ミュージック」は面影も無く、西陣、千本釈迦堂はどの辺だったか、雨のバス車窓からは見分けがつかず、仏教大学や立命館大学も移転したのか立派な大学となっていた。 特に吃驚したのはJR二条駅で、近辺には水族館もできている。 「綾小路きみまろ」のセリフ同様、「あれから40年」以上経つと世の流れはこうも変わるもんかと思ったのである。 阪急六甲へ着いたのが17時半ころで雨は上がっていたが歩行計を見るとバスの移動が多かったので歩いていないようだったが7681を示していた。




















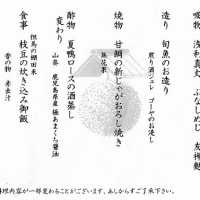
人も多いし、雨も降ったので、さぞお疲れのことでしょう。
バスの移動も結構疲れるものですよね。
私は青梅の御岳山に行ってきました。
登りはケーブルカー、帰りは徒歩だったので5時間弱20kmくらい歩いたでしょうか。
好天でスカイツリーも見えました。
新緑の季節のハイキングは最高です!
20kmの下山お疲れさんでした。
我輩は多少の登りは杖をつきながら登れますが、下りが怖くて高所へは行きません。
山から眺める景色、素晴らしいですね
六甲連山のハイキングは観光地だけあり、要所、要所にエレベーター、ケーブルやロープウエーがあり高齢者に便利になっています。
滑って転んで骨でも折ったら大変です。
膝は大丈夫ですが、太ももがきついです。
下りはやはりきついですね。
人生も同じでしょうか。
引き時、やめ時、老害にならないようにしたいですね。
後期高齢者なると毎年、衰えを感じます。
あれも見てみたい、あれをもう一度食べてみたいと「人生下り坂もまた楽し」ですが、その意欲何時まで続くか