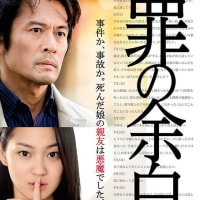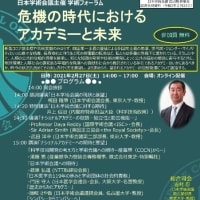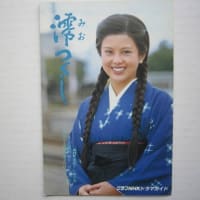今週に入り大学へ戻ったとたんの大問題は、定員の削減問題。
5%削減は具体的数値として、ほとんど全ての国立大学に求められている。しかし、生首を切ることはできない。ということは、今後長期にわたって、教授などの新たな採用ができないということになる。一方で, 中曽根内閣以来の大量博士生産計画で、すでに多くの有能な博士が生まれ、世界に日本国内に30代のポスドクが溢れ、定職につけずにいる。この深刻な現状は国の将来をどうするのか、ということと結びつき出口のないジレンマの中にある。このような時代、「役に立つ」ことを目的とする理系、すなわち工学、農学、薬学、医学などはまさにその目的に突き進めば良い。しかし、私たちのような「知る」ことを目的とする数学や理学はこの矛盾の最中にある。すぐには「役に立たない」しかしそれは百年先への見通しであり、こころの安らぎでもある、「知る」作業をないがしろにする社会は必ず必ず滅びる。生産に役に立たないとして自然をないがしろにして人類はどれほど苦しんだか、そのことに似ている。花を見て、こころを和ませ、自然の中で生気をもらう。美しい絵を見て音楽を聴いて感動をもらう。短時間では「知る」という作業はそのことと同じ位置にいる。しかも、それは未来へとつながるのである。
大学という知の殿堂は、この問題にこれからしばらく苦しめられるであろう。負を如何に正に転ずるか、そのことが問われている。

5%削減は具体的数値として、ほとんど全ての国立大学に求められている。しかし、生首を切ることはできない。ということは、今後長期にわたって、教授などの新たな採用ができないということになる。一方で, 中曽根内閣以来の大量博士生産計画で、すでに多くの有能な博士が生まれ、世界に日本国内に30代のポスドクが溢れ、定職につけずにいる。この深刻な現状は国の将来をどうするのか、ということと結びつき出口のないジレンマの中にある。このような時代、「役に立つ」ことを目的とする理系、すなわち工学、農学、薬学、医学などはまさにその目的に突き進めば良い。しかし、私たちのような「知る」ことを目的とする数学や理学はこの矛盾の最中にある。すぐには「役に立たない」しかしそれは百年先への見通しであり、こころの安らぎでもある、「知る」作業をないがしろにする社会は必ず必ず滅びる。生産に役に立たないとして自然をないがしろにして人類はどれほど苦しんだか、そのことに似ている。花を見て、こころを和ませ、自然の中で生気をもらう。美しい絵を見て音楽を聴いて感動をもらう。短時間では「知る」という作業はそのことと同じ位置にいる。しかも、それは未来へとつながるのである。
大学という知の殿堂は、この問題にこれからしばらく苦しめられるであろう。負を如何に正に転ずるか、そのことが問われている。