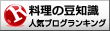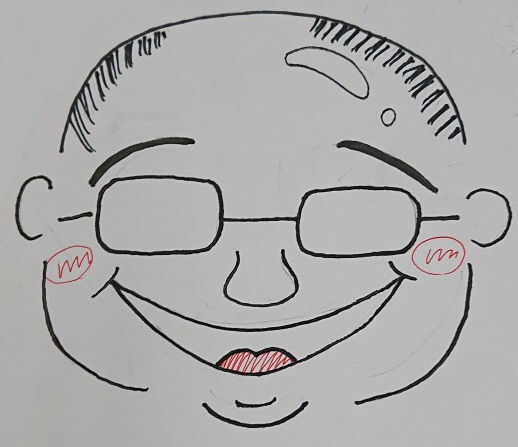【前の答】カレーうどん
月初めに同僚とうどん屋さんに行く機会がありました。
迷うことなく、カレーうどんを選びましたよ。
Q1,カレーうどんが全国に広まってからどれくらいたつでしょうか?
a,約40年 b,約80年 c,約110年
→c,1908年に朝松庵がつくった説を私はとりますので、今年は113年目となります。
明治末から食べられていたのは意外でした。
(1904年に発明したとする本もありますが、三朝庵は1906年創業なので辻褄があいません。)
(三朝庵の前身の三河屋が1874年に創業していますがそこでの記録は残っていませんから、
三朝庵の話の1904年の誤記だと考えます。)
Q2,うどん屋さんでは「カレーうどん」。では、そば屋さんでは?
→カレー南蛮。
こちらはそばにカレーがかかっています。
しかし、南蛮は「ネギ」のことで、入っているかいないかで名前が変わるという説もあります。
Q3,「カレーうどんの町」はどこでしょう?
a,高松市 b,大阪市 c,高鍋町 d,美瑛町
→d,うどん麺とカレールウ、具材を別々に盛った「つけ麺」、
熱々のカレーの下にうどんが入ってい「焼き麺」、
冬限定の「かけ麺」があるようです
【脳トレの答】松風焼
【今日の話】
稲作の伝来は大きな生活の変化をもたらしました。
移住する自然物採集経済から定住する食料生産経済へ変わりました。
と、同時に、住みかの竪穴住居の中にワラを敷いたのではないでしょうか。
何でも有効活用しなければいけない厳しい環境ですから、
保温性に富んだワラを使ったのではないかと推察できます。
そこにですよ、熱々に煮た大豆が落ちたとしたら・・・
ワラについているボク菌が活動して発酵してできた・・・のかもしれませんね。
これが、一番古い説です。
後は聖徳太子説、鑑真説、源義家説、加藤清正説などもありますが、
英雄譚の域を出ないような気がします。
なんとなくできちゃった・・・というのがホントのところでしょうか。
さて、なぜか落語にはあまり出てこないボクですが、
ボク好き志ん生の「替り目」の「今朝食べたボク」という部分には笑えます。
反対に、しんみりとするのが菊池寛の『ボク合戦』。
ネットの青空文庫で読めますから、ぜひご一読下さい。
Q1,江戸時代、ボクはどの季節に食べられていたでしょう?
a,春 b,夏 c,秋 d,冬
Q2,ボク1gあたり、どれぐらいのボク菌がいるでしょう?
a,10~20万 b,10~20億 c,10~20兆 d,10~20京
Q3,血栓を防ぐボクの成分は何でしょうか?
a,ナットウキナーゼ b,ビタミンB2 c,ビタミンK2
Q4,ボクのもったいない食べ方はどれでしょう?
a,熱々のご飯の上にのせて食べる b,酢をかけて食べる c,醤油を入れて食べる
Q5,ボクは何回混ぜると美味しくなるでしょうか?
a,100回 b,250回 c,500回 d,750回
【今日の脳トレ】

月初めに同僚とうどん屋さんに行く機会がありました。
迷うことなく、カレーうどんを選びましたよ。
Q1,カレーうどんが全国に広まってからどれくらいたつでしょうか?
a,約40年 b,約80年 c,約110年
→c,1908年に朝松庵がつくった説を私はとりますので、今年は113年目となります。
明治末から食べられていたのは意外でした。
(1904年に発明したとする本もありますが、三朝庵は1906年創業なので辻褄があいません。)
(三朝庵の前身の三河屋が1874年に創業していますがそこでの記録は残っていませんから、
三朝庵の話の1904年の誤記だと考えます。)
Q2,うどん屋さんでは「カレーうどん」。では、そば屋さんでは?
→カレー南蛮。
こちらはそばにカレーがかかっています。
しかし、南蛮は「ネギ」のことで、入っているかいないかで名前が変わるという説もあります。
Q3,「カレーうどんの町」はどこでしょう?
a,高松市 b,大阪市 c,高鍋町 d,美瑛町
→d,うどん麺とカレールウ、具材を別々に盛った「つけ麺」、
熱々のカレーの下にうどんが入ってい「焼き麺」、
冬限定の「かけ麺」があるようです
【脳トレの答】松風焼
【今日の話】
稲作の伝来は大きな生活の変化をもたらしました。
移住する自然物採集経済から定住する食料生産経済へ変わりました。
と、同時に、住みかの竪穴住居の中にワラを敷いたのではないでしょうか。
何でも有効活用しなければいけない厳しい環境ですから、
保温性に富んだワラを使ったのではないかと推察できます。
そこにですよ、熱々に煮た大豆が落ちたとしたら・・・
ワラについているボク菌が活動して発酵してできた・・・のかもしれませんね。
これが、一番古い説です。
後は聖徳太子説、鑑真説、源義家説、加藤清正説などもありますが、
英雄譚の域を出ないような気がします。
なんとなくできちゃった・・・というのがホントのところでしょうか。
さて、なぜか落語にはあまり出てこないボクですが、
ボク好き志ん生の「替り目」の「今朝食べたボク」という部分には笑えます。
反対に、しんみりとするのが菊池寛の『ボク合戦』。
ネットの青空文庫で読めますから、ぜひご一読下さい。
Q1,江戸時代、ボクはどの季節に食べられていたでしょう?
a,春 b,夏 c,秋 d,冬
Q2,ボク1gあたり、どれぐらいのボク菌がいるでしょう?
a,10~20万 b,10~20億 c,10~20兆 d,10~20京
Q3,血栓を防ぐボクの成分は何でしょうか?
a,ナットウキナーゼ b,ビタミンB2 c,ビタミンK2
Q4,ボクのもったいない食べ方はどれでしょう?
a,熱々のご飯の上にのせて食べる b,酢をかけて食べる c,醤油を入れて食べる
Q5,ボクは何回混ぜると美味しくなるでしょうか?
a,100回 b,250回 c,500回 d,750回
【今日の脳トレ】