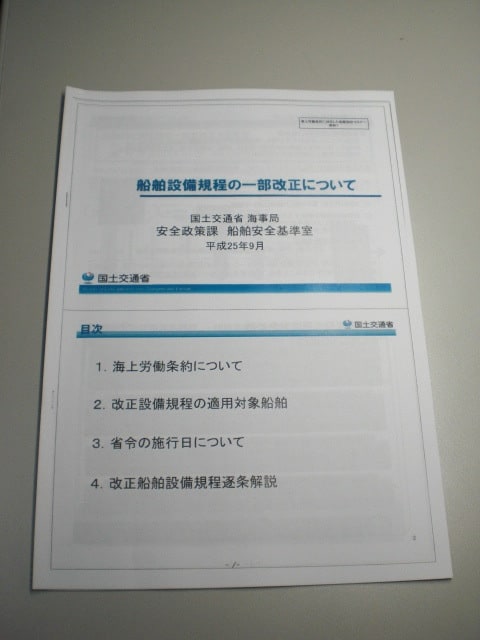昨日に続いて今日は動物取扱業の後編です!
動物取扱業を営むために必要な公的資格というのはありません。 動物取扱業としては、例えば、犬の訓練士や美容室のトリマーなど様々な名称をもつ資格がありますが、これらは公的な資格ではありません。
また、ペットショップやペットホテル、ペットレンタルなどを営業する場合でも、特に資格は要求されません。
もっとも、第一種動物取扱業の登録申請をしても、次のいずれかに欠格事由に該当すると、登録は拒否されます(動物愛護法12条)。
・成年後見人もしくは被保佐人、または破産者で復権していない者
・動物愛護法や同法に基づく処分に違反して罰金以上の刑を課され、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
・登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
・法人が登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその動物取扱業の役員であった者で、その処分のあった日から2年を経過しない者
・業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
・法人であって、その役員の中に以上のいずれかの事由に該当する者があるもの
(動物取扱責任者)
動物取扱業者は、第一種動物取扱業の申請時に、事業所ごとに次の要件を満たす常勤の職員から専属の動物取扱責任者を選任しなければなりません(動物愛護法22条)。
1.営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに半年間以上の実務経験があること
2.営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること
3.公平性及び客観性を持った団体が行う試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること
※ただし、前述した動物愛護法12条の欠格事由に該当すると、動物取扱責任者にはなれません。
★同一の事業所で複数の種別の第一種動物取扱業を営む場合は、種別ごとに登録を受ける必要があります。
(申請窓口)…事業所の所在地が大阪府内の場合は、大阪府環境農林水産部 動物愛護畜産課。 事業所の所在地が大阪市内の場合は、大阪市動物愛護相談室
(申請手数料)…第一種動物取扱業は1業種につき15,000円。但し、同じ事業所で同時に2業種以上申請する場合は、2業種目以降1業種ごとに7,500円。
第二種動物取扱業は届出ですので、手数料は無料です。
(登録の有効期間)…5年。 有効期間が切れる2ヶ月前から、登録の更新申請を行うことができます。
以上、前編と後編の2回にわたって動物取扱業のことを簡単に説明しましたが、参考にしていただければ幸いです。