「集志貫徹」
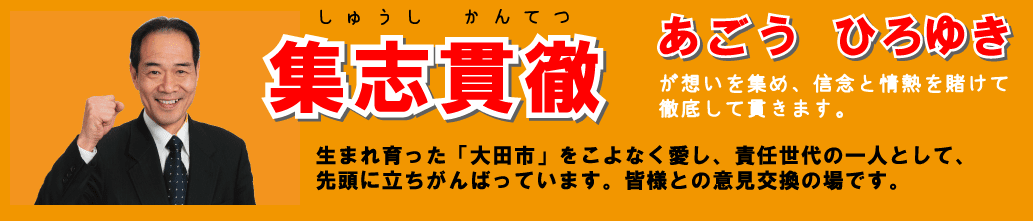
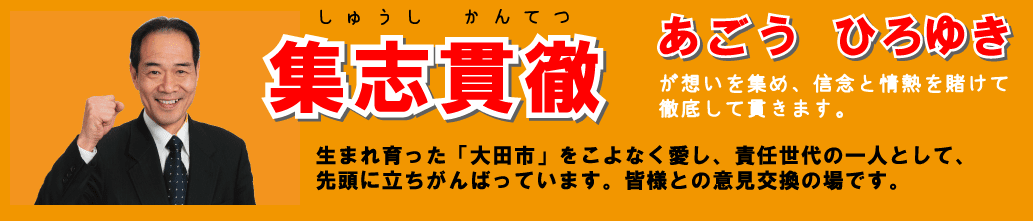

昨日は、午前9時から行財政改革特別委員会が開催されました。
平成22年6月に継続的に設置されたこの委員会。
約2年に渡っての委員会の議論を総括として、「委員長提言としてどうまとめるのか」という集大成がテーマでありました。
委員長の想いは「第2次大田市行財政改革推進大綱」の各項目に対しての意見具申。
委員の要求は全体的な、総論的なまとめしかできないのではないかという意見。
委員からはその理由として、委員会として各項目に対する議論が成熟していないから、というものでした。
では、成熟した議論をもっとするべきではなっかたのか、という反省も残ります。
委員会の2年間というスパンの中で、どう進めていくのかという進行管理が甘かったという反省も残ります。
この2年に渡っての一生懸命取り組んだ事案に対して総論だけの総括でいいのでしょうか。
委員各位が真剣に、議論の成熟を求めて委員会で審議をしたのでしょうか。
なぜ、各項目に及んで意見具申ができるように議論を展開しなかったのでしょうか。
私自身も大いなる反省です。
午後2時からは産業建設委員会が開催されました。
「大田市農業活性化プラン(素案)」に対しての説明がなされました。
感想として、非常に良いプランだと感じました。
「市民みんなが健康で豊かに暮らせるおおだし農業」という大田市農業の将来像を掲げ、
「儲ける」、「環境」、「地産地消」をキーワードに基本方針を掲げています。
具体的な数値目標も盛り込まれています。実現に向けてサポート体制も確立して行かねばなりません。
午後3時からは「石見銀山農政会議」の役員の皆さんと意見交換会が開催されました。
「農商工連携」「鳥獣被害対策」「食農教育」「燃油価格の上昇による代替エネルギー」「乳用牛更新・導入に対する補助制度」
について有意義な意見交換をさせて頂きました。
午後6時30分からは商工会議所にて大田商店会連合会の常任理理会、いわゆる商店会長会議を行ないました。
主な議題は橋南地区の買物弱者支援策についてでした。
「宅配」「移動販売」「買物バス」の3つ視点から商店会でできる取組みを早急に模索するという結論に達しました。
昨日の全員協議会について少しばかり。
(3)「まちづくり体制」について
今日までの協働によるまちづくりの経過は
平成18年度に、ブロック単位に「まちづくりの実践母体」となる「まちづくり委員会」を設置、
平成21年度からは、まちづくりの拠点として公民館をまちづくりセンターとし、
各ブロックに学社連携機能を充実するためにブロック公民館を配置されました。
併せて、まちづくりセンターの活動の支援、まちづくり委員会の事務局を担うため
まちづくり支援センターを配置してきました。
まちづくり元年と謳って体制の再編から、6年が経過し、問題点も浮き彫りになる中で
今後の体制への反映を目的に、まちづくりセンター職員、公民館職員、まちづくりセンター運営委員会委員、
公民館運営委員会委員、まちづくり支援センター職員の合計446人をを対象にアンケート調査を
実施され、結果がまとまりました。
■「まちづくりセンター」は目的を達成しているか
過半数が目的を達成していると評価しているが、約4割は何らかの不満を
かかえ、まちセンごとの力量差、旧公民館からの移行が不十分であったことが伺える。
記述式では、庁内における連携不足の解消や、地域課埠の解決、本格的なまちづくりに
向けての職員体制の充実、地域を巻き込んだ実践が求められている。
また、公民舘とまちづくりセンターの役割分担の整理など、体制の分かりにくさの解消が指摘されている。
■「ブロック公民館」が目的を達成しているか
活動や体制の認知が十分でないと推察される。
「学校支援地域本部事業」「放課後子ども教育推進事業」を実施していない地域では、
回答がしにくかったようである。
記述式では、より専門的な生涯学習事業や、主事の専門性を活かした活動、活動内容の
PR不足など、成果に結び付いていないようである。
また、公民館活動とまちづくりセンター事業との整理、連携が不十分なため、
住民にとっては主体が分かりづらい状況である。
■「まちづくり委員会」が目的を達成しているか
委員会がスタートして6年を経過するが、各地域での活動は十分といえず、
地域での認知度や実績も不足していることが伺われる。
記述式では、ブロック単位でなく各町のまちづくりになっていることと、地域課題に踏
み込んだ活動内容になっていないことが指摘されている。また、委員構成の見直しにより、
実践力のある体制にすべきとの意見や、ブロックよりも各町での実践を望む声が多かった。
■「まちづくり支援センター」が目的を達成しているか
活動の内容や実績は十分でない状況である。
記述では、支援センターは、事業費(主催事業)を持たないことや、地域住民との直接
的な関わりが薄いことなど、活動実態が分かりづらいことをあげられている。
■まちづくり体制全般に係る意見、市の施策等への意見についてく上記と重複しない内容)
市長(市執行部含む)との対話を求める意見が多く寄せられている。
関係者の多くは地域団体を代表する人であり、地域住民の声を直接届けたい気持ちが強いようである。
ブロックの枠組みについては、中学校区との相違や様々なブロック単位の実在など、
地域事情に配慮した枠組みの見直しを求める意見が寄せられている。
という集計です。
アンケートの集計の詳細は拡大してご覧下さい。
このアンケート結果を踏まえながら、まちづくりの方向性を
(1)まちづくりセンターを基本とする自主的なまちづくりの支援を一層進める。
(2)各まちづくりセンターで共通する課題解決に向けたまちづくり事業、公民館事業については、
それぞれまちづくり委員会、公民館がブロックを対象として事業展開を行う。
と打ち出され具体的な事項が示されました。
「平成24年度からの具体的な取り組み」
(1)まちづくり委員会の充実
①まちづくり委員会の構成強化
・各まちづくりセンター及び各町自治会を代表する者の参画
・公民館長及び主事の参画
②所掌事務の追加
・ブロック内のまちづくり委員会事業、まちづくりセンター事業及び公民館事業の事
業調整(重複、類似事業)
※なお、まちづくり委員会の事務局についてはまちづくり支援センターが行うが、必要
に応じて教育委員会からも協議に参加する。
(2)まちづくり支援センターの集約について
①まちづくり支援センターをまちづくり推進課内に設置する。
・支援センター職員を配置後、3年が経過し、それぞれの地域において地域の課題解
決や特性を生かしたまちづく一り事業が自主的に取り組まれはじめている。
・外部評価やアンケート調査結果において、体制が複雑であり、効率化を求められている。
・支援センター職員同士のまちづくりに関する情報の共有、意見交換が随時可能となり、
職員のレベルアップを図り、まちづくり事業への一層の支援を行う。
②各ブロックの担当制とする。(相互が補完する)
(3)身近な行政サービスの変更
①現在支援センターが行っている証明書等(住民票、印鑑証明書等〉の発行は4つのまち
づくりセンター(久手、静間、池田、水上)が引き続き行う。
②戸籍謄抄本の発行については本庁、支所で発行することとする。
よって、新しい体制は
「まちづくり委員会」7ブロック 所管:まちづくり推進課・生涯学習課
を中心として、
「まちづくりセンター」28館(内1分館) 所管:まちづくり推進課
「公民館」7ブロック 所管:生涯学習課
が、連携し進めることの案が示されたところです。
この新体制により、まちづくり支援センターは本庁のまちづくり推進課に集約され
職員数も11名から、各ブロック1名づつの計7名となる案です。
私の考えは、
①まちづくりセンター長の権限と報酬を強化し、常勤とすること。
②センター長に定年制を設け、U・Iターン者を含め、若者の雇用の場とすること。
③支援センター担当職員を減らして、各まちセンと問題ごとに各課担当者の連絡・調整に務めること。
④まちセンと公民館の役割を明確に分担すること。
⑤あくまでも、各町単位で自主性に任せること。
を提案したいと思います。
(4)大田市高齢者福祉計画・第5期介護保険事業計画について
国の介護保険制度が施行され、11年が経過し、平成26年度~26年度の計画で第5期を迎えます。
国・県はもとより大田市においても、高齢化の進行に伴い、医療ニーズの高い高齢者や重度の要介護者
が増加し、介護保険サービスの利用者が激増しています。
この傾向が第5期においてもますます進行することが予想されるため、
第1号保険料の基準額の増額の案が示されました。
第5期における介護サービス給付費を3年間合計で135億円と試算しています。
1年間あたり、平均で45億円の給付費になります。
この内、第1号被保険者(65歳以上の方)は、介護サービスにかかる費用の総額(利用者負担分を除く)
の20%分を負担能力に応じた所得段階別に負担しなければなりません。
すなわち、45億円 × 20% = 9億円 が年間の負担額です。
これを、65歳以上の方、約14000人で負担することになります。
第4期(平成21年度~23年度)は1年間あたり、平均で41億円の給付費
でしたから給付費はかなり増えることになります。
第3期、第4期と据え置かれた月額保険料4400円も大幅に増額の計画が見込まれています。
これは第4期計画書にもあらかじめ今日の状況を予想して見直しが謳われています。
保険料を抑制するために、介護給付費準備基金や県の財政安定化基金の大田市分からの繰入を検討するとのことです。
また、負担能力に応じての保険料負担から、第4期に所得段階を6段階から8段階に見直しましたが、
第5期計画では更に、11段階に細分化し、保険料を多段階にすることによって、第1号被保険者の実態に即した
保険料の負担を計画しています。
現状を考えると、保険料増額も致し方ないかもしれませんが、高齢者にとって負担額の増は深刻な問題です。
保険料抑制の方法をよく検討して頂きたいと思います。
また、介護給付の適正化と介護予防の推進を望むところです。
全員協議会が開催されました。
議題は (1)大田市総合計画後期計画(案)について
(2)平成23年度大田市中長期財政見通しについて
(3)まちづくり体制について
(4)大田市高齢者福祉計画・第5期介護保険事業計画について の4件でした。
全体を通じての感想ですが、とにかくボリュームが多過ぎます。
どの案件も重要な施策で、各議員からは多くの意見が出る事は、 予め考えられたはずです。
しかも、本日は物部神社の節分祭で市長以下一部の議員も参加が決まっています。
いくら昼の休憩時間を利用してと言っても、通常より30分程早めに休憩に入らざるを得ない 状況です。
結局、終了は午後3時20分過ぎ。 時間が多少長くなるのは、一向に構いませんが、議論も中途半端に終了した感が 否めません。
おまけに、その後に大田市立病院医療確保対策特別委員会も控えていました。
細かい事を沢山の質疑として述べられる議員もおられ、計画の全体的な本質の議論には 程遠い状況でもありました。
議論の本質を考えるべきです。
(1)については、10年間に及ぶ「大田市総合計画」 の前期5カ年が平成23年度を持って 終了するため、
後期5カ年の計画を策定するものです。
この後期計画を策定するにあたり、 「市民満足度調査」も実施され、 「満足度」並びに「重要度」を数値的に表し、
相関図に落とし込み、 市民の意見として、後期計画の参考とされています。
私が思うに、主な施策と事業において、重点的な物については何らかの 数値目標を明確に示すべきだと思います。
進行管理をする上で、具体的な成果をわかり易く評価するには、必要な事です。
先日、県庁へ「島根県総合発展計画」を詳細にわたって理解するために勉強に行きました。
この計画には重点的な施策については、最終的な目標を達成するための数値目標が 記載されています。
大田市も総合計画を作成するに当たって、各原課からの素案が提出されるはずです。 各課は 、計画を遂行するにあたり、
年度ごとの実行スケジュールを踏まえた上での提出でしょうから 数値目標も考えていると思われます。
逆に数値目標を持って計画を実行してもらわなければいけない はずです。
そうすると、自ずと数値目標が見えてくるはずだと思います。 総合計画に基づいて、
各下部の実行計画も前期から計画的に実行されている物もあります。
下部の実行計画すら数値目標を定められていない計画も多く存在します。
なぜ、数値目標を示さないのか、理解に苦しみます。
(2)については、未来は決して明るくありません。 要因は自主財源が乏しいの一言です。
よって、交付税に頼らざるを得ませんが、その交付税も合併算定替により平成28年度から 5年間で毎年2億円づつ減少します。
おまけに、 国勢調査の人口減少分が28年度、33年度にそれぞれ3億円見込まれています。
こういう状況下に置かれながら、後期計画の施策を実行していかねばなりません。
財政見通しも厳しい中ですが、必要な事にはそれなりの投資もするべきです。
特に自主財源が見込める「産業振興施策」には 力を入れて頂きたいところです。
長くなりますので、以下は 次の、機会に譲りたいと思います。