「集志貫徹」
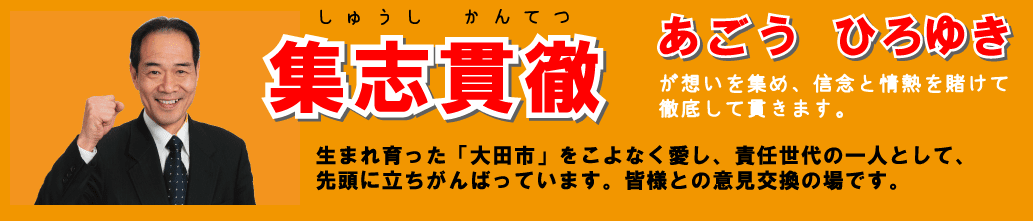
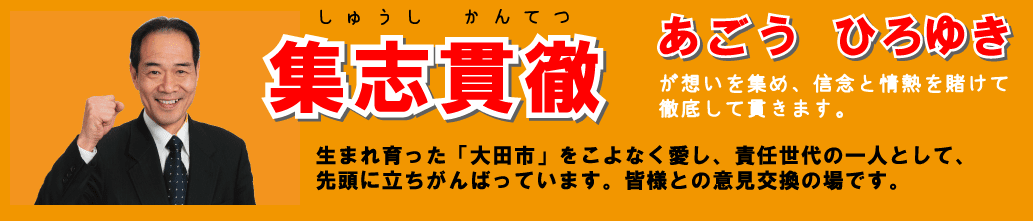

前回に引き続き、「国民健康保険料」についてです。
保険料が引き下がる(一部を除き)ことは前回お示しした通りですが、
これはあくまで25年度と比較した場合です。
24年度と26年度を比較してみると
所得割基準額が100万円の場合
4人家族世帯は、12,700円、2人世帯は、9,500円。
所得割基準額が200万円の場合
4人家族世帯は、18,700円、2人世帯は、15,500円。
所得割基準額が300万円の場合
4人家族世帯は、24,700円、2人世帯は、21,500円。
所得割基準額が400万円の場合
4人家族世帯は、38,800円、2人世帯は、39,200円。
それぞれ増額となっています。
保険料は年々高くなっていると言っても良いでしょう。
保険料が高くなる要因の主なものは
①医療費の高騰
②加入世帯及び加入者の減少
が考えられます。
保険料の高騰を抑えるために、26年度は
6月補正で一般会計から36,300千円、基金会計から155,345千円の繰り入れを行い、
補正後、両者合わせて517,481千円もの巨額な繰り入れを実施しています。(予算時)
これは国民健康保険事業予算の約11%にあたります。
予算規模では25年度に補正後502,744千円、24年度は360,965千円の繰り入れで
保険料の高騰を抑え、事業を維持しています。
とは言っても県内8市では、江津市、浜田市についで3番目に保険料が高い水準です。
また、年収に対する保険料の負担割合ですが
所得割基準額が100万円の場合は約15.5%。
私の手元計算だと、年収が上がるにつれて、負担率が下がる計算になります。
これはいかがなものでしょうか。
所得割基準額が100万円の場合は、年収換算で約234万円くらいでしょうから、
2割軽減基準額(今年度から基準改正で対象が拡大)
の213万円にもギリギリ引っかかりません。
年収約234万円で保険料を年額362,700円支払い、市・県民税も支払い、2人の子育てをしなければならないことになります。
子供に対する医療費は随分負担軽減になりましたが、
転ばぬ先の杖といえ、病院にかかっていない世帯の負担感は大きいものがあるのではないでしょうか。
6月定例の議会が終了しましたね。
補正予算を始め13議案と追加の3議案の全てが原案通り可決されました。
一般会計の補正予算額は146,751千円。
特別会計は国民健康保険事業会計が145,771千円の減額で可決されました。
最近、気になる事項が何点かありましたので、何回かに分けて書きたいと思います。
まず今回は「国民健康保険料」についてです。
市の広報配布に伴い、国保だよりが各世帯へ配布されましたので、
国民健康保険料が確定したのは周知の通りです。

国民健康保険料のの算出については、
「医療分」「後期高齢者支援金分」「介護分」の3区分があり
それぞれ「所得割」「均等割」「平等割」があり決められた算出金額に応じて
負担することになっています。
前年度と比べると、それぞれ所得割で「医療分」が0.2%、「後期高齢者支援金分」が0.1%
安くなりました。(その他については同額)
これによって平均の保険料(年額)が、前年度と比較して
医療分が一世帯当りで、1,823円、一人当りで、1,966円
後期高齢者支援金分で一世帯当りで、1,226円、一人当りで、1,000円
安くなることになります。
これで、皆さんめでたし、めでたし、では終わらないのです。
実は今年度から賦課限度額が「後期高齢者支援金分」で14万円から16万円に
「介護分」で12万円から14万円に引き上げられることとなりました。
文字で書いているだけでは非常に解りにくいので、
モデルケースで説明してみます。
モデルとして取り上げるのは「世帯主と妻、そして子ども2人」の4人家族世帯と
「世帯主と妻」の2人世帯のそれぞれの所得割基準額(年収ではありません)について
年額保険料で比較してみます。(世帯すべてが国民健康保険に加入)
まず、所得割基準額が100万円の場合
4人家族世帯の保険料は、362,700円、2人世帯は、289,700円で、いずれも前年度より3,000円安くなります。
次に、所得割基準額が200万円の場合
4人家族世帯の保険料は、528,700円、2人世帯は、455,700円で、いずれも前年度より6,000円安くなります。
これから先が問題になってきます。
所得割基準額が350万円の場合
4人家族世帯の保険料は、777,700円、2人世帯は、704,700円で、
4人世帯で9,900円、2人世帯で2,600円高くなります。
これは、前述した賦課限度額の引き上げによるものです。
具体的に4人家族世帯で説明すると
「医療分」は所得割の係数が引き下げられたため7,000円値下げになりますが、
「後期高齢者支援金分」は前年度の計算上は147,300円で、限度額14万円だったことがあり、
実際は140,000円でしたが、今年度の143,800円は限度額16万円のあおりを受け、全額負担に。それに伴い3,800円の増。
「介護分」は前年度の計算上は133,100円で、同じように限度額12万円で済んでいたのが、
今年度は前年度と同額にもかかわらず、限度額が14万円になったことで、13,100円の増。
全体で差し引きすると、9,900円の増となってしまいます。
所得割基準額が400万円の場合は
同じように賦課限度額の引き上げに伴い
4人家族世帯の保険料は、38,800円、2人世帯は、14,300円高くなります。
年収が多いから仕方がない、と言われればそこまでですが、年収約550万円ほどの人は値上げの
可能性があります。
この保険料の算出はそれぞれに相違があるため一概には語れませんが、念のため。
6月の定例会が10日から開会となります。
改選後に初めて開かれる定例会とあって注目されるところです。
議員の皆様におかれては、改選時に大田市の将来を鑑み、そのための政策提言や、方向性など
自らの想いを様々な形で表し、市民の皆様の信託を得られた住民全体の代表者であります。
議員、あるいは議会の使命は、大きく二つあると言えます。
一つは、「執行部から提案された具体的な政策を最終的に決定する」ことです。
もちろん、政策形成過程や実施過程に参画し、その時々において重要な決定を行っていますが、
最終的には本会議において提出された議案に対し、質疑等を行こない、議決をもって意思決定することになります。
そのために、不明瞭な点や疑問は本会議において質疑するべきですし、
委員会に付託された専門的な議案については、更に事細かく質問をし、判断することを心がけなければなりません。
二つ目は、執行されている事業について適正になされているかを監視することです。
行財政の運営や事務処理が公平で効率的に、かつ民主的に行われているか住民の立場に立って
時には批判しながら監視することが重要になってきます。
この監視を行うにあたって有効的な方法の一つが一般質問です。
放映されることもあって、市民の皆様からも重大な関心と期待が持たれる議員活動の場だと思います。
前述したように改選時において、行政課題や政策提言を明確に表した訳で、各々の視点はすでにお持ちに
なっているはずですから、市民の意思を反映させるためにも、特に改選後の初議会においては
議員全員が一般質問するべきです。
議会基本条例の前文にも「地域の課題のみならず、様々な市政の課題とこれに対する市民の意思を的確に
反映しうる合議体としての議会づくりを通じ、市民の負託に応えていくことを決意するものである。」と謳っています。
また質問の内容や回答等については、満足のいくものかどうかを市民の皆様がきちんと判断する目を持つことが
必要とされています。
どれだけの議員が、どのような質問するか興味津々ですね。