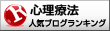とすると戦後日本の原子力ブーム、あるいはその先駆であるテレビ・ブームとは何だったのか、なぜあれほど大きな力をもったのかを問うことは、そのまま戦後世界の光と影、そこでのアメリカの位置を問い返すことになってくるでしょう。
テレビも原子力「平和利用」も、単に情報メディアやエネルギー供給手段であるにとどまらず、何よりもアメリカの世界戦略・対ソ戦略上の最も強力な軍事的・外交的武器であり、またそうであったからこそ、日本でもこれほど目覚ましく発展してくることができたことを知らなければなりません。
アメリカは第2次大戦に勝利し、原爆投下で全世界を威圧する地位を獲得したとはいえ、戦前まではソ連領内にとどまっていた共産圏が、この戦争でかえって東欧へ、朝鮮半島へ、さらには中国へと拡大したことに(ほとんど敗北に匹敵せんばかりの)大きな危機感を抱き、その封じ込めに戦後の一切の政治的・外交的・軍事的な関心を集中せずにはいられませんでした。そのために、狭義の政治・外交・軍事の手段だけにとどまらず、国防総省・(1947年創設の)CIA・(大統領直属機関として設立された)「心理戦局」などを駆使して、「心理戦」(Psychological Strategy)を展開していくのです(なお、「心理戦」のため軍事・政治・経済にまたがる総合的戦略を立案または調整する大統領直属の機関だった「心理戦局」は、やがて1953年9月に、アイゼンハワー大統領の下で廃止され、CIAに統合集中されて、以後CIAが今日知られるように肥大化することになります)。
この戦略のもとで、まずテレビが、共産圏の周辺国に反共イデオロギーを浸透させる「心理戦」の格好のメディアとして動員され、次いで原子力が、「平和利用」の形をとることで、軍事的にも心理的にも、反共自由主義陣営のブロック化の紐帯として動員されることになったのです。
なかんずく日本は、ソ連・北朝鮮に対峙する最前線の反共の砦として、地政学的にも枢要な位置を占める地域の1つでした。占領後もいかに実質的な植民地支配を継続するか、アメリカにとって、対日「心理戦」は喫緊の課題となります。日本の共産化を防ぎ、共産主義の防波堤とするため、アメリカの政治的意図は、日本に天皇制を護持させること、「本土」は経済成長によって貧困から離陸させ、同時に“アジアの工場”として復活させること、一方「沖縄」は軍事基地化して米軍の駐留を確保すること、しかしやがては日本全体に憲法を改定し、(核武装を除く)再軍備をさせ、いざとなれば共産圏諸国と直接戦う役目を日本に負わせられるようにすることでした。わがニッポンのナショナリストたちが、日本国家の真の独立の要件として主張してやまない、天皇制も経済成長も改憲も再軍備も、いずれも実は、アメリカの支配のために予め日本にあてがわれた、植民地主義的な制度以上のものではなかったのです。それらを確立すればするほど、ますます日本はアメリカの属国となっていく仕組みになっています。
とすればなおさら、そのことにニッポン人たちが宥和的な態度をとりつづけ、親米反共的なメンタリティを維持してくれることが必要です。そこで、とくにサンフランシスコ講和条約以降、つまり占領が終結して日本が独立して以降、アメリカは「心理戦」を盛んに行なっていきます。1953年1月30日には「対日心理戦計画」(PSB D-27)を策定、その趣旨は、「日本の知識階級に影響を与え、迅速なる再軍備に好意的な人々を支援し、日本とその他の極東の自由主義諸国との相互理解を促進する心理戦――を速やかに実施することによって中立主義者、共産主義者、反アメリカ感情と戦う」と外交文書には解説されているそうです(有馬哲夫『原発・正力・CIA』pp.63-4)。
すなわちアメリカは、占領終結後も米軍の駐留をつづけて、まず日本を<軍事的再占領>の体制下におくと、その正当化も狙いつつ、テレビをはじめメディアの支配によって<心理的再占領>の体制を打ち立て、さらにその「心理戦」の一環として原子力の「平和利用」を進め、あわせて保守合同による安定的な親米政権の樹立によって<政治的再占領>の体制も確立し、その政権への国民の支持を確保するのにも「心理戦」を存分に用いるという(有馬哲夫『日本テレビとCIA』、pp.273,300)、「心理戦」を中軸にすえた<軍事的再占領><心理的再占領><政治的再占領>の複合的な間接的占領体制=植民地支配体制を構築するのでした。
ところで「心理戦」となれば、本家本元の心理学はどうだったのでしょう。ちょうど講和条約前後の1951年には、ミネソタ大学のウィリアムソンを委員長とする(第2次)アメリカ教育使節団が来日し、その勧告により、アメリカの民主主義を代表するものとして(専らロジャーズ派の)「カウンセリング」が紹介され、大学等に広く導入されます。カウンセリングの専門家の来日はさらに50年代半ばにかけて相次ぎ、ロジャーズも来日、1950年代の日本は「第1次の心理学ブーム」(藤永保『「こころの時代」の不安』、p.7)に沸きかえるのでした。ちょうどテレビ・ブーム、原子力ブームの昂揚と時期を同じくするものです。ちなみにこの頃、50年代後半~60年代初めの少なくとも5年間、研究者としても最も全盛期にあったロジャーズは、CIAとの決して浅からぬ結びつきのあったことが明らかになっています(Demanchick,S.P.&Kirschebaum, H., Carl Rogers and the CIA, in Journal of Humanistic Psychology,48-1,2008)。それでなくとも、そもそも戦後日本における原子力の展開過程と(臨床)心理学の展開過程の間には、興味深い並行関係があるといえるかもしれません。それが見えにくいとすれば、見えにくくする<心理学ムラ>のごときものができているのかもしれません。
戦後日本におけるテレビと原子力は、まさにこうした底深い文脈においてこそ捉えていく必要があるでしょう(同様にして日本の心理学の歴史も、こうした底深い文脈において捉えかえされる必要があるでしょう)。
<つづく>
テレビも原子力「平和利用」も、単に情報メディアやエネルギー供給手段であるにとどまらず、何よりもアメリカの世界戦略・対ソ戦略上の最も強力な軍事的・外交的武器であり、またそうであったからこそ、日本でもこれほど目覚ましく発展してくることができたことを知らなければなりません。
アメリカは第2次大戦に勝利し、原爆投下で全世界を威圧する地位を獲得したとはいえ、戦前まではソ連領内にとどまっていた共産圏が、この戦争でかえって東欧へ、朝鮮半島へ、さらには中国へと拡大したことに(ほとんど敗北に匹敵せんばかりの)大きな危機感を抱き、その封じ込めに戦後の一切の政治的・外交的・軍事的な関心を集中せずにはいられませんでした。そのために、狭義の政治・外交・軍事の手段だけにとどまらず、国防総省・(1947年創設の)CIA・(大統領直属機関として設立された)「心理戦局」などを駆使して、「心理戦」(Psychological Strategy)を展開していくのです(なお、「心理戦」のため軍事・政治・経済にまたがる総合的戦略を立案または調整する大統領直属の機関だった「心理戦局」は、やがて1953年9月に、アイゼンハワー大統領の下で廃止され、CIAに統合集中されて、以後CIAが今日知られるように肥大化することになります)。
この戦略のもとで、まずテレビが、共産圏の周辺国に反共イデオロギーを浸透させる「心理戦」の格好のメディアとして動員され、次いで原子力が、「平和利用」の形をとることで、軍事的にも心理的にも、反共自由主義陣営のブロック化の紐帯として動員されることになったのです。
なかんずく日本は、ソ連・北朝鮮に対峙する最前線の反共の砦として、地政学的にも枢要な位置を占める地域の1つでした。占領後もいかに実質的な植民地支配を継続するか、アメリカにとって、対日「心理戦」は喫緊の課題となります。日本の共産化を防ぎ、共産主義の防波堤とするため、アメリカの政治的意図は、日本に天皇制を護持させること、「本土」は経済成長によって貧困から離陸させ、同時に“アジアの工場”として復活させること、一方「沖縄」は軍事基地化して米軍の駐留を確保すること、しかしやがては日本全体に憲法を改定し、(核武装を除く)再軍備をさせ、いざとなれば共産圏諸国と直接戦う役目を日本に負わせられるようにすることでした。わがニッポンのナショナリストたちが、日本国家の真の独立の要件として主張してやまない、天皇制も経済成長も改憲も再軍備も、いずれも実は、アメリカの支配のために予め日本にあてがわれた、植民地主義的な制度以上のものではなかったのです。それらを確立すればするほど、ますます日本はアメリカの属国となっていく仕組みになっています。
とすればなおさら、そのことにニッポン人たちが宥和的な態度をとりつづけ、親米反共的なメンタリティを維持してくれることが必要です。そこで、とくにサンフランシスコ講和条約以降、つまり占領が終結して日本が独立して以降、アメリカは「心理戦」を盛んに行なっていきます。1953年1月30日には「対日心理戦計画」(PSB D-27)を策定、その趣旨は、「日本の知識階級に影響を与え、迅速なる再軍備に好意的な人々を支援し、日本とその他の極東の自由主義諸国との相互理解を促進する心理戦――を速やかに実施することによって中立主義者、共産主義者、反アメリカ感情と戦う」と外交文書には解説されているそうです(有馬哲夫『原発・正力・CIA』pp.63-4)。
すなわちアメリカは、占領終結後も米軍の駐留をつづけて、まず日本を<軍事的再占領>の体制下におくと、その正当化も狙いつつ、テレビをはじめメディアの支配によって<心理的再占領>の体制を打ち立て、さらにその「心理戦」の一環として原子力の「平和利用」を進め、あわせて保守合同による安定的な親米政権の樹立によって<政治的再占領>の体制も確立し、その政権への国民の支持を確保するのにも「心理戦」を存分に用いるという(有馬哲夫『日本テレビとCIA』、pp.273,300)、「心理戦」を中軸にすえた<軍事的再占領><心理的再占領><政治的再占領>の複合的な間接的占領体制=植民地支配体制を構築するのでした。
ところで「心理戦」となれば、本家本元の心理学はどうだったのでしょう。ちょうど講和条約前後の1951年には、ミネソタ大学のウィリアムソンを委員長とする(第2次)アメリカ教育使節団が来日し、その勧告により、アメリカの民主主義を代表するものとして(専らロジャーズ派の)「カウンセリング」が紹介され、大学等に広く導入されます。カウンセリングの専門家の来日はさらに50年代半ばにかけて相次ぎ、ロジャーズも来日、1950年代の日本は「第1次の心理学ブーム」(藤永保『「こころの時代」の不安』、p.7)に沸きかえるのでした。ちょうどテレビ・ブーム、原子力ブームの昂揚と時期を同じくするものです。ちなみにこの頃、50年代後半~60年代初めの少なくとも5年間、研究者としても最も全盛期にあったロジャーズは、CIAとの決して浅からぬ結びつきのあったことが明らかになっています(Demanchick,S.P.&Kirschebaum, H., Carl Rogers and the CIA, in Journal of Humanistic Psychology,48-1,2008)。それでなくとも、そもそも戦後日本における原子力の展開過程と(臨床)心理学の展開過程の間には、興味深い並行関係があるといえるかもしれません。それが見えにくいとすれば、見えにくくする<心理学ムラ>のごときものができているのかもしれません。
戦後日本におけるテレビと原子力は、まさにこうした底深い文脈においてこそ捉えていく必要があるでしょう(同様にして日本の心理学の歴史も、こうした底深い文脈において捉えかえされる必要があるでしょう)。
<つづく>