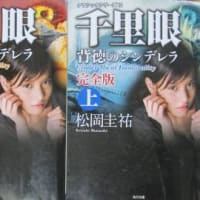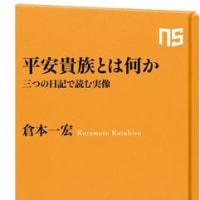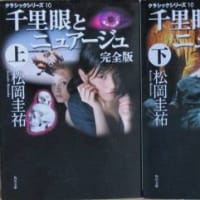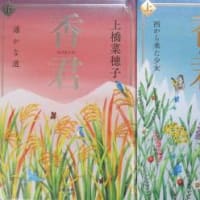ブログを書き始める以前の愛読作家の一人の新刊広告を読み、十有余年ぶりに本書を手に取った。漢を建国する劉邦の功臣となった張良という存在をかつては意識していなかった。劉邦と諸葛孔明との関係に関心があったからだろう。今、初めて張良という存在を知る機会となった。本書は、劉邦との関わりを描きつつ、張良の生涯を描いた伝記風中国史小説と言える。
本書は、著者はじめてのウエブ連載小説として「読売新聞オンライン」(2024.1.1~2024.10.26)に連載された後、2024年12月に単行本が刊行された。
読了後に少しネット検索していて、著者がこのウエブ連載小説を始める時点で、インタビューに応じている記事に出会えた。そこに記された著者の抱負をまず要約してご紹介しておこう。
この小説の連載にあたり「『美しい軍師』を書きたい」という願望があったと著者は語る。そして、「張良は基本的に軍を指揮しないし、政治にもたずさわらない。『王佐の才』すなわち君主の補佐という意味で、最も軍師らしい軍師だ」と位置づけている。その張良が活躍する「原動力はまさに『恨み』です」と語る。それが張良の信念に昇華されて行ったのだ。「本当に目的に向かって意志を貫くと、生きる原動力になる」という転換である。
この小説、張良の人生ステージに沿ってストーリーが進展する。大きくとらえると次のようにとらえられると思う。
A 楚の国・淮陽への遊学と帰国。暗殺の対象になる
韓の国の宰相・張平の晩年の子として生まれた。父の死のときには幼小の故に位を継げなかった。淮陽への遊学の折、倉海君の知遇を得て、その親交の絆が生涯の支えとなる。その時、王佐の才と剣難の相を観相者に指摘される。
B 韓の消滅。その因となる秦の始皇帝への復讐:博浪沙での襲撃
『韓非子』を著した公子非は秦王政の招請で秦に赴くが、後に殺される。秦軍の攻撃で韓が滅亡。張良は秦王政を殺すという目的で生きる決意をする。国土を平定した始皇帝(政)を張良は苦節の末、博浪沙で襲撃するが失敗。この経緯が張良の人生の最初の山場となる。
C 潜伏期。黄石公との出会い
倉海君の助力を得て張良は潜伏する。このとき、黄石公との不思議な出会いを体験する。この時、太公望の兵法書を授かる。張良が兵法を修得する契機となる。
後で調べてみると、この黄石公との出会いが能の演目にも取り入れられていることを知った。張良の人生にとって、将来軍師として劉邦を佐(たす)けるための力量を培う時期となったのだろう。張良の許に、少数だが剣士、方士など精鋭の人々が一団を形成する。張良の情報収集力が培われる。
D 始皇帝の死と劉邦との出会い
始皇帝が巡遊中に死ぬ。秦帝国に大乱の兆しが生じる。群雄割拠の到来である。大沢郷で陳勝の起こした叛乱が嚆矢となる。陳勝は張楚を建国する。張良は情報収集に努め、情勢分析に注力する。張良は再び韓の国を建てるという志望を果たすために行動し始める。
張良は方士南生の観たてに従い、沛公(劉邦)に謁見する。この出会いが、その後の張良の生き方を決定づけていくことになる。人が人にほれるという共鳴が起こったのだろう。
著者は記す。「この出会いは、歴史的な邂逅といってよく、端的にいえば、劉邦は張良を拾ったことにより、天下を拾ったのである」(p246)と。
劉邦は、張良という力量があり軍師となれる人物、国佐の人物に巡り合ったのだ。
張良は、韓を建国するうえで劉邦が支持力・推進力になってくれると感じたのだろう。
E 韓国再建
張良は横陽君すなわち韓の公子成と再会する。張良は公子成と共に、楚の国の武信公(項梁)に謁見する。項梁が楚王の代人として、横陽君を韓王と認め、張良を申徒(司徒、首相)に任じた。これが再建の始まりとなる。やがて長社が韓国再建の基地となる。
F 劉邦との再会。劉邦と共に歩む
病に倒れた張良が養生している陽城に劉邦軍が進軍してくることで、劉邦と張良が再会する。この再会で、劉邦は張良を傍に置き、相談相手とし、張良に軍師の役割を担わせていく。
G 鴻門の会
項羽軍は函谷関を破り、西進し鴻門に本営を置く。劉邦軍が項羽軍に勝てるはずがない。そこで窮余の一策が講じられる。その結果、劉邦が項羽に謁見する形で両者の衝突が回避される。それが成功した背景には、張良と項伯との強い絆があった。
鴻門の戦い回避の成功が、張良の人生で大きな岐路になったのではないかと思う。
H 劉邦が漢王になる。張良は韓に帰国。項羽が韓を滅ぼす
劉邦が漢王になった時点で、張良は韓国に戻る。帰路、張良は己につき従ってくれた部隊を解散させ、故郷に戻す。韓国に戻ると、韓王成は、項王(項羽)に実質上拉致されていた。項王は後に韓王を殺害し、韓を滅ぼす。
I 張良は漢王劉邦の王佐となり、項羽への復讐を目指す
改めて張良は漢王劉邦のもとに行く。劉邦より成信侯と名づけられ、王佐として劉邦への助言を行い、軍師としての働きを担う。韓王成を殺し、韓国が滅ぼされた恨みを、項羽を倒すという目的にして張良は再び前進する。彭城の戦いから始まって行く。
J 漢王朝の確立。張良は留侯に封じられる。
劉邦が漢王朝を確立し、漢皇帝となる。張良は劉邦が与えようとした巨大な褒賞を辞退し、留の地に封じられれば充分とだと述べる。留県を領地とした張良は留侯と称される。
張良は恵帝の六年に亡くなった。本書の最後は、張良の言葉で締めくくられる。
私利私欲を持たず、己の信念と目的のもとに突き進んだ張良のスタンスが「美しい」。張良が親交を持ち、絆を強くして行った人々との真摯な関わり方、張良の許に集まった人々を大事に思い共に行動する姿が「美しい」。
本作を読み終えて、劉邦の様々な戦いがストーリーに織り込まれていくのに、諸葛孔明が一度も顔を出さないことに気づいた。なぜだろうかと気になった。
読後にたまたま入手した上記のインタビュー記事で著者は次のように語っている。
「諸葛孔明は文官としての能力が高いとおもいますが、兵の扱いもうまくなって文武両道になっていきます。軍とともに行動して、戦場にいながら裁判や中央行政などなんでもやっており、常に仕事をしているオールマイティーな人物です」
この箇所を読み、思った。戦争と闘争(戦い)の次元の違いだろうかと。張良は大きな戦争の方向性という観点で軍略について劉邦を助ける軍師となった。諸葛孔明は、主に、既に動き出した戦争の実際の戦場における戦闘次元で、軍師として策略をたて助言した。多分、その違いではないか。だから、諸葛孔明の活躍は直接にはこのストーリーの流れの中では、戦争に関する記述の水面下で、諸葛孔明が重層的に活躍しているということではないかと。
最後に、インタビュー記事の末尾の著者の語りを引用しておきたい。
それは、本書で描かれた張良の生きざまに反映していると思うので・・・・・。
「本当に真剣な人は、自分のやりたいことがみえてくるはずで、みえていないというのは真剣さが足りていない。仕事でも学問でも一生懸命やるということの大切さを感じてほしいとおもいます」
これは耳の痛い警句でもある。
ご一読ありがとうございます。
補遺
自身初のウェブ連載小説で描く「美しい軍師」の生涯~「張良」宮城谷昌光さんインタビュー :「讀賣新聞オンライン」
張良 :ウィキペディア
張良とはどんな人物?簡単に説明【完全版まとめ】 :「歴史上の人物.com」
張良 :「コトバンク」
演目事典:張良 :「the 能.com」
曲目解説 張良 :「銕仙会~能と狂言~」
黄石公 :ウィキペディア
始皇帝 :ウィキペディア
劉邦 :ウィキペディア
項羽 :ウィキペディア
ネットに情報を掲載された皆様に感謝!
(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません
その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。
その点、ご寛恕ください。)
本書は、著者はじめてのウエブ連載小説として「読売新聞オンライン」(2024.1.1~2024.10.26)に連載された後、2024年12月に単行本が刊行された。
読了後に少しネット検索していて、著者がこのウエブ連載小説を始める時点で、インタビューに応じている記事に出会えた。そこに記された著者の抱負をまず要約してご紹介しておこう。
この小説の連載にあたり「『美しい軍師』を書きたい」という願望があったと著者は語る。そして、「張良は基本的に軍を指揮しないし、政治にもたずさわらない。『王佐の才』すなわち君主の補佐という意味で、最も軍師らしい軍師だ」と位置づけている。その張良が活躍する「原動力はまさに『恨み』です」と語る。それが張良の信念に昇華されて行ったのだ。「本当に目的に向かって意志を貫くと、生きる原動力になる」という転換である。
この小説、張良の人生ステージに沿ってストーリーが進展する。大きくとらえると次のようにとらえられると思う。
A 楚の国・淮陽への遊学と帰国。暗殺の対象になる
韓の国の宰相・張平の晩年の子として生まれた。父の死のときには幼小の故に位を継げなかった。淮陽への遊学の折、倉海君の知遇を得て、その親交の絆が生涯の支えとなる。その時、王佐の才と剣難の相を観相者に指摘される。
B 韓の消滅。その因となる秦の始皇帝への復讐:博浪沙での襲撃
『韓非子』を著した公子非は秦王政の招請で秦に赴くが、後に殺される。秦軍の攻撃で韓が滅亡。張良は秦王政を殺すという目的で生きる決意をする。国土を平定した始皇帝(政)を張良は苦節の末、博浪沙で襲撃するが失敗。この経緯が張良の人生の最初の山場となる。
C 潜伏期。黄石公との出会い
倉海君の助力を得て張良は潜伏する。このとき、黄石公との不思議な出会いを体験する。この時、太公望の兵法書を授かる。張良が兵法を修得する契機となる。
後で調べてみると、この黄石公との出会いが能の演目にも取り入れられていることを知った。張良の人生にとって、将来軍師として劉邦を佐(たす)けるための力量を培う時期となったのだろう。張良の許に、少数だが剣士、方士など精鋭の人々が一団を形成する。張良の情報収集力が培われる。
D 始皇帝の死と劉邦との出会い
始皇帝が巡遊中に死ぬ。秦帝国に大乱の兆しが生じる。群雄割拠の到来である。大沢郷で陳勝の起こした叛乱が嚆矢となる。陳勝は張楚を建国する。張良は情報収集に努め、情勢分析に注力する。張良は再び韓の国を建てるという志望を果たすために行動し始める。
張良は方士南生の観たてに従い、沛公(劉邦)に謁見する。この出会いが、その後の張良の生き方を決定づけていくことになる。人が人にほれるという共鳴が起こったのだろう。
著者は記す。「この出会いは、歴史的な邂逅といってよく、端的にいえば、劉邦は張良を拾ったことにより、天下を拾ったのである」(p246)と。
劉邦は、張良という力量があり軍師となれる人物、国佐の人物に巡り合ったのだ。
張良は、韓を建国するうえで劉邦が支持力・推進力になってくれると感じたのだろう。
E 韓国再建
張良は横陽君すなわち韓の公子成と再会する。張良は公子成と共に、楚の国の武信公(項梁)に謁見する。項梁が楚王の代人として、横陽君を韓王と認め、張良を申徒(司徒、首相)に任じた。これが再建の始まりとなる。やがて長社が韓国再建の基地となる。
F 劉邦との再会。劉邦と共に歩む
病に倒れた張良が養生している陽城に劉邦軍が進軍してくることで、劉邦と張良が再会する。この再会で、劉邦は張良を傍に置き、相談相手とし、張良に軍師の役割を担わせていく。
G 鴻門の会
項羽軍は函谷関を破り、西進し鴻門に本営を置く。劉邦軍が項羽軍に勝てるはずがない。そこで窮余の一策が講じられる。その結果、劉邦が項羽に謁見する形で両者の衝突が回避される。それが成功した背景には、張良と項伯との強い絆があった。
鴻門の戦い回避の成功が、張良の人生で大きな岐路になったのではないかと思う。
H 劉邦が漢王になる。張良は韓に帰国。項羽が韓を滅ぼす
劉邦が漢王になった時点で、張良は韓国に戻る。帰路、張良は己につき従ってくれた部隊を解散させ、故郷に戻す。韓国に戻ると、韓王成は、項王(項羽)に実質上拉致されていた。項王は後に韓王を殺害し、韓を滅ぼす。
I 張良は漢王劉邦の王佐となり、項羽への復讐を目指す
改めて張良は漢王劉邦のもとに行く。劉邦より成信侯と名づけられ、王佐として劉邦への助言を行い、軍師としての働きを担う。韓王成を殺し、韓国が滅ぼされた恨みを、項羽を倒すという目的にして張良は再び前進する。彭城の戦いから始まって行く。
J 漢王朝の確立。張良は留侯に封じられる。
劉邦が漢王朝を確立し、漢皇帝となる。張良は劉邦が与えようとした巨大な褒賞を辞退し、留の地に封じられれば充分とだと述べる。留県を領地とした張良は留侯と称される。
張良は恵帝の六年に亡くなった。本書の最後は、張良の言葉で締めくくられる。
私利私欲を持たず、己の信念と目的のもとに突き進んだ張良のスタンスが「美しい」。張良が親交を持ち、絆を強くして行った人々との真摯な関わり方、張良の許に集まった人々を大事に思い共に行動する姿が「美しい」。
本作を読み終えて、劉邦の様々な戦いがストーリーに織り込まれていくのに、諸葛孔明が一度も顔を出さないことに気づいた。なぜだろうかと気になった。
読後にたまたま入手した上記のインタビュー記事で著者は次のように語っている。
「諸葛孔明は文官としての能力が高いとおもいますが、兵の扱いもうまくなって文武両道になっていきます。軍とともに行動して、戦場にいながら裁判や中央行政などなんでもやっており、常に仕事をしているオールマイティーな人物です」
この箇所を読み、思った。戦争と闘争(戦い)の次元の違いだろうかと。張良は大きな戦争の方向性という観点で軍略について劉邦を助ける軍師となった。諸葛孔明は、主に、既に動き出した戦争の実際の戦場における戦闘次元で、軍師として策略をたて助言した。多分、その違いではないか。だから、諸葛孔明の活躍は直接にはこのストーリーの流れの中では、戦争に関する記述の水面下で、諸葛孔明が重層的に活躍しているということではないかと。
最後に、インタビュー記事の末尾の著者の語りを引用しておきたい。
それは、本書で描かれた張良の生きざまに反映していると思うので・・・・・。
「本当に真剣な人は、自分のやりたいことがみえてくるはずで、みえていないというのは真剣さが足りていない。仕事でも学問でも一生懸命やるということの大切さを感じてほしいとおもいます」
これは耳の痛い警句でもある。
ご一読ありがとうございます。
補遺
自身初のウェブ連載小説で描く「美しい軍師」の生涯~「張良」宮城谷昌光さんインタビュー :「讀賣新聞オンライン」
張良 :ウィキペディア
張良とはどんな人物?簡単に説明【完全版まとめ】 :「歴史上の人物.com」
張良 :「コトバンク」
演目事典:張良 :「the 能.com」
曲目解説 張良 :「銕仙会~能と狂言~」
黄石公 :ウィキペディア
始皇帝 :ウィキペディア
劉邦 :ウィキペディア
項羽 :ウィキペディア
ネットに情報を掲載された皆様に感謝!
(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません
その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。
その点、ご寛恕ください。)