http://news.goo.ne.jp/article/sankei/politics/snk20150116069.htmlより転載
東大、軍事研究を解禁 公開前提に一定の歯止め
東京大学(浜田純一総長)が禁じてきた軍事研究を解禁したことが15日、分かった。東大関係者が明らかにした。安倍晋三政権が大学の軍事研究の有効活用を目指す国家安全保障戦略を閣議決定していることを踏まえ、政府から毎年800億円規模の交付金を得ている東大が方針転換した。軍事研究を禁じている他大学への運営方針にも影響を与えそうだ。
東大は昭和34年、42年の評議会で「軍事研究はもちろん、軍事研究として疑われるものも行わない」方針を確認し、全学部で軍事研究を禁じた。さらに東大と東大職員組合が44年、軍事研究と軍からの援助禁止で合意するなど軍事忌避の体質が続いてきた。
ところが、昨年12月に大学院の情報理工学系研究科のガイドラインを改訂し、「軍事・平和利用の両義性を深く意識し、研究を進める」と明記。軍民両用(デュアルユース)技術研究を容認した。ただ、「成果が非公開となる機密性の高い軍事研究は行わない」と歯止めもかけた。以前は「一切の例外なく、軍事研究を禁止する」としていた。
東大などによると、評議会は審議機関で、軍事研究の是非など運営方針の決定権は総長にある。総長には審議結果に従う法的な義務はない。それにもかかわらず、東大は評議会での一部の総長らの軍事忌避に関する発言をよりどころに禁止方針を継承してきた。
東大は解禁理由について「デュアルユース研究は各国の大学で行われている。研究成果の公開性を担保する国際的な動向に沿った形で、ガイドライン改訂を行った」と強調している。
東大の軍事研究をめぐっては、昨年4月、複数の教授らが平成17年以降、米空軍傘下の団体から研究費名目などで現金を受け取っていたことが判明し、学内の独自ルールに手足を縛られてきた研究者が反旗を翻した。5月には防衛省が、不具合が起きた航空自衛隊輸送機の原因究明のため、大学院教授に調査協力を要請したが、拒否された。










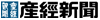


 http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-237392-storytopic-11.htmlより転載
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-237392-storytopic-11.htmlより転載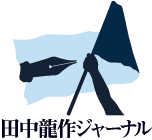 http://tanakaryusaku.jp/2015/01/00010572より転載
http://tanakaryusaku.jp/2015/01/00010572より転載

