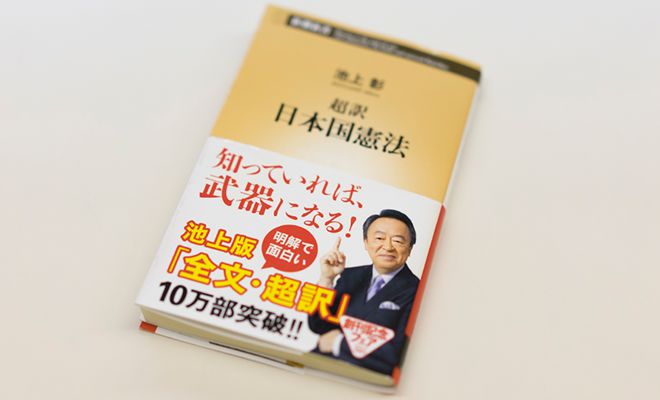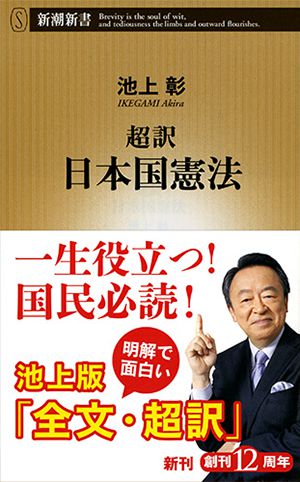dot. https://dot.asahi.com/dot/2017042300028.htmlより転載
元SEALDs諏訪原健「僕も昔、保守ともリベラルともとれる答えを用意していた」
安全保障関連法反対のデモ活動を行った学生団体「SEALDs(シールズ)」の中核メンバーだった諏訪原健氏は、かつて「政治になんて関わりたくない」と考えていたという。だが、そんな意識が変わったのは――。
***
「デモをやっている人なんて一部の特別な人でしょ」とか思ってしまう人の気持ちって、実はとてもよくわかる。
僕が路上で声を上げるようになったのは、ここ3年くらいの話だ。
それまでは、そもそもデモなんて見たこともなかったし、自分が国会前に毎週足を運ぶようになるなんて思いもしなかった。バイトばかりやっていて、あんまりアクティブに社会と関わろうとする学生ではなかった。できるだけ家にこもっていたい、布団と仲良くしていたい。今でもそんな人間だ。
自分の思いを表明したり、行動につなげたりするのってすごくエネルギーを使うことだと思う。僕みたいな腰の重い人間にはあんまり向かない。
実際、動かなきゃと思っても、気付いたら何もしないままってことが多い。
3.11(東日本大震災)をきっかけにして、社会的な活動に参加するようになった人って多いと思うけど、その時ですら自分は何もしなかった。
3.11の瞬間は鹿児島にいたから、いまいちリアリティを持てないままだったのもあるし、そもそも状況をきちんと見つめようとする気持ちすらなかったのだと思う。
復興支援のボランティア活動をしている友人を見ても、「意識高いなー、えらいなー」と思うだけで、結局他人事だった。「原発についてどう思う?」って聞かれても、「リスクは大きいけど、電源交付金ないと回らないのが地域の実情だよねー」なんて言って、賛成とも反対とも言わずに、結局ごまかした。
支持政党を聞かれた時には、安倍自民党ではないけど、民主党と言うのは気が引けるので「かつての自民党・宏池会かなー」とか答えた。
保守ともリベラルともとれるような答えを用意しただけだった。今となっては、どうしようもなく恥ずかしい。
少しだけ立ち止まって、ちゃんと考えようとすればわかるはずなのに。
気付こうとすれば、見えてくる世界は全然違うはずなのに。
それなのに僕は面倒臭さがって、ずーっと何もしなかった。適当なこと言って、ずーっとやり過ごしてきた。それが何も悪いことだとも思っていなかった。
でも、自分が何となくやり過ごしている裏で、実際に誰かが苦しんでいたんだと思う。直接の知り合いではないかもしれないけど、血の通った、感情を持った、僕らと何ら変わらない人間が。
しかも僕たちが投票の時、もう少しだけ頭を使っていたら、そんな目に合わなかったかもしれないのに。今、目の前で流れているニュースに反応して声を上げたら、状況は少しでも変わるのかもしれないのに。
そんなふうに、想像力をはたらかせてみると、自分も誰かの苦しみに加担しているのかと思えてきて、どうしようもなく恐ろしい。
本当にごめんなさいって気持ちになる。
「原発なんて簡単になくならないでしょ?」
「米軍基地がなくなったら防衛はどうするの?」
「共謀罪は一般人には関係ないでしょ?」
「好きで大学行くのだから、奨学金を借りるなんて当たり前でしょ?」
「性暴力を受けても、仕方ないような格好をしてたんじゃないの?」
そういう言葉を投げかけるのって簡単だ。でも、それって力の強い者が、弱く小さき者を納得させるのに都合のいい言い訳なんじゃないですか?
為政者が国民の目を背けさせるために使っている常套句なんじゃないですか?
それをあたかも自分の意見かのように振りかざして、自分は大丈夫だと安心して、それで本当にいいんでしょうか。
適当なこと言って、考えることをやめて、できるだけ雑音のない世界を生きる方が、表面的にはずっとハッピーに決まっている。
毎日みんなそれぞれ忙しい。気付いたらまた次の1日が始まってみたいな生活していたら、政治なんて考えられなくても仕方ない。
だけどそういうこと繰り返している間に、この社会は取り返しのつかないことになるんじゃないかと思えてしょうがない。
「憲法守れ」とかそういうこと語ることが、「左翼」とか「反日」とか言われる社会になっている。
権力者が、憲法の枠の中で政治やるのは当然のことで、思想がどうとか支持政党がどうとか、それ以前の問題だ。
それなのに、極端に偏っているかのように非難される。
これまで「当たり前」だと思っていたことが、どんどん当たり前ではなくなっている。ものを言うことがどんどん難しくなっている。
こんな調子だと、やがて政治について語ること自体がタブーになるかもしれない。気付いたら政治は、人々のものではなくなるかもしれない。
民主主義(笑)――みたいな空気に、社会が包まれているかもしれない。
公のために、誰かが痛い目をみるのが当然の世の中になるかもしれない。
僕はそんなふうにはなってほしくない。少し前まで、わかったふりして、ちゃんと政治と向き合ってこなかったから、偉そうなこと言えるような人間じゃないのは自分でもよくわかっている。
アレコレ発言しても家に帰ってから「あんなこと言わなきゃよかった――」って後悔することも多い。
でもそんな人間だからこそ、政治について意見するくらいのことは、別に特別な人間じゃなくてもできるって思うわけです。
考え直すことは、いつからでも始められる。とりあえず今、思っていることを言うことから始めたらいいし、社会も、自分も変わるから、言っていることが後から変わってもいい。それくらいの気持ちで、みんな思っていることを本音で語り合えたら、その瞬間からちょっとこの社会は良くなるんじゃないかな――と僕は思うのです。(諏訪原健)