2月25日、岡山市北区の河本公会堂で、「私たちの年金は大丈夫か?安心できる年金制度を考える集い」(日本共産党牧石支部主催)をひらきました。
 最初に参加者で「たきび」を唄った後、講師の東都支男さん(年金者組合県本部委員長・年金裁判岡山原告団長)から次のようなお話(概要)がありました。
最初に参加者で「たきび」を唄った後、講師の東都支男さん(年金者組合県本部委員長・年金裁判岡山原告団長)から次のようなお話(概要)がありました。
年金は減らされ続け、後の世代はとことん減らされる
以前は物価に応じて年金額はスライドしていました。2004年、年金財政の均衡を保つ(積立金の保有)ためとして「マクロ経済スライド」が導入され、平均余命の伸長や被保険者の減少によって年金額を調整する(下げる)ことが決められました。
2012年には、税と社会保障の一体改革と称して社会保障制度改革推進法ができました。その特徴は、社会保障は家族や国民相互の助け合いで行い(公助を減らし)、給付の主要財源を消費税とし(貧乏人から集めたお金を財源とする)、保険料を払ったものだけが保障を受けるというものでした。
翌2013年にはいわゆるプログラム法ができ、受益と負担の均衡をはかり(憲法に基づく社会保障制度を解体していく)、健康で年齢等に関係なく働くことができる環境を整備する(働けなくなった時については書かれていない。死んでくれということか?)とし、その推進は、関係閣僚による推進本部と有識者(御用学者)による推進会議がおこないます。
さらに、2015年に安倍内閣は「経済財政運営と改革の基本方針」を閣議決定しました。これは、社会保障費の自然増(年8千億~1兆円)を5千億円程度に抑え、公的年金制度を壊して私的年金へ市場を開放することになります。
昨年末の国会では、強行採決で、マクロ経済スライド未実施分の繰り越し減額、物価スライドに賃金変動率を加味した調整(減額)が決められました。なお歓迎できることもあり、受給資格期間が25年から10年に短縮されました。ただし、10年加入の年金は月額1250円とわずかな額です。
高齢者の実態は、基礎年金のみの受給者が767万人で、その平均月額は約5万円です。厚生年金受給者の平均月額は、男性が16万5千円で女性が10万2千円、月額10万円以下の受給者は393万人です。そして無年金者は約100万人と推定されています。
いま岡山地裁で年金裁判をやっています。マクロ経済スライドで年金が減らされるのは、僕らが生きとる間は大したことはないですが、後の人はとことん減らされます。このマクロ経済スライドは憲法違反だとして203人の原告が国家賠償を求めています。2月13日に第1回口頭弁論があり、100の傍聴席を満席にしました。全国では42都道府県の人が提訴していて、あと2県で提訴を準備しています。5000人を超える原告が国と闘うことになります。主な争点は、憲法25条の生存権、29条の財産権と13条の幸福追求権です。国は、減額は裁量権の範囲内だと主張していますが、国際社会権規約では社会保障の条件の後退は禁止されています。
財源は国内で余っているお金(大企業の内部留保など)に求め、社会保障を充実させよう
年金者組合は、年金改革の5つの提案をしています。
1)雇用は正規が当たり前の社会へ戻すことによって保険料収入が安定する。
2)現役労働者の賃金を引き上げる(1万円アップすれば保険料収入が年間8千億円増)。
3)保険料の上限を引き上げる(現行では31等級の62万円が上限。これを健康保険並みの47等級の121万円に引き上げると年間約8千億円の収入増)。
4)年金積立金の活用は国債の購入に限り、危険な株式投資はしない。
5)国民全員の最低保障年金制度を創設する(共産党の政策は月5万円を最低保障年金額としている)。
財源問題としては、政府のお金は足りませんが、国内全体では大企業の内部留保などでお金は余っているので、そこに財源を求ることで解決できます。税は応能負担・生活費非課税を原則として累進性を強化させましょう。財政支出は、大企業優遇や軍事費優先ではなく、社会保障を優先させましょう。
その後、参加者の意見交換がおこなわれ、「同一労働同一賃金を実行すれば社会保障費の負担は軽減される」、「弱者は団結する必要がある」、「戦争がなくなり軍事支出がなくなれば、人類は豊かになる」、「国立大学が独立行政法人になって国の予算が年々減らされている」などの発言がありました。
最後に、日本共産党の年金政策として、最低保障年金やその財源の確保などを紹介し、社会をよくするために力を合わせようと呼びかけました(「2016年参議院議員選挙/各分野の政策-10、年金」参照)。また、共謀罪に反対する署名も呼びかけました。
 最初に参加者で「たきび」を唄った後、講師の東都支男さん(年金者組合県本部委員長・年金裁判岡山原告団長)から次のようなお話(概要)がありました。
最初に参加者で「たきび」を唄った後、講師の東都支男さん(年金者組合県本部委員長・年金裁判岡山原告団長)から次のようなお話(概要)がありました。年金は減らされ続け、後の世代はとことん減らされる
以前は物価に応じて年金額はスライドしていました。2004年、年金財政の均衡を保つ(積立金の保有)ためとして「マクロ経済スライド」が導入され、平均余命の伸長や被保険者の減少によって年金額を調整する(下げる)ことが決められました。
2012年には、税と社会保障の一体改革と称して社会保障制度改革推進法ができました。その特徴は、社会保障は家族や国民相互の助け合いで行い(公助を減らし)、給付の主要財源を消費税とし(貧乏人から集めたお金を財源とする)、保険料を払ったものだけが保障を受けるというものでした。
翌2013年にはいわゆるプログラム法ができ、受益と負担の均衡をはかり(憲法に基づく社会保障制度を解体していく)、健康で年齢等に関係なく働くことができる環境を整備する(働けなくなった時については書かれていない。死んでくれということか?)とし、その推進は、関係閣僚による推進本部と有識者(御用学者)による推進会議がおこないます。
さらに、2015年に安倍内閣は「経済財政運営と改革の基本方針」を閣議決定しました。これは、社会保障費の自然増(年8千億~1兆円)を5千億円程度に抑え、公的年金制度を壊して私的年金へ市場を開放することになります。
昨年末の国会では、強行採決で、マクロ経済スライド未実施分の繰り越し減額、物価スライドに賃金変動率を加味した調整(減額)が決められました。なお歓迎できることもあり、受給資格期間が25年から10年に短縮されました。ただし、10年加入の年金は月額1250円とわずかな額です。
高齢者の実態は、基礎年金のみの受給者が767万人で、その平均月額は約5万円です。厚生年金受給者の平均月額は、男性が16万5千円で女性が10万2千円、月額10万円以下の受給者は393万人です。そして無年金者は約100万人と推定されています。
いま岡山地裁で年金裁判をやっています。マクロ経済スライドで年金が減らされるのは、僕らが生きとる間は大したことはないですが、後の人はとことん減らされます。このマクロ経済スライドは憲法違反だとして203人の原告が国家賠償を求めています。2月13日に第1回口頭弁論があり、100の傍聴席を満席にしました。全国では42都道府県の人が提訴していて、あと2県で提訴を準備しています。5000人を超える原告が国と闘うことになります。主な争点は、憲法25条の生存権、29条の財産権と13条の幸福追求権です。国は、減額は裁量権の範囲内だと主張していますが、国際社会権規約では社会保障の条件の後退は禁止されています。
財源は国内で余っているお金(大企業の内部留保など)に求め、社会保障を充実させよう
年金者組合は、年金改革の5つの提案をしています。
1)雇用は正規が当たり前の社会へ戻すことによって保険料収入が安定する。
2)現役労働者の賃金を引き上げる(1万円アップすれば保険料収入が年間8千億円増)。
3)保険料の上限を引き上げる(現行では31等級の62万円が上限。これを健康保険並みの47等級の121万円に引き上げると年間約8千億円の収入増)。
4)年金積立金の活用は国債の購入に限り、危険な株式投資はしない。
5)国民全員の最低保障年金制度を創設する(共産党の政策は月5万円を最低保障年金額としている)。
財源問題としては、政府のお金は足りませんが、国内全体では大企業の内部留保などでお金は余っているので、そこに財源を求ることで解決できます。税は応能負担・生活費非課税を原則として累進性を強化させましょう。財政支出は、大企業優遇や軍事費優先ではなく、社会保障を優先させましょう。
その後、参加者の意見交換がおこなわれ、「同一労働同一賃金を実行すれば社会保障費の負担は軽減される」、「弱者は団結する必要がある」、「戦争がなくなり軍事支出がなくなれば、人類は豊かになる」、「国立大学が独立行政法人になって国の予算が年々減らされている」などの発言がありました。
最後に、日本共産党の年金政策として、最低保障年金やその財源の確保などを紹介し、社会をよくするために力を合わせようと呼びかけました(「2016年参議院議員選挙/各分野の政策-10、年金」参照)。また、共謀罪に反対する署名も呼びかけました。














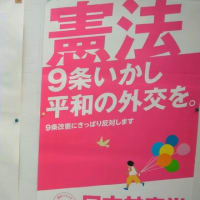

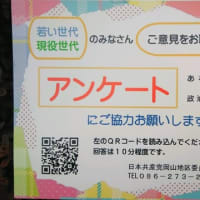



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます