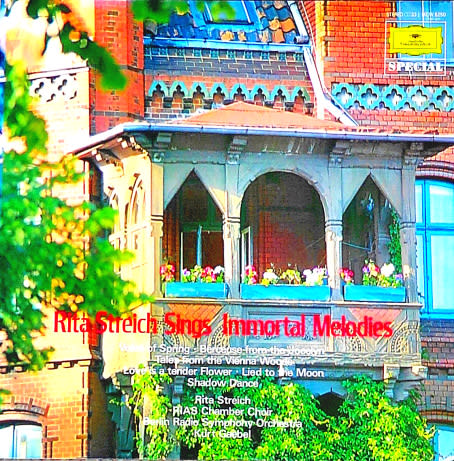モーツァルト:モテット「踊れ、喜べ、幸な魂よ」
シューベルト:ゲーテ歌曲集
ミニヨンの4つの歌
君よ知るや南の国
ただあこがれを知る者だけが
私に言わせないで
この装いを許したまえ
恋人の手紙
恋人のそばに
野ばら
美しい恋人
ソプラノ:エリー・アメリンク
オルガン:レスリー・ピアーソン
指揮:レイモンド・レパード
管弦楽:イギリス室内管弦楽団
ピアノ:ダルトン・ボールドウィン
発売:1975年
LP:日本フォノグラム(フィリップスレコード) PL‐1330(6598 114)
エリー・アメリンク(1933年生まれ、本名:エリザベート・サラ・アーメリング)は、オランダのソプラノ歌手で、1996年に引退してしまったので、現在は、その歌声を聴くことはできないが、現役時代のその澄んだ歌声を、このLPレコードでは存分に聴くことができる。アメリンクは、ソプラノ歌手といっても、オペラではなく、リートやカンタータ、それにオラトリオといった分野で活躍した歌手であり、比較的地味な存在ではあった。当時、同じソプラノ歌手のシュワルツコップ(1915年―2006年)などは、オペラでの目を見張る活躍は、常に楽界の耳目を集めていた。一方、アメリンクの活動の場は、リートを中心としたものであったため、マスコミなどで派手に扱われることは、ほとんどなかったように記憶している。しかし、一方では熱烈なリート愛好家からは高く評価をされ、特にリートファンの多かった日本では、当時、シュワルツコップに劣らない人気を有していたと思う。シュワルツコップもリートのLPレコードを残しているが、あくまで正当性の高い、ある意味では裃を纏ったその歌唱力に圧倒されたように感じていた。それに対し、アメリンクの透明感の中に柔らか味のある歌声は、常に強い親近感が持てたように思う。何か自分のすぐ側にいて歌ってくれているような感じが常にしていたのである。また、コレギウム・アウレウムやイェルク・デムスなど、草創期の古楽器団体や古楽器奏者と共演して、バッハのカンタータやモーツァルトおよびシューマンのリートを録音した。このほか、山田耕筰や中田喜直などの日本の歌曲までも日本語で歌うという、当時としては稀有の存在の歌手でもあったのだ。アメリンクは、古楽界における女性歌手の第一人者カークビーの先駆けとも言うべき声の特徴から、明らかに古楽むきで、 ヘルムート・ヴィンシャーマン指揮のドイツ・バッハ・ゾリステンとバッハのカンタータで度々共演し、日本にも共に来日しCDも残している。そんなアメリンクが、誰もが知っているモーツァルト:モテット「踊れ、喜べ、幸な魂よ」と、有名な「野ばら」を含むシューベルト:ゲーテ歌曲集を歌ったのがこのLPレコードなのである。いずれの曲もアメリンクの暖かみ溢れた透明感漂う歌声に聴き惚れてしまう、珠玉のようなLPレコードに仕上がっている。モーツァルト:モテット「踊れ、喜べ、幸な魂よ」は、第3次イタリア旅行に旅立ったモーツァルトが、その期間中の1773年1月に、ローマのカストラートとラウッツィーニのために作曲した作品。初演は1773年1月17日、ミラノのテアーテ教会で行われた。このLPレコードに収められたシューベルトの歌曲の作曲年代は、次の通りとなる。君よ知るや南の国(1815年)、ただあこがれを知る者だけが(1826年)、私に言わせないで(1826年)、この装いを許したまえ(1826年)、恋人の手紙(1819年)、恋人のそばに(1815年)、野ばら(1815年)、美しい恋人(1815年)。(LPC)