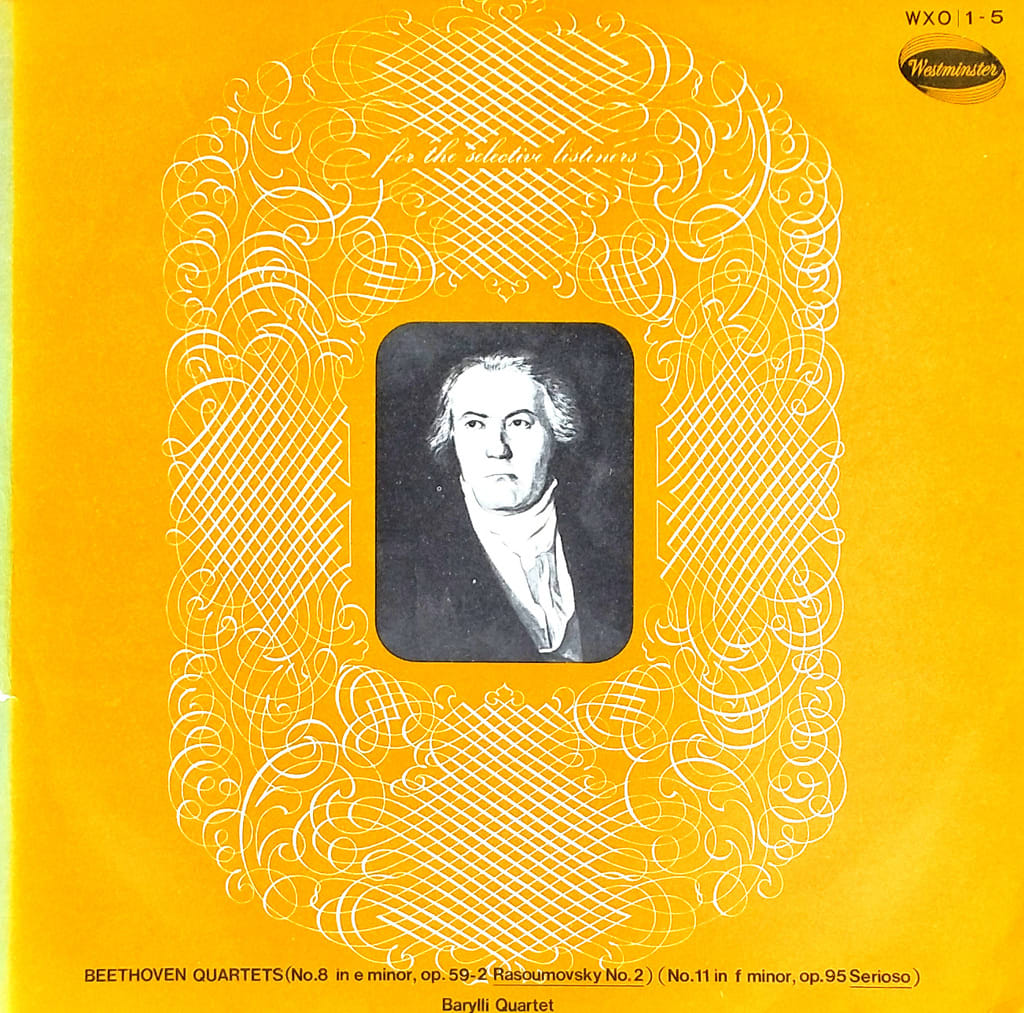シューベルト:弦楽四重奏曲第14番「死と乙女」
弦楽四重奏曲第10番
弦楽四重奏:ウィーン・フィルハーモニー弦楽四重奏団
ウィリー・ボスコフスキー(第1ヴァイオリン)
オットー・シュトラッサー(第2ヴァイオリン)
ルドルフ・シュトレンク(ヴィオラ)
ロベルト・シャイヴァン(チェロ)
発売:1979年
LP:キングレコード GT9254
このLPレコードで演奏しているウィーン・フィルハーモニー弦楽四重奏団は、ウィリー・ボスコフスキー(1909年―1991年)をはじめとして、当時のウィーン・フィルの首席奏者達による、ウィーン弦楽派の最高峰に位置する弦楽四重奏団であり、ヴォルフガング・シュナイダーハン(1915年―2002年)やワルター・バリリ(1921年―2022年)という歴代のコンサートマスターによるムジーク・フェライン弦楽四重奏団のメンバーを引き継いだ弦楽四重奏団でもあった。このLPレコードでの曲は、シューベルト:弦楽四重奏曲第14番「死と乙女」と弦楽四重奏曲第10番の組み合わせだ。有名な弦楽四重奏曲第14番「死と乙女」は、シューベルトがマティアス・クラウディウスの詩に作曲した歌曲「死と乙女」が採用されていることで広く知られている。作曲は、1824年に着手され、完成は1826年とシューベルトとしては時間を掛けた作品。それだけに霊感に飛んでいると同時に、十分な推敲がなされ、あたかもベートーヴェンの弦楽四重奏曲を思わせるような深みと迫力を備えた作品に仕上がっている。一方、弦楽四重奏曲第10番は、1813年に完成した曲。シューベルトの家では、父親のチェロ、兄二人のヴァイオリン、そしてシューベルト自身のヴィオラによって弦楽四重奏曲を演奏して楽しんでいたという。特別に目立つ曲ではないが、このLPレコードのライナーノートで小林利之氏は、「少年時代のシューベルトらしい、伸びやかなメロディーと簡素なスタイルは見逃せない」と書いているように、健康的で明るいシューベルト像がそこにはある。このLPレコードにおけるウィーン・フィルハーモニー弦楽四重奏団の演奏は、弦楽四重奏曲第14番「死と乙女」については、繊細この上ない演奏に終始している。一般的に「死と乙女」の演奏は、どのカルテットも力が入るものであるが、ここでの同四重奏団よる演奏は、通常とは真逆の道を行く。これは、この曲の持つ抒情的な面をことさら強調することによって、新しい「死と乙女」像をつくり出そうとする狙いがあったのかもしれない。デリケートで傷つきやすい「死と乙女」像がそこには出来上がっており、私なぞ「こんな演奏もあるんだ」と感じ入った次第。一方、第10番の演奏については、家庭的で明るく、伸び伸びとした演奏を聴かせ、若き日のシューベルトの残像を追い求めるような演奏内容となっている。(LPC)