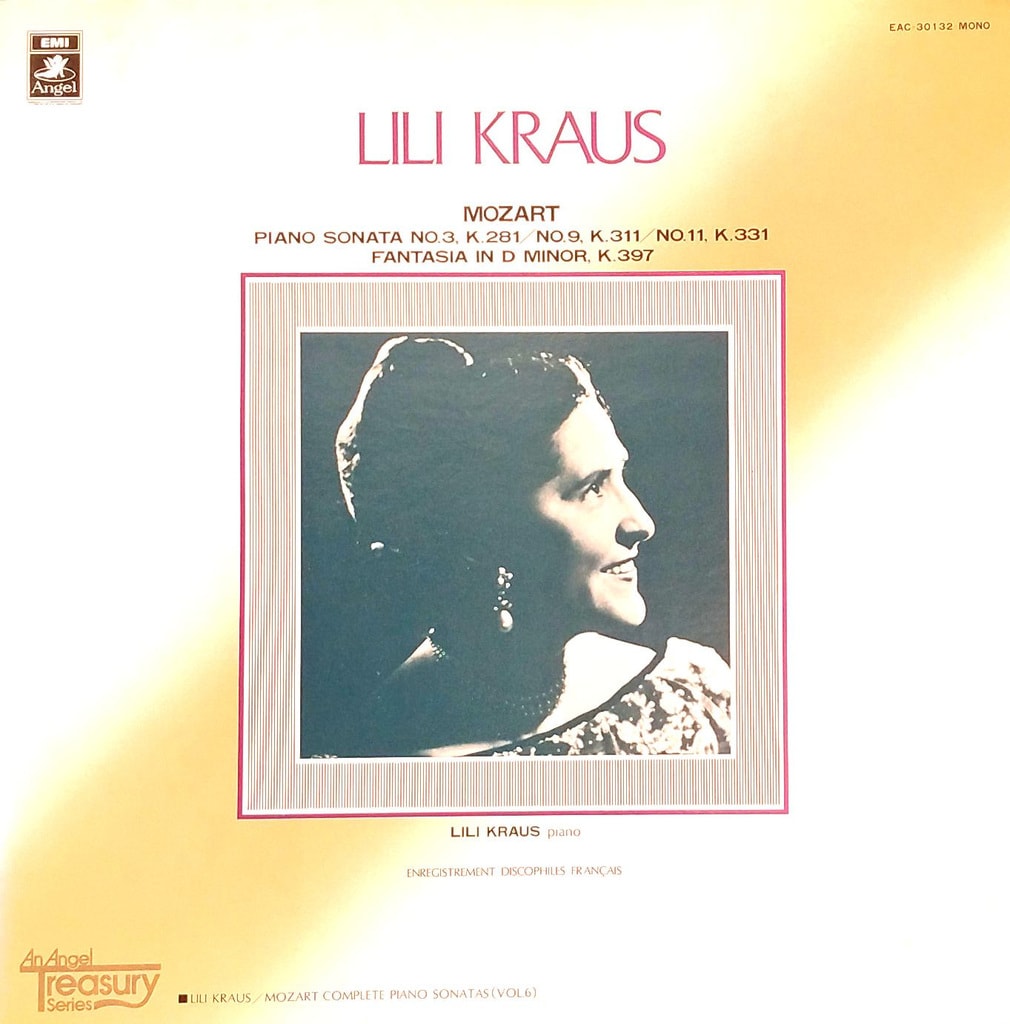マスネ:4手のためのピアノ曲集:「過ぎ去りし年」(第1集~第4集)
第1集「夏の午後」
第2集「秋の日々」
第3集「冬の夕暮れ」
第4集「春の朝」
4手のためのピアノ曲:3つの行進曲
聖母マリア―ガレリアの踊り
第1組曲
2つの子守歌
ピアノ:アルド・チッコリーニ
録音:1979年1月22日、3月15日、6月26日、12月13日
LP:東芝EMI EAC‐50012
このLPレコードは、名ピアニストのアルド・チッコリーニ(1925年―2015年)による、フランスの作曲家のマスネ(1842年―1912年)の“秘曲”とでもいうべき、いずれも4手のためのピアノ曲が収録されている。マスネというと直ぐに「タイスの瞑想曲」を思い浮かべるリスナーが多いのではないだろうか。マスネは、オペラ作曲者として19世紀末から20世紀の初めにかけて大変人気があったが、現在では「マノン」と「ウェルテル」などを除き、そのほとんどが忘れ去られてしまっている。マスネは、1853年、11歳でパリ国立高等音楽学校へ入学し、1862年には、カンタータ「ダヴィッド・リッツィオ」で世界的に有名な作曲賞の「ローマ賞」を受賞。オペラ作品の成功作としては、1884年の「マノン」、1892年の「ウェルテル」それに1894年の「タイス」が挙げられる。マスネは、オペラの他には、バレエ、オラトリオ、カンタータ、管弦楽作品、ピアノ曲さらに200以上の歌曲を作曲している。このLPレコードで演奏しているアルド・チッコリーニは、イタリア・ナポリ出身で、フランスで活躍した名ピアニスト。1949年パリの「ロン・ティボー国際コンクール」に優勝。1969年にはフランスに帰化している。パリ音楽院で教鞭を執ったこともあり、フランス近代音楽の解釈者として世界的にもに著名である。80歳を超えても第一線のピアニストとして活躍し、高齢にもかかわらず来日し、日本の聴衆に深い感銘を与えた。このLPレコードに収録された曲は、通常では滅多に聴くことのない曲ではあるが、いずれの曲もフランス風の洗練された感覚が魅力になっている。マスネの曲は、特にメロディーが美しいことで知られているが、これらのピアノ曲も例外でなく、いずれも甘美とも言える美しいメロディーに覆い尽くされている。4手のためのピアノ曲集:「過ぎ去り年」は、マスネ版「四季」とも呼べる作品で、第1巻から順に夏・秋・冬・春と辿り、1年が巡るようになっている。題名の「過ぎ去り年」とは、遠く去った昔の年月ではなく、自分が過ごしてきたこの1年を意味している。作曲年代は、パリ音楽院の作曲科の教授を退いた1896年、54歳の時で、作曲家として脂の乗り切った頃の作品。この曲は、全曲を演奏するのに30分近くを要し、いかにもマスネらしい、美しい旋律に溢れた佳曲。アルド・チッコリーニは、これらの“秘曲”を愛情を持って弾いている。通常ではあまり聴くことができないが、今後、これらのマスネの優れたピアノ曲が聴かれる機会が増えてほしいものだ。(LPC)