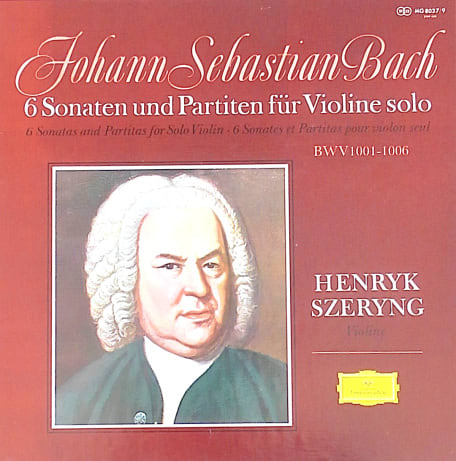バッハ:平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV846~869
第2巻 BWV870~893
ピアノ:スヴャトスラフ・リヒテル
録音:第1巻:1970年夏、第2巻:1973年2月、8月、9月/ザルツブルク、クレスハイム宮殿
LP:ビクター音楽産業 VIC‐4072~6
バッハの平均律クラヴィーア曲集は、「平均律」と「クラヴィーア」という2つの言葉を理解して聴くと、より理解が深まる。古代ギリシャ時代に、振動数比2対3という純正5度によって全音階をつくるピュタゴラス音律がつくられた。その原理が中世に受け継がれ、エオリア、イオニアなどという12旋法が生まれた。しかしもともと、ピュタゴラス音律は、オクターブの振動数比1対2に重なり合う音が得られず、厳密な意味での純正律とはなっていない。やがて、16世紀のポリフォニー全盛時代を迎え、全音音階が揺らぎ、半音が使用されることが多くなっていく。17世紀~18世紀になると12音階のそれぞれを基音として調がつくりだされる。ここで、調性の発達のための新しい調律法をつくり出す必要性が生まれることになった。そこで考えだされたのが平均律である。平均律とは、1オクターヴの12の半音の音程を一定にするという形で、自然な和音の音程に調整を加える調律法のことをいう。これによって、鍵盤楽器でも12の長調と12の短調の使用が可能となった。バッハは、この新発明の調律法である平均律をいち早く取り取り入れ、書いたのが平均律クラヴィーア曲集というわけである。当時のバッハは、最先端を行く音楽技法を駆使する新し物好きの作曲家であったわけである。それでは「クラヴィーア」とは、いったい何を指すのであろうか。当時、バッハは、クラヴィーアを特定の楽器に限定しないで、オルガン、クラヴィコード、クラヴィチェンバロなど、鍵盤楽器のすべてに使っていたという。そのため、この平均律クラヴィーア曲集は、特定の鍵盤楽器のために書かれた作品ではなさそうだ。このため題名にバッハ自身が印した「よく調律されたクラーヴィーア」とは、現代のピアノでも一向にかまわないことになる。このLPレコードで演奏しているのは、ロシアの名ピアニストのスビャトスラフ・リヒテル(1915年―1997年)である。リヒテルは、男性的で芯のある力強い演奏によって、曲の核心をずばりとつき、圧倒的な印象をリスナーに与える。ところが、このバッハ:平均律クラヴィーア曲集の演奏では、むしろ叙情的な感情を存分に込めたような演奏を披露している。芯がピーンと張った演奏ではあるのだが、何か、バッハへの敬愛がこもった、人間臭さを存分に発揮した、リヒテルとしては比較的珍しい演奏のように思う。テンポは安定しており、リヒテルの演奏を通して、バッハのフーガの世界にどっぷりと身を浸すことができる、限りなく内容の濃い演奏となっている。(LPC)