みなさん ちょっとご相談 ! 
この 石造りの仏様 軽井沢のどこにあるか 知ってますか?

江戸時代の 安永3年(1774)と年号が刻まれていて 追分宿西の外れ「 追分の分か去れ(わかされ) 」
と呼ばれる  中山道(現:国道18号線)と江戸時代の北国街道が分岐する「 追分宿 」の信号西側
中山道(現:国道18号線)と江戸時代の北国街道が分岐する「 追分宿 」の信号西側

こんな風に 8基の 石造物が並ぶ三角地形の 1番西奥側に佇んでいるんだ
背中側のお隣さんの変遷が激しくて  現在はオフ・ロードカーか何かの販売店になっているようだね
現在はオフ・ロードカーか何かの販売店になっているようだね
あまり日頃、石仏を 見慣れていない人にとっても こうして改めてみると ちょっと
同じ時代モノの 石仏様やお地蔵さまとなんとなく感じが違うかな‥ とか 変わっているな・・
とか ちょっと詳しい人には こんなのもあるんだ・・ って気がするんじゃないかな
このあいだも 年配の男性グループが ネームカードをぶら下げた男性から
この石仏様を囲んで 熱心に説明を聞いたり 画像に収めたりしているのを見かけた
みなさんに 「 相談 」というのは  この石仏様のこと
この石仏様のこと
この石仏様の正面足元に 大きな刻字で 「 牛 」「 千疋飼 」「 馬 」とタテ3列に刻まれていて
それぞれの 見識ある学者様は それぞれに この石仏様を  関連書籍の中で
関連書籍の中で
長野県歴史の道調査報告書(1984) では 「 観音菩薩立像(図内表記は観音菩薩像塔) 」
地元の石造仏の第一人者と高名な学者先生はその膨大な調査資料集(1986調査)の中で 「 勢至菩薩像 」
「 軽井沢町の石造文化財 」(1985)の中では 「 鳥獣供養塔 」
そして 2年前に発行された 「 軽井沢町石造物ガイドブック 」(2019)では「 聖観音 」
ボクには  どれが何だか さっぱりわからない・・
どれが何だか さっぱりわからない・・
仲良しのボクの森の下に住む奥さんのお友達で 歴女さんがいて 最新の出版物に記された
「 聖観音 」というのが どういう経過で表記されたのか 関係者にそれとなく訊ねたところ 
「 聖観音だから聖観音 違うと言うなら これが何なのか教えてください 」と バッサリ !
確かに NET百科事典なんかでのククリは 「 聖観音 」を
「 多面多臂などの超人間的な姿ではない、1面2臂の像を指して聖観音と称している 」としていて
この石仏様 お顔ひとつ 腕(臂)2本 のお姿ではあるけれど・・ 
お話の中で 「 長野県歴史の道調査報告書 」(1984)の 解説文中に 
「分去れ」の奥に異形の観音菩薩立像がある。
安永3年11月の建立で役牛馬持連中が牛馬の供養のために立てたものと思われる。(文中より引用)
こんな風に あくまで 建てた人から直接でも経緯を聞かない限り 祭祀目的や思いは判らない
牛馬の刻字があるのに 「 馬頭観音 」とも 呼ばれない 
異形とも 異様な優美さとも感じられるその印象から 安易にひとくくりの名称にしなかったのかもしれない
誰か 「 学識者 」が 1種のファイナルアンサー的な 名称をつけてしまうと・・
ま、 どの名称にしても 同じリクツになるのか・・ 
みなさんの中で 誰か こーゆーの 「 ああ それはね・・・ 」 って人  いませんか ?
いませんか ? 

 東と南の見晴らしがよくて、西日と北風があまりあたらない場所がある
東と南の見晴らしがよくて、西日と北風があまりあたらない場所がある 落っこちている現場に出会う
落っこちている現場に出会う 〇くらいの大きさの
〇くらいの大きさの
 あまり 美味しくないのか小鳥が集まって来る様子でもない
あまり 美味しくないのか小鳥が集まって来る様子でもない ファイナルカウントダウンを始めて
ファイナルカウントダウンを始めて 思わず 深呼吸するんだな
思わず 深呼吸するんだな 











 夏の終わりのお楽しみイベントが開催されたそうだね
夏の終わりのお楽しみイベントが開催されたそうだね 明治42(1909)年6月25日「 追分仮停車場 」として開業し
明治42(1909)年6月25日「 追分仮停車場 」として開業し
 それからは 無人駅 になっているんだ
それからは 無人駅 になっているんだ イベントの延期や中止が頻発
イベントの延期や中止が頻発




 手が出せないものなのか 気になっている人もいそうだ
手が出せないものなのか 気になっている人もいそうだ


 中山道(現:国道18号線)と江戸時代の北国街道が分岐する「 追分宿 」の信号西側
中山道(現:国道18号線)と江戸時代の北国街道が分岐する「 追分宿 」の信号西側
 現在はオフ・ロードカーか何かの販売店になっているようだね
現在はオフ・ロードカーか何かの販売店になっているようだね この石仏様のこと
この石仏様のこと どれが何だか さっぱりわからない・・
どれが何だか さっぱりわからない・・


 いませんか ?
いませんか ?  強めの日差しが照り付けて う~~~ン久しぶりに朝から夏らしい・・
強めの日差しが照り付けて う~~~ン久しぶりに朝から夏らしい・・ とてつもなく大昔の歴史ロマンの一端が
とてつもなく大昔の歴史ロマンの一端が


 8月最後の週末、金曜日だけれど
8月最後の週末、金曜日だけれど  幹線道路の流れは空いていて 静かでいい感じ
幹線道路の流れは空いていて 静かでいい感じ
 「 ポール・ジャクレー全木版画展 」 を 見学がてら 追分宿を散策して来たんだってさ
「 ポール・ジャクレー全木版画展 」 を 見学がてら 追分宿を散策して来たんだってさ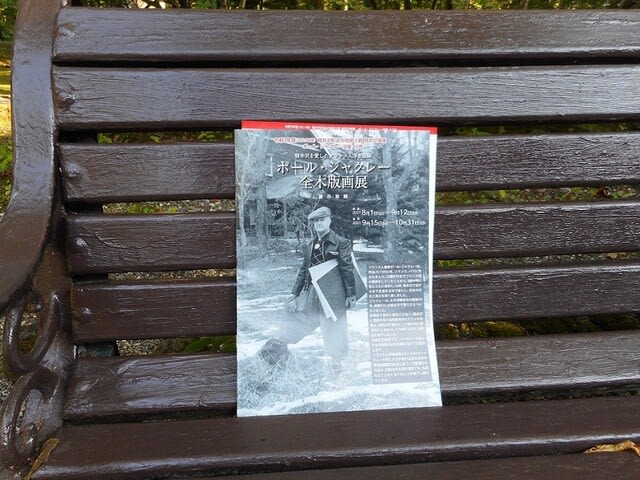
 「 目録集 」なんだって
「 目録集 」なんだって





