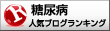今朝の血糖値です。162(mg/dl)です。ちょい高し(´・ω・`)まぁ、こういう日もあるさ!ふん!
全く同じの「手術ケース」だったので記載。

がんなどで膵臓(すいぞう)の一部を切除すると、血糖値を下げるインスリンの分泌量が減って糖尿病を発症しやすくなる。九州大の小川佳宏教授(内分泌・代謝学)の研究チームは、膵臓の切除部位によって糖尿病のなりやすさに差があることを確かめた。どうやら腸内細菌の変化や、膵臓細胞の“疲労度”が関係しているらしい。小川さんは「手術後の患者さんの生活管理に役立つ。2型糖尿病の発症解明にもつながりそうだ」と話す。
▽沈黙の臓器
膵臓はおなかの中にある長さ20センチほどの細長い臓器。食物を消化する膵液や、血糖値を調節するホルモンを分泌する。膵臓のベータ細胞で作られるのが血糖値を下げるインスリン。分泌量が減ったり働きが弱まったりすると糖尿病につながる。
膵臓がんは症状が出にくく早期発見が難しい。肝臓と並んで「沈黙の臓器」と呼ばれる理由だ。悪性化していなくても腫瘍が見つかると予防的に切除することがある。
手術方式は腫瘍ができた部位によって異なる。「膵頭十二指腸切除」はつながった十二指腸や胆管ごと膵臓の頭部を大きく取り除く。消化管のバイパス手術も行うため6~8時間を要する。
体部や尾部を脾臓(ひぞう)と一緒に取り除く「膵体尾部切除」は2~3時間で済む。体への負担は比較的軽い。いずれの手術も残りの膵臓が半分近くになるため、インスリンの分泌量が減って同じように糖尿病になりやすいと考えられていた。
▽驚きの結果
ところが小川さんらが東京医科歯科大や国立国際医療研究センター研究所などと患者を6年間にわたって追跡すると、驚くような結果が出た。
2014~17年にいずれかの手術を受けた患者48人の経過を調べた。すると膵体尾部切除を受けた28人のうち60%近くが糖尿病を発症したのに対し、膵頭十二指腸切除を受けた20人では発症率が10%程度と顕著に低かった。手術は大がかりなのに糖尿病になりにくいことが分かった。
「そんなにはっきりとした差が出るとは思わなかった」と小川さん。「以前は患者さんに一律に『いずれ糖尿病になるからインスリンが必要になるかもしれません』と伝えていたが必ずしもそうではなかった」と語る。調べると意外な理由が分かった。膵頭十二指腸切除を受けた人は腸内細菌のバランスが変化し、小腸から分泌される別のホルモンの働きでインスリンの量が増えていた。十二指腸を切除した影響とみられ、残った膵臓の働きが強まるらしい。
一方、膵体尾部切除の人ではこうしたホルモンの変化はみられなかった。むしろ切除した膵臓を調べるとベータ細胞が肥大し、疲労して働かなくなる「脱分化」という現象が起きている人が多かった。
▽限界超え
小川さんは「高血糖や肥満などの代謝ストレスにさらされて疲労度が高まったベータ細胞はインスリン分泌の予備力が落ちている。膵臓を半分摘出することで限界を超えてしまうのではないか」とみる。
2型糖尿病も個人の体質に加えて長年の生活習慣が発症のしやすさやタイミングを左右する。「限界ぎりぎりで働いていた膵臓に新たなストレスが加わって発症するという図式が見えてきた」と話す。
膵体尾部切除は膵頭十二指腸切除に比べ、残った膵臓への負担が大きくなる可能性がある。こうした患者は将来の糖尿病発症に気を付ける必要がありそうだ。小川さんは「今後は血液検査や切除した膵臓の解析などで糖尿病の発症リスクを予測する手法を開発したい」と話す。(共同=吉村敬介)