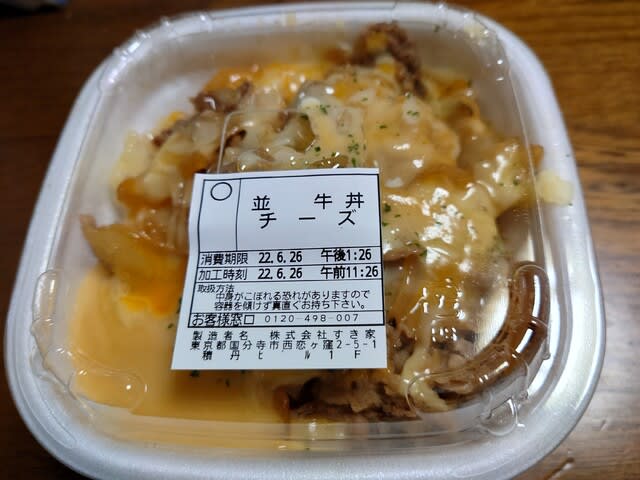4.介護保険について
〇介護保険について長期の計画を立てるべきではないかと何回か質問したが、いつもその都度政府の見える化というのがあって一定長期の見通しはできているという答弁でだいたい終っていたのでその見える化について質問したい。
⇒地域包括ケア見える化システムは自治体の介護保険事業計画の策定を総合的に支援するため平成27年度から稼働している厚生労働省運営による情報システム。
地域包括ケアシステムの構築に関するさまざまな情報が一元化され、グラフ等で見やすくなっている。
システムには全国自治体の人口推計、要介護認定率と認定者数、保険給付費、保険料の基礎データが集約されている。多自治体のデータも参照できるので類似団体との比較もでき自治体の事例も参照できる。
〇市民の方が見ようと思えば見られるのか❔
⇒一定程度の内容は見られる。
〇全国でなく国分寺市のデータが見られるのか❔
⇒細部については把握していない。
〇3年ごとの計画を作る時に見える化システムを利用しているそうだが、どういう形で利用しているのか❔
⇒本市の実績をシステムに入力すると本市における介護保険サービスの給付量等々を推計して、それに対する対応を計画に盛り込んでいく。
〇介護保険制度は2040問題があり、2040年に高齢者人口が4000万人でピークを迎え大きな問題と言われている。
介護給付費は2018年の10.7兆円から2040年には25.8兆円、介護職員の必要数も2019年の211万人から2040年には280万人と言われている。
このままいったら2040年に介護保険制度がどうなっていくのか、少子化も早まっていて危惧している。
3年度ごとの計画はそれはそれで必要だが、高齢化のピークまでの2040年までのシナリオを各自治体できちんとやっていけるのかというシナリオは別途必要だと思うがいかが❔
⇒介護保険事業計画については法により3年を一期として定めることになっている。
国もこの期間を踏まえて基本指針を示している。また、地域の多様な状況を反映して機動的な対応や改善を行うには3年が望ましいとの見解もある。
また、近年の介護予防・日常生活支援総合事業の開始など制度変更による影響は中長期にわたって見込むことは難しい。
長期の見込みについては現在の3年の計画策定においても認定者数や認定率などの長期の推計も踏まえて施策の方向性を検討している。
3年サイクルの計画策定は基本として進めていく。その中で長期の推計も踏まえて策定する。
〇3年の計画は8期目で定着しているし必要だ。
長期的な見通しも一般にも公開して市民の方にも知っていただく必要がある。