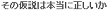いまどこ ―冒頭表示2
キーボードの2段めと3段目はなぜ互い違いになっていないの - 教えて!goo:
に答えてってな形で部分統合しようかナとも思う。
http://blog.goo.ne.jp/raycy/e/c11db5b33d4a1d67900e568ab0dc6273ではちょっとスレ違うと思う。
http://www6.atpages.jp/~raycy/Q/ を http://www6.atpages.jp/raycy/blog2btron/door やらの作業経過を取り入れつつ、ふくらませるようなかんじで、、
http://www6.atpages.jp/~raycy/Q/ を http://www6.atpages.jp/raycy/blog2btron/door やらの作業経過を取り入れつつ、ふくらませるようなかんじで、、
(a)DSKが開発されたころ、米国をはじめ、全世界が不況のどん底にあった。記録によれば、当時のタイプライタ・セールスマンに課せられた重要な任務の一つは、市場に出た中古タイプライタを見つけて安く買い取り、新しいタイプライタが1台でも多く高く売れるようにと、古いものをこわしてしまうことであった( Bliven 1954 )。そのような状況下では、どこのメーカーでも2台分のタイプライタの仕事を1台でこなしてしまうような新しい機械の製造に興味を示すはずはなかった。また、職にありつけないでいるタイピストたちも巷にはたくさんいた。
しかし大学教授として世情にうとかったらしいドボラクは、DSKの採用は多くのタイプライタやタイピストの削減が可能であると主張していたのである。(実際には、より簡単にタイプできる鍵盤は新しい使用者を多く獲得して、タイプライタの販売促進のための有力な武器になった に違いないとも思われる。)http://b.hatena.ne.jp/raycy/20090917#bookmark-16073940
米国事務経営協会( National Office Management Association, 通称 NOMA )は、その独自の立場を利用して、学校、事務所、製造業者たちなどに、DSKの使用を通して進歩の道をとるよう慫慂する意向をもっていた( American Business 1956 )
Bliven 1954
Remington Noise- less typewriter
Davis 1977
[ ]Bliven,Bruce,Jr., 1954, The Wonderful Writing Machine, Random House.
[ ]Davis, Philip, 1967, The keyboard of the future is here now!, Easy Keyboard Co., Irvington, New Jersey, 8pp.
[ ]Davis, Philip, 1977, History of the Dvorak Arrangement for Alphanumeric Keybosrds since 1944, Quick
Strokes, West Sacramento, California, 5pp, February.
[ ]American Business, 1956, Dvorak keyboard back in the news, 26, p.41, February.
タイピングの音おそびアクションの派手さ大きさによる仕事やってます感かもし出し演出アピール顕示性
5線式電信機 5針式電信器
5bitリレーとかで検索してhttp://b.hatena.ne.jp/raycy/20090917#bookmark-16070113、例の記述を探していた。http://b.hatena.ne.jp/raycy/20090917#bookmark-16070297
そのあと、five-unit codeとかもみたりしたな。http://b.hatena.ne.jp/raycy/20090917#bookmark-16070892
そうこうしてるうちに、5線式電信とかが、目にはいった。http://b.hatena.ne.jp/raycy/20090917#bookmark-16071493
みてみると、ホイットストーンとかも絡んでいるらしい。http://b.hatena.ne.jp/raycy/20090917#bookmark-16072079ホイートストンか、、
1837年だとか、、
5線 5針 とあったので、反応してみたが、5ビットとのつながりは、、ないのかも、、
と思ったら、あった。
ウィートストンのコードはどうなっていたのかな、。
http://chem.ch.huji.ac.il/history/cooke.html
やや?三進数五桁だな。5ビットじゃない。コードは、三進数で5桁。5ビットじゃないんじゃないか、
ありゃ、二進五桁もあった。不定というか、電荷なし状態は使わないことにしたんだ。
じゃあやっぱり五ビットか。
コードは、三進五桁か5ビットか微妙、5ビット以下、不定長?
5bitリレーとかで検索してhttp://b.hatena.ne.jp/raycy/20090917#bookmark-16070113、例の記述を探していた。http://b.hatena.ne.jp/raycy/20090917#bookmark-16070297
そのあと、five-unit codeとかもみたりしたな。http://b.hatena.ne.jp/raycy/20090917#bookmark-16070892
そうこうしてるうちに、5線式電信とかが、目にはいった。http://b.hatena.ne.jp/raycy/20090917#bookmark-16071493
みてみると、ホイットストーンとかも絡んでいるらしい。http://b.hatena.ne.jp/raycy/20090917#bookmark-16072079ホイートストンか、、
1837年だとか、、
5線 5針 とあったので、反応してみたが、5ビットとのつながりは、、ないのかも、、
と思ったら、あった。
http://www.tdk.co.jp/techmag/ninja/daa00171.htmhttp://b.hatena.ne.jp/raycy/20090917#bookmark-16073578
ところで、電信機の発明史はいささか複雑です。モールス電信機の発明と同じ年の18 37年、イギリスの物理学者ホイートストンが5針式電信機を考案して、モールス電信 機よりも早く実用化されているからです。ホイートストンの5針式電信機というのは 、図のように5つの磁針を備えたものです。磁針は振れる・振れないの2通りの状態 があるので、2の5乗=32通りの組み合わせがつくれます。ホイートストンはアルフ ァベット文字を盤上に配列することで、磁針の振れがどの文字を表すかを一目で読み 取れるようにしました。今日風にいえば、5ビットのデジタル通信です。
ウィートストンのコードはどうなっていたのかな、。
http://chem.ch.huji.ac.il/history/cooke.html
やや?三進数五桁だな。5ビットじゃない。コードは、三進数で5桁。5ビットじゃないんじゃないか、
ありゃ、二進五桁もあった。不定というか、電荷なし状態は使わないことにしたんだ。
じゃあやっぱり五ビットか。
コードは、三進五桁か5ビットか微妙、5ビット以下、不定長?
一つ前の記事もそうだったが、しばらく前から、
gooブログの,記事の投稿クリック後に認証画面が出ても、認証クリックすれば投稿通るようになった。
gooブログの操作性向上している。データ落ち、しにくくなった。
認証の賞味期限切れにともなう追加確認の認証前でも、いったんgooブログ側が記事データを受つけて受信してバッファしてくれてるって事なんでしょう。以前は、データ捨てられていた。
gooブログの,記事の投稿クリック後に認証画面が出ても、認証クリックすれば投稿通るようになった。
gooブログの操作性向上している。データ落ち、しにくくなった。
認証の賞味期限切れにともなう追加確認の認証前でも、いったんgooブログ側が記事データを受つけて受信してバッファしてくれてるって事なんでしょう。以前は、データ捨てられていた。
フロントエンドプロセスのスイッチングコスト?
今変えなきゃならないかもなことは
Firefoxの履歴機能の一時凍結、あるいは、ずっと古い分をアーカイブに切り離し。たぶん、このsqliteデータベースファイルの大きさの所為だと思うので。でないと、あまりの重さに耐えられない。
姫踊子草か、DvorakJか。軽くなるなら、。ただ、μTRON配列のマップ書かないといけないのかも。
どっこいしょ、よっこらしょ、いっちょやってみるかも。
スイッチング、気が重い、、気が乗らない、乗り気がしない、、
今変えなきゃならないかもなことは
Firefoxの履歴機能の一時凍結、あるいは、ずっと古い分をアーカイブに切り離し。たぶん、このsqliteデータベースファイルの大きさの所為だと思うので。でないと、あまりの重さに耐えられない。
姫踊子草か、DvorakJか。軽くなるなら、。ただ、μTRON配列のマップ書かないといけないのかも。
どっこいしょ、よっこらしょ、いっちょやってみるかも。
スイッチング、気が重い、、気が乗らない、乗り気がしない、、
山田尚勇の「印字棒が絡まるといった機械的な問題は速かに解決されていった」http://b.hatena.ne.jp/raycy/20090916#bookmark-16057032
Davidの「1879年」
英wikipediaのtypebarに「Mechanisms to avoid such jamming had been created by 1879,」とあったので、これは何のことかと思った。
メカというか、type-wheel or type-sleeve マシンのことのようだ。
山田尚勇の言う「解決」とはなんだろうか。バネ復帰with引き金はずれ状態あり、かな?http://blog.goo.ne.jp/raycy/e/b6d71c0aaf8a441b1db751e2e320f958
まあタイプライターにおいて、なぜタイプホイールでなくてタイプバーメカニズムが勝ったか、って問題があるのだが、これは、文字頻度傾斜配分 http://blog.goo.ne.jp/raycy/e/b8d4510a796f1a1ac4209fbd6ca772a3 http://blog.goo.ne.jp/raycy/e/e782e78fe2960bdac108a8fd2b0c7724 と待ち心理やら、所要エクセルギーの対出力ネゲントロピー比といったことから、説明できるやもしれず、、http://blog.goo.ne.jp/raycy/e/54d324a499dd97676290551346be0ca2
Davidの「1879年」
英wikipediaのtypebarに「Mechanisms to avoid such jamming had been created by 1879,」とあったので、これは何のことかと思った。
http://b.hatena.ne.jp/raycy/20090916#bookmark-16057644
Nor was its future much protected by any compelling technological necessities. For, there were ways to make a typewriter without the up-stroke typebar mechanism that had called forth the QWERTY adaptation, and rival designs were appearing on the American scene. Not only were there typebar machines with "down-stroke" and "frontstroke" actions that afforded a visible printing point; the problem of typebar clashes could be circumvented by dispensing with typebars entirely, as young Thomas Edison had done in h s 1872 patent for an electric print-wheel device whch later became the basis for teletype machnes. Lucien Stephen Crandall, the inventor of the second typewriter to reach the American market (in 1879) arranged the type on a cylindrical sleeve: the sleeve was made to revolve to the required letter and come down onto the printing-point, locking in place for correct alignment. (So much for the "revolutionary" character of the IBM 72,432's "golf ball" design.) Freed from the legacy of typebars, commercially successful typewriters such as the Hammond and the Blickensderfer first sported a keyboard arrangement which was more sensible than QWERTY. Then so-called "Ideal" keyboard placed the sequence DHIATENSOR in the home row, these being ten letters with which one may compose over 70 percent of the words in the English language.
メカというか、type-wheel or type-sleeve マシンのことのようだ。
the problem of typebar clashes could be circumvented by dispensing with typebars entirely,http://b.hatena.ne.jp/raycy/20090916#bookmark-16057644
OCN|翻訳サービス:http://www.ocn.ne.jp/translation/
タイプバー衝突の問題は、タイプバーを完全に省くことによって出し抜かれえました、
山田尚勇の言う「解決」とはなんだろうか。バネ復帰with引き金はずれ状態あり、かな?http://blog.goo.ne.jp/raycy/e/b6d71c0aaf8a441b1db751e2e320f958
まあタイプライターにおいて、なぜタイプホイールでなくてタイプバーメカニズムが勝ったか、って問題があるのだが、これは、文字頻度傾斜配分 http://blog.goo.ne.jp/raycy/e/b8d4510a796f1a1ac4209fbd6ca772a3 http://blog.goo.ne.jp/raycy/e/e782e78fe2960bdac108a8fd2b0c7724 と待ち心理やら、所要エクセルギーの対出力ネゲントロピー比といったことから、説明できるやもしれず、、http://blog.goo.ne.jp/raycy/e/54d324a499dd97676290551346be0ca2