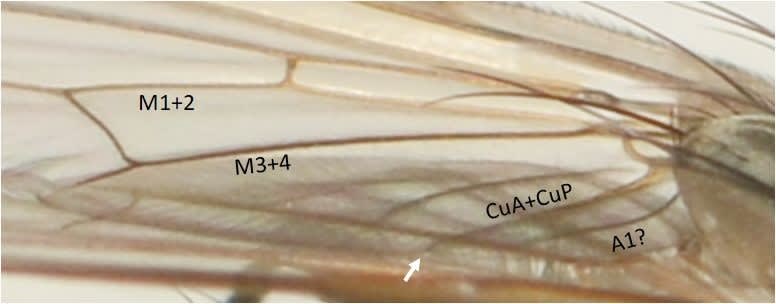5月16日に六甲高山植物園で見た花の続きです。

この目立たない植物はシクラメンの一種 Cyclamen hederifoliumです。その近くにはくるくると巻いたものが見られます。


家族が「花のガイド」に参加して聞いてきました。花が終わって実ができると、こんな風に花軸がらせん状に巻いて、そのまま実を地面の中に押し込んでしまうそうです。

ちょっと引っ張るとこんな風にらせんになって伸びます。面白いですね。でも、こんな風になるのは原種だけなのだそうです。シクラメンの学名cyclamenはcircle(円)から来たようですが、この形状を表したものでしょうか。


これはユキモチソウ。「山に咲く花」によると、「花序の付属体の先端が、雪のように白くてやわらかく餅のようなことから名づけられた」そうです。

近くにはこんな実があちこちに出ていました。


これはカタクリの実のようです。


それからシュンラン。


クリンソウは一面に咲いていました。

ニッコウキスゲはまだなのか、こんな風にぽつんぽつんと咲いているだけでした。

これはサラサドウダンです。これについても「花のガイド」で説明があったようです。

通常、花は下向きに咲いていますが、花が終わると左側にあるように一年かけて上向きになるそうです。


こちらはキビヒトリシズカ。

それにエビネ。

それからサルメンエビネ。六甲高山植物園で見た花も、後、もう少しで終わります。

この目立たない植物はシクラメンの一種 Cyclamen hederifoliumです。その近くにはくるくると巻いたものが見られます。


家族が「花のガイド」に参加して聞いてきました。花が終わって実ができると、こんな風に花軸がらせん状に巻いて、そのまま実を地面の中に押し込んでしまうそうです。

ちょっと引っ張るとこんな風にらせんになって伸びます。面白いですね。でも、こんな風になるのは原種だけなのだそうです。シクラメンの学名cyclamenはcircle(円)から来たようですが、この形状を表したものでしょうか。


これはユキモチソウ。「山に咲く花」によると、「花序の付属体の先端が、雪のように白くてやわらかく餅のようなことから名づけられた」そうです。

近くにはこんな実があちこちに出ていました。


これはカタクリの実のようです。


それからシュンラン。


クリンソウは一面に咲いていました。

ニッコウキスゲはまだなのか、こんな風にぽつんぽつんと咲いているだけでした。

これはサラサドウダンです。これについても「花のガイド」で説明があったようです。

通常、花は下向きに咲いていますが、花が終わると左側にあるように一年かけて上向きになるそうです。


こちらはキビヒトリシズカ。

それにエビネ。

それからサルメンエビネ。六甲高山植物園で見た花も、後、もう少しで終わります。