わが町目黒には、「目黒シネマ」という、2本立ての映画上映館があります。
きょうは、のんびりいつものカフェで、と歩いていると、『かもめ食堂』の看板が。
以前から気になっていた映画だったので、ふらっと観てまいりました。
ヘルシンキの街中に、おにぎりをメインメニューにした「かもめ食堂」のお話です。
全編あったかーいエネルギーに包まれていて、大阪帰りのボクとしては、とても癒された時間でした。
開店したけれども、まったくお客が来ない「かもめ食堂」
それでも、まいにち、たんたんとお皿やコップを磨く女店主。
そこに、ようやく初めてのお客が・・・
それは、やたら日本かぶれの、おたくっぽいフィンランド青年。
おまけに、おかしな日本人女性が一人、また一人とまるで「かもめ食堂」に、ひきつけられるかのようにあらわれる。
コーヒーを美味しく入れるおまじないを教えてくれるオッサンやら、だんなに逃げられたおばさんも、入れ替わり立ち代りに登場します。
やがて、かもめ食堂は・・・・・・・
主役の小林聡美さんが、なんともステキでした。
ほんとにこころがあったまる作品です。
そして、更に時間もあったし、特に急ぎの用事も無かったために、二本目も観てしまったんですよ。
これが、だいだいだいだいだい感動でした。
『The Last Trapper(狩人と犬、最後の旅)』
極北の狩人ノーマン・ウィンター{実在の人物です}のお話です。
主人公は、ノーマン自らが演じて?います。
ドキュメントというわけではないけれども、演技をしている映画ってわけでもない。
秋のロッキー山脈 ユーコンの川をカヤックで下っている壮大なシーンから始まります。

ネイティブアメリカン ナハニ族のネブラスカという奥さんと、シベリアンハスキー犬7頭との、生活を描いた作品です。
「最後の狩人」といわれるほどに、狩をする民がほとんどいなくなっている。
その中でも、ネイティブたちでさえ、スノーモービルや、GPSを使って狩をしているのに、ノーマンはいまだにそりを犬に引かせて冬場の狩を続けているのです。
時折、町まで1週間ほどかけて出かけて、生活用品を調達したり、毛皮を売りにいったりする生活。
心の奥底から「あこがれてしまう生き方」
もちろん、到底軟弱なボクにできっこないですけどね。
この大自然の宝庫にも、「経済」は容赦なく立ち入り、森を伐採し、獣がすめなくなっている。
ノーマンは今年限りで、狩の生活を終え、ロッキーを去る決意をするのです。
最後の冬を、獣たちの生存する狩場で過ごすために、住まいを更に山の奥深くに移します。
あっという間に見事なキャビンを夫婦で建ててしまうんです。
愛するリーダー犬を、町で不慮の事故でなくし、代わりにハスキーの子犬をもらいます。
しかし、「そりを引く犬」ではないために、ノーマンは「ダメ犬」というレッテルをはるのです。
そんなある日、少し早く凍った氷原をそりで横断する際に、氷が割れて犬ともども凍てつく湖水にはまってしまいます。
驚いた犬たちは必死に脱出し、そのまま走り去ってしまうのです。ノーマンを湖の中に残したまま。
「ウォーク!!」とリーダー犬の名を呼ぶものの、パニックになった犬たちは走り続けます。
体温低下、崩れていく氷塊、麻痺していくからだ、空気に触れた瞬間に凍りつく服・・・そのときノーマンはダメ犬のアパッシュの名を呼びます。
アパッシュはその声を聞き、綱でつながれた群れを、もう一度ノーマンの元へ連れ戻すのです。

やっとの思いで命を救われたノーマンと、アパッシュは強い絆で繋がっていくのです。
圧倒する大自然の美しさと脅威。
グリズリー(ハイイログマ)との遭遇シーン、クロクマの鮭狩り、トナカイの群れ、オオカミ、かわいらしいビーバー・・・・
ノーマンは言います。
「森の動物たちの中には、異常にその数を増やしているものがいる。そして、絶滅しようとしている動物もいる。
狩人が減っているからだ。
矛盾しているかもしれないが、人間の役割は、自然に手を入れてやることで調和を保つことなのだ」
おそらく、ボクが一生出会えない動物たちが、星野道夫さんが言うように、「今も、この瞬間も生きている」んですよね。
最近、『極北のトヨン』や、星野道夫さんのNHKドキュメンタリーを見たり、かなり気持ちが「北へ」向かっています。
この映画は、自らも冒険家であるフランスのニコラス・ヴァニエ監督のドキュメンタリー映画です。犬ぞりでシベリア横断8000キロ走破したり、カナダ北極圏8600キロ走破。
尋常ではありませんね。
このカナダ北極圏の冒険の際に、ノーマンと出会い、彼と彼の生活を映画にしたいと思ったのだそうです。
(06年のアカデミー賞ドキュメンタリー部門)
『かもめ食堂』は、ボクに癒しを、そして『狩人と犬、最後の旅』からは生きる勇気を与えられました。
ぜひみなさんも、目黒シネマで心を癒してみてください。
きょうは、のんびりいつものカフェで、と歩いていると、『かもめ食堂』の看板が。
以前から気になっていた映画だったので、ふらっと観てまいりました。
ヘルシンキの街中に、おにぎりをメインメニューにした「かもめ食堂」のお話です。
全編あったかーいエネルギーに包まれていて、大阪帰りのボクとしては、とても癒された時間でした。
開店したけれども、まったくお客が来ない「かもめ食堂」
それでも、まいにち、たんたんとお皿やコップを磨く女店主。
そこに、ようやく初めてのお客が・・・
それは、やたら日本かぶれの、おたくっぽいフィンランド青年。
おまけに、おかしな日本人女性が一人、また一人とまるで「かもめ食堂」に、ひきつけられるかのようにあらわれる。
コーヒーを美味しく入れるおまじないを教えてくれるオッサンやら、だんなに逃げられたおばさんも、入れ替わり立ち代りに登場します。
やがて、かもめ食堂は・・・・・・・
主役の小林聡美さんが、なんともステキでした。
ほんとにこころがあったまる作品です。
そして、更に時間もあったし、特に急ぎの用事も無かったために、二本目も観てしまったんですよ。
これが、だいだいだいだいだい感動でした。
『The Last Trapper(狩人と犬、最後の旅)』
極北の狩人ノーマン・ウィンター{実在の人物です}のお話です。
主人公は、ノーマン自らが演じて?います。
ドキュメントというわけではないけれども、演技をしている映画ってわけでもない。
秋のロッキー山脈 ユーコンの川をカヤックで下っている壮大なシーンから始まります。

ネイティブアメリカン ナハニ族のネブラスカという奥さんと、シベリアンハスキー犬7頭との、生活を描いた作品です。
「最後の狩人」といわれるほどに、狩をする民がほとんどいなくなっている。
その中でも、ネイティブたちでさえ、スノーモービルや、GPSを使って狩をしているのに、ノーマンはいまだにそりを犬に引かせて冬場の狩を続けているのです。
時折、町まで1週間ほどかけて出かけて、生活用品を調達したり、毛皮を売りにいったりする生活。
心の奥底から「あこがれてしまう生き方」
もちろん、到底軟弱なボクにできっこないですけどね。
この大自然の宝庫にも、「経済」は容赦なく立ち入り、森を伐採し、獣がすめなくなっている。
ノーマンは今年限りで、狩の生活を終え、ロッキーを去る決意をするのです。
最後の冬を、獣たちの生存する狩場で過ごすために、住まいを更に山の奥深くに移します。
あっという間に見事なキャビンを夫婦で建ててしまうんです。
愛するリーダー犬を、町で不慮の事故でなくし、代わりにハスキーの子犬をもらいます。
しかし、「そりを引く犬」ではないために、ノーマンは「ダメ犬」というレッテルをはるのです。
そんなある日、少し早く凍った氷原をそりで横断する際に、氷が割れて犬ともども凍てつく湖水にはまってしまいます。
驚いた犬たちは必死に脱出し、そのまま走り去ってしまうのです。ノーマンを湖の中に残したまま。
「ウォーク!!」とリーダー犬の名を呼ぶものの、パニックになった犬たちは走り続けます。
体温低下、崩れていく氷塊、麻痺していくからだ、空気に触れた瞬間に凍りつく服・・・そのときノーマンはダメ犬のアパッシュの名を呼びます。
アパッシュはその声を聞き、綱でつながれた群れを、もう一度ノーマンの元へ連れ戻すのです。

やっとの思いで命を救われたノーマンと、アパッシュは強い絆で繋がっていくのです。
圧倒する大自然の美しさと脅威。
グリズリー(ハイイログマ)との遭遇シーン、クロクマの鮭狩り、トナカイの群れ、オオカミ、かわいらしいビーバー・・・・
ノーマンは言います。
「森の動物たちの中には、異常にその数を増やしているものがいる。そして、絶滅しようとしている動物もいる。
狩人が減っているからだ。
矛盾しているかもしれないが、人間の役割は、自然に手を入れてやることで調和を保つことなのだ」
おそらく、ボクが一生出会えない動物たちが、星野道夫さんが言うように、「今も、この瞬間も生きている」んですよね。
最近、『極北のトヨン』や、星野道夫さんのNHKドキュメンタリーを見たり、かなり気持ちが「北へ」向かっています。
この映画は、自らも冒険家であるフランスのニコラス・ヴァニエ監督のドキュメンタリー映画です。犬ぞりでシベリア横断8000キロ走破したり、カナダ北極圏8600キロ走破。
尋常ではありませんね。
このカナダ北極圏の冒険の際に、ノーマンと出会い、彼と彼の生活を映画にしたいと思ったのだそうです。
(06年のアカデミー賞ドキュメンタリー部門)
『かもめ食堂』は、ボクに癒しを、そして『狩人と犬、最後の旅』からは生きる勇気を与えられました。
ぜひみなさんも、目黒シネマで心を癒してみてください。













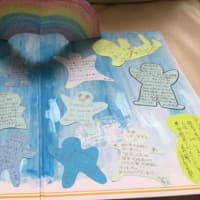



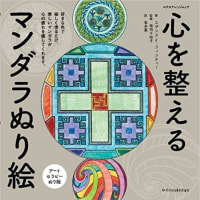
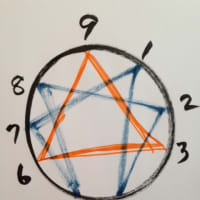

かもめ食堂は俺も好き~!
うん。あれは面白い(笑)
あの 途切れず流れている
プラスの雰囲気がほっとします。