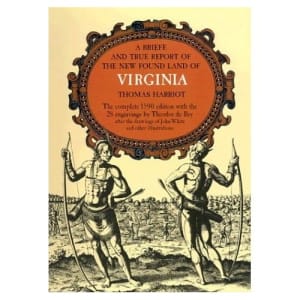白妙菊を書くために調べていたら、自分に大きな誤解があったことに気づいた。
そして、キクの歴史は意外なことがけっこうある。
春のウメ、サクラに対して秋のキクというのが日本の季節感をあらわす代表的な花で、
3種とも日本固有の植物かと思っていたが、そうではなかった。

※キク科の花 ダイヤーズカモマイル
1.キクには、野生種が存在しない
現在のキクは、5~6世紀の頃の中国で自然交配で出来た園芸種のようだ。
親は、白花のチョウセンノギク (※1) と 黄花のハイシマカンギク (※2)が交配してできたと
推定されている。
文献では、 シマカンギク (※3)或いはハイシマカンギクとあり正解はわからない。
だから現在のキクには原種というものがなく、両親がいるだけだ。
この両親から生まれた第一子が原種と言えば原種だが・・・・(答えは最後に)
2.日本には、奈良時代中期から平安時代初めに中国から伝わる。
このときに、奇数の数字が重なる日はおめでたく5節句というものも一緒に伝わる。
1月7日(人日、じんじつ、七草)、3月3日(上巳、じょうし、桃の節句)、
5月5日(端午、たんご、菖蒲の節句)、7月7日(七夕、しちせき)、そして、
旧暦での9月9日は、重陽(ちょうよう)の節句で
キクの花びらを浮かべた菊酒を飲むと長寿ができるという不老長寿の薬として伝わり、
貴族階級では、ブームとなったようだ。
また、キクを見て楽しむという“鑑賞の習慣”は、このときに中国から伝わってきた。
ヨーロッパでは、花の観賞という美意識が育つのが15世紀以降であり、
それ以前に日本では鑑賞の価値を習慣化していたようだ。これも意外かな?
ウメも8世紀半ばに原産国中国から伝わってきているので、キクと同じ頃に日本に入ってきた。
ということは、現在のウメ、キクのおおもとは中国だったということになる。
3.花といえば、平安以前はウメ、平安からサクラ。キクは鎌倉時代から
秋を代表する花としてキクが確立したのは、鎌倉時代の初め後鳥羽上皇(1180-1239)が
菊の花の意匠を好み、「菊紋」を天皇家家紋とした頃から。
日本を代表する花にもこのように時代差があったのだ。これも意外。
4.「菊」は漢名で、「菊」が残る
平安時代の辞書「和名類聚抄(わみょうるいじゅしょう)」では、漢名の菊に対して
和名は「カハラヨモギ」または「カハラオハギ」としている。
これは別に意外ではないか!
5.中国産の「菊」は、日本で独自に品種改良され世界に誇る園芸品種となる。
江戸元禄時代以降に園芸品種としての菊の改良が特に進み、直径30cmにならんとする大輪菊が栽培された。
この時代植木屋が集まっていた巣鴨から染井(ソメイヨシノの染井=駒込)が
園芸種栽培の中心で、開国後にここを訪れた外国人は園芸水準の高さに驚いたようだ。
6.プラントハンター、フォーチュンもびっくり
イギリスのプラントハンター、フォーチュン(R.Fortune 1812-1880)(※5)は、
1860年及び1861年に再来日し、キクの品種を大量に集めロンドンに送った。
フォーチュンの驚きは、
江戸の団子坂で菊人形にふれ、翌日は染井、王子の植木村を訪問しているが、
この植木村(ナーサリー・種苗園)の規模の大きさは、ロンドンをも上回り、
彼をして
“世界のどこに行ってもこんなに規模の大きな売り物の植物を栽培しているのを見たことがない”
と言わしめている。
江戸末期の日本の園芸市場は世界最高水準であり、これを支える花・植物を愛する日本人が多数いた。
ということがフォーチュンの驚きだった。
中国のキクの品種は、日本のものよりは早い1789年にヨーロッパに入っていたが(※4)
単純な八重咲きのためか、人気にもならなかった。
フォーチュンにより日本種が入り交配されることによりヨーロッパでもキクブームが起こった。
いまでは、バラ、カーネーション、キクが世界での三大花となるまで成長した。
井伊直弼が暗殺されたのが1860年であり、尊皇攘夷で荒れていた時期に、
フォーチュンが王子まで動き廻っていたことも驚きだ。プラントハンターは命がけだ。
7.蛇足
「以ての外(もってのほか)」は、 ”思いもよらない”という意味で使われるが
これが“もってのほか”だった。
子供の頃は秋になると菊の酢の物など食べたものだ。
山形の菊が入った漬物“晩菊”は、お茶漬けにすると最高だが、
「もってのほか」は東北地方で栽培される食用菊の名前だった。
この由来は、狩に出かけたお殿様が、百姓屋で振舞われたお茶うけの菊びたしに
「これはうまい。百姓にはもってのほか」といったそうだが
それにしてもひどい逸話で、 “もってのほか”という以外ない。
8.蛇足2
現在のキクの親は園芸種で雑種であることがわかった。
野生のキク科の植物もあり、これが死滅する可能性があるそうだ。
何故かといえば、
キクの園芸種は、野生種と交配し新しい種が誕生しやすい遺伝子構造を持っているようだ。
この雑種が誕生する原因として挙げられているのは、
野原などに自生する野生種に、墓参りでもって行ったキクの花の花粉が交配するからのようだ。
野生種を守るには、お墓にキクの花を持っていかないか、お墓を地代の安いところに作らせないか
野生種を空調設備が管理できる実験室に移植するかなどなど奇策があるが
とんでもないことを考えざるを得ないようだ。
“もってのほか”といいたい・・・・

※ キク科の花 ローマンカモマイル
<脚 注>
(※1)チョウセンノギク(出典:'Botanic Garden')
チョウセンノギク(Dendrantbema zawadskii var. latilobum kitamura)は、
中国北部、モンゴル低地、朝鮮半島などに自生する頭花の直径が8㎝にもなる大きな白い花を咲かせる。
http://www.botanic.jp/plants-ta/chonog.htm
(※2)ハイシマカンギク(出典:独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 花き研究所)
ハイシマカンギク(D.indicum var. procumbens Nakai)は、中国中部に広く分布し、茎は地上をはって長くなりところどころで根を出すので匍匐性がある。鮮やかな黄色の花をつける。中国では、薬用で漢名では甘菊という。
http://flower.naro.affrc.go.jp/kaki_iden/c3_kiku/kiku_yasei_show/detail_html/00030.html
(※3)シマカンギク(出典:'Botanic Garden')
シマカンギクDendrantbema indicumは、草丈30~80㎝で、黄色の直径2.5cmの頭花をつけ、近畿以西の本州、四国、九州、台湾、朝鮮半島、中国、ベトナム北部までに分布する。
http://www.botanic.jp/plants-sa/sikang.htm
(※4)中国からキクを持っていったヒト
1789年フランス人ブランカール(P.L.Blancard)は、中国から大輪菊を持ち帰り、これがイギリスキュー植物園に伝えられ、オールドパープルの名で栽培される。
(※5)フォーチュン(R.Fortune 1812-1880)は、
1843年に中国からポンポン咲きの品種を、1861年には中国と日本から新しい大輪厚物品種をイギリスに送る。
ちなみにフォーチュンの経歴は、
ロンドンの園芸協会のプラントハンターとして1843年7月に香港に派遣され、
茶の木、製法、マニラでのランの収集などで知られる。
そして、発酵させて作る紅茶の製法と茶の栽培法をインドに持ちこみ、紅茶大国イギリスの基礎をつくった。
そして、キクの歴史は意外なことがけっこうある。
春のウメ、サクラに対して秋のキクというのが日本の季節感をあらわす代表的な花で、
3種とも日本固有の植物かと思っていたが、そうではなかった。

※キク科の花 ダイヤーズカモマイル
1.キクには、野生種が存在しない
現在のキクは、5~6世紀の頃の中国で自然交配で出来た園芸種のようだ。
親は、白花のチョウセンノギク (※1) と 黄花のハイシマカンギク (※2)が交配してできたと
推定されている。
文献では、 シマカンギク (※3)或いはハイシマカンギクとあり正解はわからない。
だから現在のキクには原種というものがなく、両親がいるだけだ。
この両親から生まれた第一子が原種と言えば原種だが・・・・(答えは最後に)
2.日本には、奈良時代中期から平安時代初めに中国から伝わる。
このときに、奇数の数字が重なる日はおめでたく5節句というものも一緒に伝わる。
1月7日(人日、じんじつ、七草)、3月3日(上巳、じょうし、桃の節句)、
5月5日(端午、たんご、菖蒲の節句)、7月7日(七夕、しちせき)、そして、
旧暦での9月9日は、重陽(ちょうよう)の節句で
キクの花びらを浮かべた菊酒を飲むと長寿ができるという不老長寿の薬として伝わり、
貴族階級では、ブームとなったようだ。
また、キクを見て楽しむという“鑑賞の習慣”は、このときに中国から伝わってきた。
ヨーロッパでは、花の観賞という美意識が育つのが15世紀以降であり、
それ以前に日本では鑑賞の価値を習慣化していたようだ。これも意外かな?
ウメも8世紀半ばに原産国中国から伝わってきているので、キクと同じ頃に日本に入ってきた。
ということは、現在のウメ、キクのおおもとは中国だったということになる。
3.花といえば、平安以前はウメ、平安からサクラ。キクは鎌倉時代から
秋を代表する花としてキクが確立したのは、鎌倉時代の初め後鳥羽上皇(1180-1239)が
菊の花の意匠を好み、「菊紋」を天皇家家紋とした頃から。
日本を代表する花にもこのように時代差があったのだ。これも意外。
4.「菊」は漢名で、「菊」が残る
平安時代の辞書「和名類聚抄(わみょうるいじゅしょう)」では、漢名の菊に対して
和名は「カハラヨモギ」または「カハラオハギ」としている。
これは別に意外ではないか!
5.中国産の「菊」は、日本で独自に品種改良され世界に誇る園芸品種となる。
江戸元禄時代以降に園芸品種としての菊の改良が特に進み、直径30cmにならんとする大輪菊が栽培された。
この時代植木屋が集まっていた巣鴨から染井(ソメイヨシノの染井=駒込)が
園芸種栽培の中心で、開国後にここを訪れた外国人は園芸水準の高さに驚いたようだ。
6.プラントハンター、フォーチュンもびっくり
イギリスのプラントハンター、フォーチュン(R.Fortune 1812-1880)(※5)は、
1860年及び1861年に再来日し、キクの品種を大量に集めロンドンに送った。
フォーチュンの驚きは、
江戸の団子坂で菊人形にふれ、翌日は染井、王子の植木村を訪問しているが、
この植木村(ナーサリー・種苗園)の規模の大きさは、ロンドンをも上回り、
彼をして
“世界のどこに行ってもこんなに規模の大きな売り物の植物を栽培しているのを見たことがない”
と言わしめている。
江戸末期の日本の園芸市場は世界最高水準であり、これを支える花・植物を愛する日本人が多数いた。
ということがフォーチュンの驚きだった。
中国のキクの品種は、日本のものよりは早い1789年にヨーロッパに入っていたが(※4)
単純な八重咲きのためか、人気にもならなかった。
フォーチュンにより日本種が入り交配されることによりヨーロッパでもキクブームが起こった。
いまでは、バラ、カーネーション、キクが世界での三大花となるまで成長した。
井伊直弼が暗殺されたのが1860年であり、尊皇攘夷で荒れていた時期に、
フォーチュンが王子まで動き廻っていたことも驚きだ。プラントハンターは命がけだ。
7.蛇足
「以ての外(もってのほか)」は、 ”思いもよらない”という意味で使われるが
これが“もってのほか”だった。
子供の頃は秋になると菊の酢の物など食べたものだ。
山形の菊が入った漬物“晩菊”は、お茶漬けにすると最高だが、
「もってのほか」は東北地方で栽培される食用菊の名前だった。
この由来は、狩に出かけたお殿様が、百姓屋で振舞われたお茶うけの菊びたしに
「これはうまい。百姓にはもってのほか」といったそうだが
それにしてもひどい逸話で、 “もってのほか”という以外ない。
8.蛇足2
現在のキクの親は園芸種で雑種であることがわかった。
野生のキク科の植物もあり、これが死滅する可能性があるそうだ。
何故かといえば、
キクの園芸種は、野生種と交配し新しい種が誕生しやすい遺伝子構造を持っているようだ。
この雑種が誕生する原因として挙げられているのは、
野原などに自生する野生種に、墓参りでもって行ったキクの花の花粉が交配するからのようだ。
野生種を守るには、お墓にキクの花を持っていかないか、お墓を地代の安いところに作らせないか
野生種を空調設備が管理できる実験室に移植するかなどなど奇策があるが
とんでもないことを考えざるを得ないようだ。
“もってのほか”といいたい・・・・

※ キク科の花 ローマンカモマイル
<脚 注>
(※1)チョウセンノギク(出典:'Botanic Garden')
チョウセンノギク(Dendrantbema zawadskii var. latilobum kitamura)は、
中国北部、モンゴル低地、朝鮮半島などに自生する頭花の直径が8㎝にもなる大きな白い花を咲かせる。
http://www.botanic.jp/plants-ta/chonog.htm
(※2)ハイシマカンギク(出典:独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 花き研究所)
ハイシマカンギク(D.indicum var. procumbens Nakai)は、中国中部に広く分布し、茎は地上をはって長くなりところどころで根を出すので匍匐性がある。鮮やかな黄色の花をつける。中国では、薬用で漢名では甘菊という。
http://flower.naro.affrc.go.jp/kaki_iden/c3_kiku/kiku_yasei_show/detail_html/00030.html
(※3)シマカンギク(出典:'Botanic Garden')
シマカンギクDendrantbema indicumは、草丈30~80㎝で、黄色の直径2.5cmの頭花をつけ、近畿以西の本州、四国、九州、台湾、朝鮮半島、中国、ベトナム北部までに分布する。
http://www.botanic.jp/plants-sa/sikang.htm
(※4)中国からキクを持っていったヒト
1789年フランス人ブランカール(P.L.Blancard)は、中国から大輪菊を持ち帰り、これがイギリスキュー植物園に伝えられ、オールドパープルの名で栽培される。
(※5)フォーチュン(R.Fortune 1812-1880)は、
1843年に中国からポンポン咲きの品種を、1861年には中国と日本から新しい大輪厚物品種をイギリスに送る。
ちなみにフォーチュンの経歴は、
ロンドンの園芸協会のプラントハンターとして1843年7月に香港に派遣され、
茶の木、製法、マニラでのランの収集などで知られる。
そして、発酵させて作る紅茶の製法と茶の栽培法をインドに持ちこみ、紅茶大国イギリスの基礎をつくった。