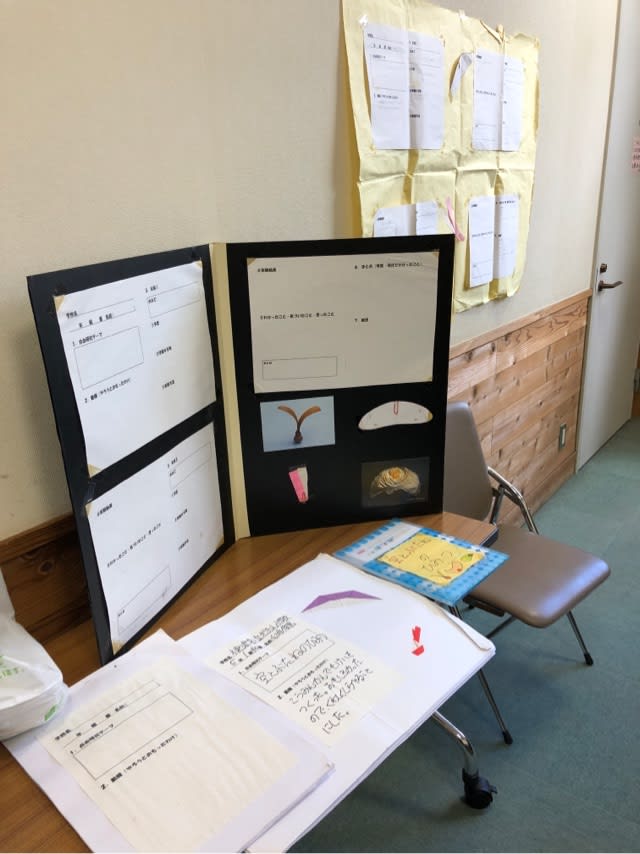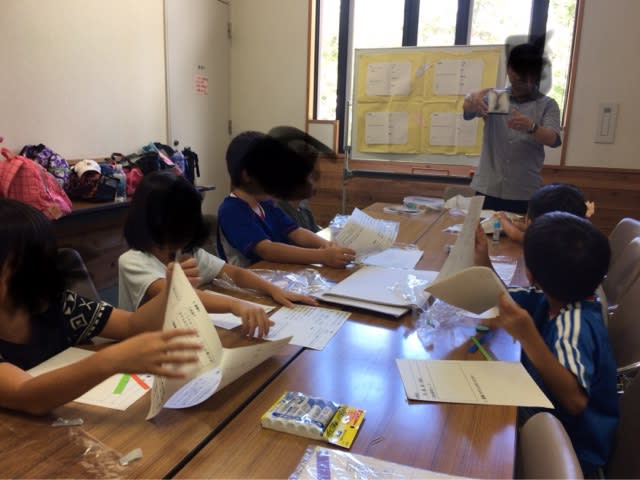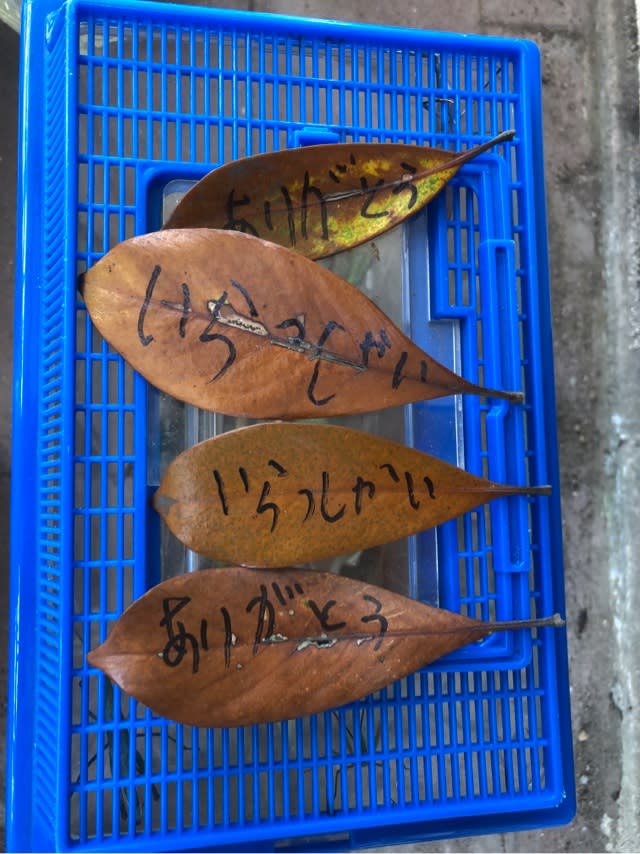教師になって間もない頃、長欠の子を受け持った。どうしていいか分からず、欠席の放課後、必ず家庭訪問した。
最初は、母親しか出てこなかった。そのうち、その子が出てきて話ようになり、そして庭でバトミントンで一緒に遊ぶようになった。
次の日から学校を休まなくなり、僕がその学校去った後も、「休まず学校に行っています」と言う手紙をくれた。
ある学校で2年ほど前から不登校の子を受け持った。2、3日おきに家庭訪問をした。
初めは門前払い。しかし、母親が出てくるようになり、子どもも庭で遊ぶようになり、やがて家の中に入れた。その子は自分の部屋まで僕を招き、いろいろな話をしてくれた。
その年は1月から3月までしかその学校にいなかった。驚いたことにその不登校の子は、4月になってから学校に来るようになり、中学校は休まず登校したと言う。
また別の学校。6年生の不登校の女子を受け持った。3年生の頃から、学校に来ていなかった。やはり家庭訪問をし、そして電話をかけ続けた。
最初のうちは、居留守を使われたが、少しずつ母親は打ち解けて行き、その子とも玄関先で話せるようになった。
11月にマラソン大会があり、前日にその子から電話がきた。たまたま職員室に来たクラスの女子に変わると、強引にその子にマラソン大会の応援に来るよう誘った。
翌日、その子はマラソン大会に現れ、そのまま学校で過ごした。
そして、次の日からその子は普通に登校し始めたのだ。
全てに共通する事は、何度も何度も家庭訪問をしたことである。最初は門前門前払いをされる。しかしだんだんと打ち解けていき、やがて家の扉を開けてくれ、その子たちに会うことができ、そして信頼してもらえると、その子たちは学校に来るようになる。
まるで三国志の劉備玄徳が諸葛亮孔明を向かい入れるための三顧の礼のようなものだ。しかし不登校の場合は3回で済むと言うわけではない。
相手が心を開くまで何度でも何度でも心が折れそうになっても何度でも何度でも家庭訪問をすることが秘訣である。

最初は、母親しか出てこなかった。そのうち、その子が出てきて話ようになり、そして庭でバトミントンで一緒に遊ぶようになった。
次の日から学校を休まなくなり、僕がその学校去った後も、「休まず学校に行っています」と言う手紙をくれた。
ある学校で2年ほど前から不登校の子を受け持った。2、3日おきに家庭訪問をした。
初めは門前払い。しかし、母親が出てくるようになり、子どもも庭で遊ぶようになり、やがて家の中に入れた。その子は自分の部屋まで僕を招き、いろいろな話をしてくれた。
その年は1月から3月までしかその学校にいなかった。驚いたことにその不登校の子は、4月になってから学校に来るようになり、中学校は休まず登校したと言う。
また別の学校。6年生の不登校の女子を受け持った。3年生の頃から、学校に来ていなかった。やはり家庭訪問をし、そして電話をかけ続けた。
最初のうちは、居留守を使われたが、少しずつ母親は打ち解けて行き、その子とも玄関先で話せるようになった。
11月にマラソン大会があり、前日にその子から電話がきた。たまたま職員室に来たクラスの女子に変わると、強引にその子にマラソン大会の応援に来るよう誘った。
翌日、その子はマラソン大会に現れ、そのまま学校で過ごした。
そして、次の日からその子は普通に登校し始めたのだ。
全てに共通する事は、何度も何度も家庭訪問をしたことである。最初は門前門前払いをされる。しかしだんだんと打ち解けていき、やがて家の扉を開けてくれ、その子たちに会うことができ、そして信頼してもらえると、その子たちは学校に来るようになる。
まるで三国志の劉備玄徳が諸葛亮孔明を向かい入れるための三顧の礼のようなものだ。しかし不登校の場合は3回で済むと言うわけではない。
相手が心を開くまで何度でも何度でも心が折れそうになっても何度でも何度でも家庭訪問をすることが秘訣である。