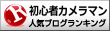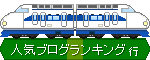今朝の信州は、気温が3度、霜が降りるギリギリの気温
もう果樹の受粉やブドウの樹も若芽に花が付いてきてい
ます。霜だけは御免被りたい。天気は快晴です。
昨日に続いて小野の御柱祭りについて、今日は後半をお
知らせします。午後1時ころからの神社境内の写真です
その前に・・この御柱の蘊蓄をWikで調べてみました。
この御柱の起源は、平安時代以前とされる、諏訪大社の
祭神に限らずこの信州の中南信の祭神はみな、五穀豊穣
狩猟・風・水・農耕の神として古くから信仰されていて
それらを祈願するものであったと推測される。江戸時代
以降は、宝殿いては様々な伝承が伝わっている。
『古事記』によると出雲の大国主神が高天原の天照大御
神の使者達に国譲りを承諾したとき、ただ一柱反対した
建御名方神は使者であった武神建御雷神に挑むも敗れて
追われることとなり、結局諏訪湖畔まで逃げてきて降伏
し、その際この地から出ないことを誓って許された。
一方、諏訪地域や信州の中南信地方では建御名方神が
『古事記』の描写とは逆で、諏訪に侵入して洩矢神をは
じめ先住の神々を降伏させた立派な神とされている。
伝承によると、征夷大将軍に任じられた坂上田村麻呂が
蝦夷征討の際に諏訪社に戦勝祈願をすると、諏訪明神が
騎馬武者の姿をとり軍勢を先導した。田村麻呂の帰京後
朝廷が神恩感謝のため信濃国全体に諏訪社の式年造営へ
の奉仕を命じたという。とWikの解説でした。
小野神社の御朱印

境内では弥彦神社の御柱と小野神社の御柱が同時並行
してその神社取り込み作業が行われていて、あっちを
撮ったりこっちを撮ったりこの日のうちに各社の四隅
に建てられる御柱の殆どが所定の位置に鎮座して弥彦
神社は5日の日に四本が建てられる、小野神社は三日
に一本、四日二本、最後五日に一本が建てられる。






塩尻の小野神社の御柱が午後になって入って来ました




境内の坂を力を合わせて引き上げていきます


漸く所定の位置に着きました。



宮司のお祓いを受け 祝詞を頭を下げて聞いて
いよいよ、建御柱に入ります。ここまで引っ張って
きた御柱の頭と尻尾(失礼)上の部分と下の部分を切っ
て決められた長さピッタリに合わせます。その時の
切り口を撮らせてもらいましたが・・この松の年輪
75まで数えましたが、たぶん80位と思われます。





安全に、御柱を飾り付けます





いよいよ立てる御柱に乗り手の11人が所定の位置
について、木遣うたによって少しずつ建てられてい
きます。





ほぼ垂直に建てられて・・安全に養生をして
倒れないようにしながら完成です。





以上で小野神社の建御柱を終わりますが、こんな小さ
な部落でも老若男女がみんな力を合わせて造営の柱を
建てるべく御柱祭りを遂行する素晴らしい祭りをみせ
ていただき、元気を頂いてきました。小野神社の氏子
の皆さん、弥彦神社の氏子の皆さんたいへんご苦労様
でした。素晴らしい祭りを見せていただきました。
ありがとうございました。
もう果樹の受粉やブドウの樹も若芽に花が付いてきてい
ます。霜だけは御免被りたい。天気は快晴です。
昨日に続いて小野の御柱祭りについて、今日は後半をお
知らせします。午後1時ころからの神社境内の写真です
その前に・・この御柱の蘊蓄をWikで調べてみました。
この御柱の起源は、平安時代以前とされる、諏訪大社の
祭神に限らずこの信州の中南信の祭神はみな、五穀豊穣
狩猟・風・水・農耕の神として古くから信仰されていて
それらを祈願するものであったと推測される。江戸時代
以降は、宝殿いては様々な伝承が伝わっている。
『古事記』によると出雲の大国主神が高天原の天照大御
神の使者達に国譲りを承諾したとき、ただ一柱反対した
建御名方神は使者であった武神建御雷神に挑むも敗れて
追われることとなり、結局諏訪湖畔まで逃げてきて降伏
し、その際この地から出ないことを誓って許された。
一方、諏訪地域や信州の中南信地方では建御名方神が
『古事記』の描写とは逆で、諏訪に侵入して洩矢神をは
じめ先住の神々を降伏させた立派な神とされている。
伝承によると、征夷大将軍に任じられた坂上田村麻呂が
蝦夷征討の際に諏訪社に戦勝祈願をすると、諏訪明神が
騎馬武者の姿をとり軍勢を先導した。田村麻呂の帰京後
朝廷が神恩感謝のため信濃国全体に諏訪社の式年造営へ
の奉仕を命じたという。とWikの解説でした。
小野神社の御朱印

境内では弥彦神社の御柱と小野神社の御柱が同時並行
してその神社取り込み作業が行われていて、あっちを
撮ったりこっちを撮ったりこの日のうちに各社の四隅
に建てられる御柱の殆どが所定の位置に鎮座して弥彦
神社は5日の日に四本が建てられる、小野神社は三日
に一本、四日二本、最後五日に一本が建てられる。






塩尻の小野神社の御柱が午後になって入って来ました




境内の坂を力を合わせて引き上げていきます


漸く所定の位置に着きました。



宮司のお祓いを受け 祝詞を頭を下げて聞いて
いよいよ、建御柱に入ります。ここまで引っ張って
きた御柱の頭と尻尾(失礼)上の部分と下の部分を切っ
て決められた長さピッタリに合わせます。その時の
切り口を撮らせてもらいましたが・・この松の年輪
75まで数えましたが、たぶん80位と思われます。





安全に、御柱を飾り付けます





いよいよ立てる御柱に乗り手の11人が所定の位置
について、木遣うたによって少しずつ建てられてい
きます。





ほぼ垂直に建てられて・・安全に養生をして
倒れないようにしながら完成です。





以上で小野神社の建御柱を終わりますが、こんな小さ
な部落でも老若男女がみんな力を合わせて造営の柱を
建てるべく御柱祭りを遂行する素晴らしい祭りをみせ
ていただき、元気を頂いてきました。小野神社の氏子
の皆さん、弥彦神社の氏子の皆さんたいへんご苦労様
でした。素晴らしい祭りを見せていただきました。
ありがとうございました。