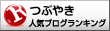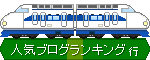今朝の信州は、気温が9度で寒い朝です。慌てて一枚重ね
着でストーブを点けて凌いでいます。
昨日市内の、平沢地区の漆器屋さんにお届け物があって
そこで朴葉巻きを頂きました。木曽路はすべて山の中で
ある。と島崎藤村によってそう謳われた山深い木曽地域
は我が町の贄川地区の「これより南木曽路」の石碑から
南の地域を木曽と呼んでいます。その山深い木曽の谷間
では、5月から7月にかけての、季節限定で「朴葉巻き」
(ほおばまき)がつくられています。その朴葉巻きとは
米粉を練ってつくった餅にあんを包んで朴葉でつつんで
い草で縛って蒸しあげたもの。朴葉の香りが餅に移って
新緑の季節らしい清々しい味わいが特徴です。
なぜ季節限定かと言えば、餅が包みやすい柔らかな若葉
の朴葉を収穫できるのがこの季節だからです。朴葉巻き
は木曽地域の各家庭でつくられ受け継がれてきた伝統の
味。木曽の人たちは「小さい頃、家に帰ると蒸し上がっ
た朴葉巻きが物干しにぶら下がっていて、大人も子供も
格好のおやつでした。現在は、木曽地域の和菓子店など
で製造されています。米粉らしい、粘り気のあるむっち
りとした餅のなかに包むあんは、つぶあん、こしあん、
白みそくるみあんが定番ですが、なかでもめずらしいの
は白味噌胡桃餡。お店によっては、柚子あんなどの変わ
り種もあるようです。もともとは、柏餅の代わりとして
食べられていたのかもしれませんね~柏の木がない木曽
地方では柏の葉の代わりに朴葉を使うようになったよう
です。朴葉巻きの大きな特徴は、ひと枝に複数枚の葉が
ついた状態で餅を包むところが特徴です。朴の木はモク
レン科の樹木で、高さは15m以上、なかには30mになる
ものもあるという高木です。そのため庭木というより山
中の木というイメージですが、木曽地域では、家庭の庭
木にする家もあったようです。ひと枝に5~8枚程度つけ
る葉の1枚1枚もとても大きくて、長さ30cm以上になる
ものもあり、餅をくるむのにも十分。朴葉を用いるのは
大きさのほか、アクが強くて殺菌力が高いため。保存性
が高く、かつてはお米を包んで蒸した朴葉飯を山仕事や
農作業のお弁当として携えたそうです。
そんな朴葉巻き、今年の初物を頂いて元気を頂いてきま
した。写真を撮れませんでしたので、木曽福島の田ぐち
さんの写真をお借りしました。

信州の葡萄も新芽か元気に育ってきましたよ~










着でストーブを点けて凌いでいます。
昨日市内の、平沢地区の漆器屋さんにお届け物があって
そこで朴葉巻きを頂きました。木曽路はすべて山の中で
ある。と島崎藤村によってそう謳われた山深い木曽地域
は我が町の贄川地区の「これより南木曽路」の石碑から
南の地域を木曽と呼んでいます。その山深い木曽の谷間
では、5月から7月にかけての、季節限定で「朴葉巻き」
(ほおばまき)がつくられています。その朴葉巻きとは
米粉を練ってつくった餅にあんを包んで朴葉でつつんで
い草で縛って蒸しあげたもの。朴葉の香りが餅に移って
新緑の季節らしい清々しい味わいが特徴です。
なぜ季節限定かと言えば、餅が包みやすい柔らかな若葉
の朴葉を収穫できるのがこの季節だからです。朴葉巻き
は木曽地域の各家庭でつくられ受け継がれてきた伝統の
味。木曽の人たちは「小さい頃、家に帰ると蒸し上がっ
た朴葉巻きが物干しにぶら下がっていて、大人も子供も
格好のおやつでした。現在は、木曽地域の和菓子店など
で製造されています。米粉らしい、粘り気のあるむっち
りとした餅のなかに包むあんは、つぶあん、こしあん、
白みそくるみあんが定番ですが、なかでもめずらしいの
は白味噌胡桃餡。お店によっては、柚子あんなどの変わ
り種もあるようです。もともとは、柏餅の代わりとして
食べられていたのかもしれませんね~柏の木がない木曽
地方では柏の葉の代わりに朴葉を使うようになったよう
です。朴葉巻きの大きな特徴は、ひと枝に複数枚の葉が
ついた状態で餅を包むところが特徴です。朴の木はモク
レン科の樹木で、高さは15m以上、なかには30mになる
ものもあるという高木です。そのため庭木というより山
中の木というイメージですが、木曽地域では、家庭の庭
木にする家もあったようです。ひと枝に5~8枚程度つけ
る葉の1枚1枚もとても大きくて、長さ30cm以上になる
ものもあり、餅をくるむのにも十分。朴葉を用いるのは
大きさのほか、アクが強くて殺菌力が高いため。保存性
が高く、かつてはお米を包んで蒸した朴葉飯を山仕事や
農作業のお弁当として携えたそうです。
そんな朴葉巻き、今年の初物を頂いて元気を頂いてきま
した。写真を撮れませんでしたので、木曽福島の田ぐち
さんの写真をお借りしました。

信州の葡萄も新芽か元気に育ってきましたよ~