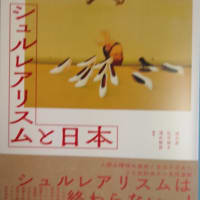ルーフガーデンにあるミカンの木にまた7匹のアゲハチョウの幼虫がいた。そこで、昨日は保護のためにと思って、ミカンの鉢を北の部屋に入れ、鉢の下に新聞紙を敷き、見守ることにした。夜、私がパソコンに向かっていると、バサッという音がした。ちょっと気になったが、まだ緑色の幼虫になって2日間ほどしか経ていないから、あの幼虫がサナギになるためにはまだもう少し時間が必要なはずだと思った。
ところがしばらくして、見に行くと3から4センチほどになっていた緑色の幼虫が2匹、いくら探してもいない。やはり、サナギになるためにミカンの木を離れたのだ。インターネットで調べてみると、アゲハチョウの幼虫はサナギになる時には、木から離れて他に移ると書いてある。そうか、前の時も幼虫が床に落ちてきた。あの時はすぐに拾い上げ、再びミカンの木に戻してやったけれど、今回はまだまだ先だと油断していた。
先回の時に比べると、今回のミカンの木は葉の数が少ない。それも若い新しい葉が少ない。まだ小さな幼虫も含めて、7匹が食べていくには足りないなと思った。それを緑色の幼虫も感じていたのだろうか。これから先もしっかり食べて大きくならなければならないのに、このままではダメだと感じたのか、先に大きくなっていた緑色の2匹の幼虫が先を争うように、ミカンの木を離れたのだ。申し訳ない気がして、周りを探しまわったが見つからなかった。
今朝、カミさんが「窓の枠のカーテンのところにサナギがあるわよ」と言う。確かにサナギがへばりついている。まだ、幼虫に近い形をしているから、ここに来て間がないのだろう。それにしても、ミカンの鉢から2メートル以上は離れているし、しかも床から90センチはある壁を這い上がって、どうしてこの縁でサナギになろうとしたのだろうか。とにかく、1匹は見つかったがもう1匹はどこへ行ってしまったのか、未だにわからない。1匹だけでも無事が確認できたのだからと思うものの、あとの1匹の行方が気にかかる。
アゲハチョウは、サナギになる時は木から離れることはハッキリした。いつもたくさんの幼虫がミカンの木に見られるのに、いつの間にかいなくなることが不思議でならなかった。鳥が来て食べてしまうのだろうか、それとも他の昆虫が来て食べるのか邪魔をするのだろうかと、ズーと考えてきた。どうやらアゲハチョウは幼虫からサナギになる段階で、ミカンの木から離れ、その時に他の昆虫か鳥でも食べられてしまうかもしれないが、何匹かは近くのどこかでサナギになる。その時期が遅ければ、一冬越さなくてはならないし、越冬できたからといって羽化できるとは限らない運命だ。
自然の仕組みはよくできているなと思う。中学高校時代からの友人が、差し上げた本を送り返してきた。もし、手紙が入っていなかったら文句を言ってやろうと思っていたが、キチンと手紙が入っていた。「納得はできなくても、気品有る生き方 ノブレス・オブリージュ(高貴なる者の宿命)という努力する生き方をしたいと思っています」と書いてあった。衝撃だった。昨日の映画『ショート・バス』は最後に「人は人生の最後で、心の中の悪魔が親友だと知る」と歌っていた。翌日の今日、私の友人はこれを完全に否定している。えらいヤツだなと敬意を覚え、みだらな自分を恥じ入った。
ところがしばらくして、見に行くと3から4センチほどになっていた緑色の幼虫が2匹、いくら探してもいない。やはり、サナギになるためにミカンの木を離れたのだ。インターネットで調べてみると、アゲハチョウの幼虫はサナギになる時には、木から離れて他に移ると書いてある。そうか、前の時も幼虫が床に落ちてきた。あの時はすぐに拾い上げ、再びミカンの木に戻してやったけれど、今回はまだまだ先だと油断していた。
先回の時に比べると、今回のミカンの木は葉の数が少ない。それも若い新しい葉が少ない。まだ小さな幼虫も含めて、7匹が食べていくには足りないなと思った。それを緑色の幼虫も感じていたのだろうか。これから先もしっかり食べて大きくならなければならないのに、このままではダメだと感じたのか、先に大きくなっていた緑色の2匹の幼虫が先を争うように、ミカンの木を離れたのだ。申し訳ない気がして、周りを探しまわったが見つからなかった。
今朝、カミさんが「窓の枠のカーテンのところにサナギがあるわよ」と言う。確かにサナギがへばりついている。まだ、幼虫に近い形をしているから、ここに来て間がないのだろう。それにしても、ミカンの鉢から2メートル以上は離れているし、しかも床から90センチはある壁を這い上がって、どうしてこの縁でサナギになろうとしたのだろうか。とにかく、1匹は見つかったがもう1匹はどこへ行ってしまったのか、未だにわからない。1匹だけでも無事が確認できたのだからと思うものの、あとの1匹の行方が気にかかる。
アゲハチョウは、サナギになる時は木から離れることはハッキリした。いつもたくさんの幼虫がミカンの木に見られるのに、いつの間にかいなくなることが不思議でならなかった。鳥が来て食べてしまうのだろうか、それとも他の昆虫が来て食べるのか邪魔をするのだろうかと、ズーと考えてきた。どうやらアゲハチョウは幼虫からサナギになる段階で、ミカンの木から離れ、その時に他の昆虫か鳥でも食べられてしまうかもしれないが、何匹かは近くのどこかでサナギになる。その時期が遅ければ、一冬越さなくてはならないし、越冬できたからといって羽化できるとは限らない運命だ。
自然の仕組みはよくできているなと思う。中学高校時代からの友人が、差し上げた本を送り返してきた。もし、手紙が入っていなかったら文句を言ってやろうと思っていたが、キチンと手紙が入っていた。「納得はできなくても、気品有る生き方 ノブレス・オブリージュ(高貴なる者の宿命)という努力する生き方をしたいと思っています」と書いてあった。衝撃だった。昨日の映画『ショート・バス』は最後に「人は人生の最後で、心の中の悪魔が親友だと知る」と歌っていた。翌日の今日、私の友人はこれを完全に否定している。えらいヤツだなと敬意を覚え、みだらな自分を恥じ入った。