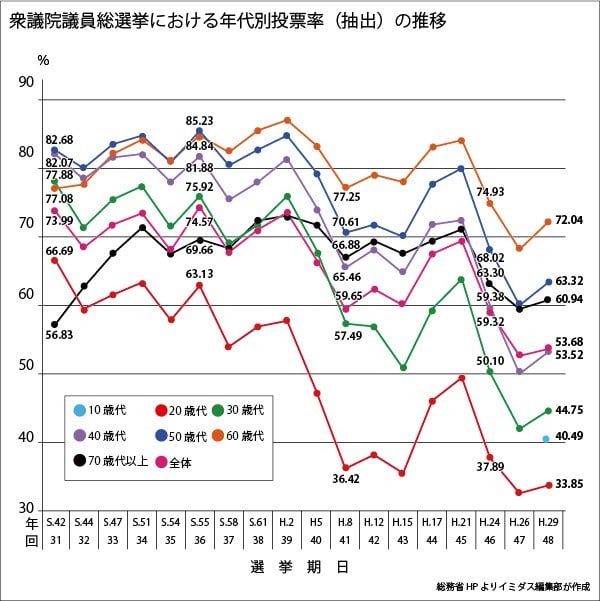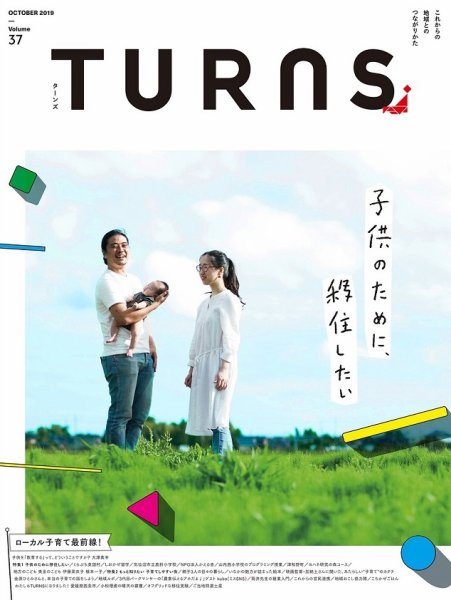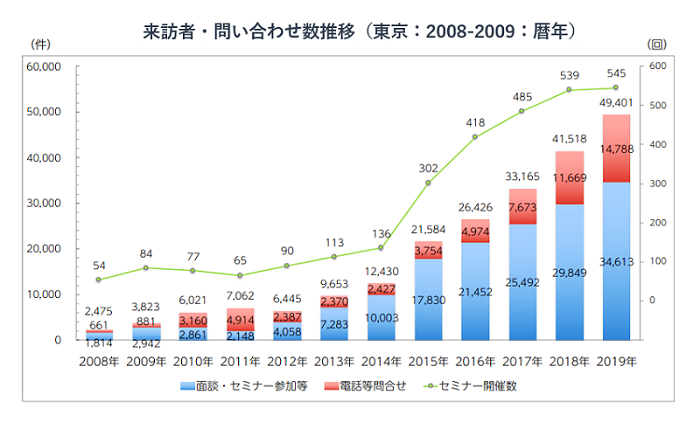マガジン9 2020年10月14日
日本学術会議の任命拒否問題が注目される中、恐ろしい小説を読んだ。
それは9月に出版された桐野夏生氏の『日没』。
帯には、「ポリコレ、ネット中傷、出版不況、国家の圧力。海崖に聳える収容所を舞台に『表現の不自由』の近未来を描く、戦慄の警世小説」とある。
主人公は作家のマッツ夢井。彼女のもとに「総務省文化局・文化文芸倫理向上委員会」から「召喚状」が届くところから物語は始まる。
召喚状では、「出頭」が要請され、日時、場所が指定されている。
「当地では、若干の講習などが予定されています。宿泊の準備等、お願いします」。病気などで出頭できない場合は医師の診断書が必要など、有無を言わせない迫力を漂わせている。
出頭日は明後日で、場所は千葉県の海辺の町。
そうして「文化文芸倫理向上委員会」の職員に案内されたのは、刑務所か秘密基地のような「療養所」。ネット環境もないのでスマホも通じず充電もできず、制服に着替えさせられ、粗末な個室と粗末な食事を与えられる。家に帰りたいと言っても帰れない。そして連れてこられた理由は「更生」のためと知らされる。
「こちらで、ご自分の作品の問題点をしっかり見据えて認識し、訓練によって直されてからなら、お帰りになることができます」と職員は言い、続ける。
「私たちは、あなた方作家さんたちに、社会に適応した作品を書いて頂きたいと願っているのですよ」
適応した作品とは、「正しいことが書いてある作品」。
この「収容」の根拠となるのは一年半前に成立した「ヘイトスピーチ法」。それを機に、「あらゆる表現の中に表れる性差別、人種差別なども規制していこうということになった」と職員は言う。ヘイトスピーチは表現ではなく扇動、差別そのもので自分の作品がそれと一緒くたにされるのは間違っているといくら言っても「文化文芸倫理向上委員会」の職員は「文句は政府に言ってください」と聞く耳を持たない。
マッツ夢井の作品が問題とされたのは、「読者からの告発」。レイプや暴力、犯罪をあたかも肯定するかのように書いているという内容の告発だった。
マッツ夢井の小説を読んだという職員も、彼女の作品を異常だと断じ、「先生、一度精神鑑定とかを受けてみたらどうですか?」と恐ろしいことをさらりと言う。
時が経つにつれ、さらに彼らの本音が見えてくる。
「先生方が無責任に書くから、世の中が乱れるということがわかっていない。猥褻、不倫、暴力、差別、中傷、体制批判。これらはもう、どのジャンルでも許されていないのですよ。昨日は言いませんでしたが、先生は文芸誌の対談で、政権批判もされてますよね。いえ、否定しても証拠がありますから。私たちは、ああいうことはやめて頂きたいんです。ええ、心の底から。作家先生たちには、政治なんかに口を出さずに、心洗われる物語とか、傑作をものして頂きたいんですよ」
主人公は怒り、混乱し、怯える。
「愚昧な人間たちが、小説作品を精査して偏向もしくは異常だと断定し、小説を書いた人間の性格を糺そうとしている。これほど恐ろしいことはなかった。療養所。そして、精神鑑定。その先には何があるのだろう」
しかし、逆らえば「減点」され、減点1で入院期間が一週間延びる。そんな「作家収容所」には、多くの作家が収容されているが会話は禁止。話したのがバレると共謀罪を適用される。
生活は常に欠乏と隣り合わせだ。
「腹が減る。トイレットペーパーがなくなる。電話ができない。メールもLINEもできない。ネットが使えない。監視されている。仲間と話せない。出て行きたいのに出て行けない。こうして、すべての自由を奪われたことを認識すると、人は従順になるのだろうか」
療養所に来る前に耳にした、「最近、作家がよく自殺する」という噂。演劇界や映画界でもこのところ多い訃報。マッツの前にこの個室を使っていたのだろう作家の遺書には、小説の前後の文脈を無視してその箇所だけを切り取られ、「人種差別作家」というレッテルを貼られたという嘆きが綴られている――。
「嫌な人間を書かせたら世界一」の桐野夏生が、とっておきの嫌なシチュエーションで嫌な奴ばかり登場させるのだから面白くないわけがない。夢中になって読みながら、何度も「これ、今の日本で起きてることとどう違う?」とスッと背筋が寒くなった。物書きとして20年生きてきた私にも思い当たるようなエピソードがところどころにちりばめられ、ざわついた気持ちになること数知れず。特にSNSが普及してからの「悪意ある切り取り」や、炎上、密告を恐れて萎縮するような、誰も信用できないような、なんとも言えない嫌な空気感が終始まとわりついてくる。
そんな中、職員がマッツ夢井だけでなく、療養所に来る作家全般に悪意を抱いていることも強調される。
「自分の薄汚い妄想を書き連ねるだけで金が貰えるなんて、そんな世の中、大いに間違っていると思いますよ」
「作家先生」は好き勝手なことして金稼いで偉そうにして、という鬱屈した思いは、職員たちの多くの言動から垣間見える。実際に口にする者もいる。
さて、そんな『日没』のシーンを彷彿とさせるようなものを今、あちこちで目にする。日本学術会議の任命拒否問題が報じられる一方で、学者たちがいかに「恵まれているか」を伝えるメディア。年金の情報など正確でないものを打ち出していかに「既得権益」であるかを主張する人。橋下徹氏もツイッターで「税金もらって自分の好きなことができる時間を与えてもらって勉強させてもらっていることについての謙虚さが微塵もない」などと書いている。それに対して、気が遠くなるほど多くの人が賛意を示している。
なんだか、あの小説の世界が現実にふっと漏れ出したような気がした。「税金でよくわからない学問をする学者先生」に対する漠然とした反発。誰かが「不当な特権」を持ち、「不当に恩恵に浴している既得権益」であるかのように名指して非難するやり方。
が、このようなバッシングは、もう見飽きてきた光景だ。
公務員バッシングに始まり、生活保護利用者までが「特権」とバッシングされてきたこの十数年。そうして現在は、障害者など公的ケアの対象となる人々までが「不当に特権を享受している」とバッシングされる始末だ。障害者ヘイト、子連れヘイトという言葉まである。そうしてこの手のバッシングを遡れば、郵政民営化に辿り着く。どこかに「既得権益」があると言われ、それをブッ潰せばこちらに何か「得」があるかのように思い込まされ、常に何かを叩いてきた十数年。
さて、その果てに、あなたのもとに恩恵はもたらされただろうか? おそらくまったくないはずだ。なぜなら、それはガス抜きのために準備されたものだからだ。「こいつが悪い」と敵を名指され、叩いているうちは充実感もあるし正義感も満たされるし「これで自分の生活は少し良くなる」という希望も持てるだろう。しかし、そんなことを繰り返しているうちに、1997年をピークとして子育て世帯の年収は100万円近く下がり、非正規雇用率は4割近くに達した。コロナ不況では非正規層をはじめとして多くの人があっというまに職を失ったわけだが、その怒りは政治には向かわず、誰かが名指した「敵」に向かう。そして今、「こいつらが既得権益だ!」と名指されているのが日本学術会議というわけだ。
『日没』の世界が描く、最悪の「近未来」までのカウントダウン。それは、すでに始まっている。
当初、0℃とかの予報も出ていましたが3℃位に訂正されたようです。
今日も予報には☂マークはなかったのに昼前から降り出し、今も降っています。
手稲山に初雪が降ったそうです。暑寒連峰の方を見ると雲ではっきりとは見えませんが白くなっているようです。こちらも、今降っている雨が雪になる可能性、あるか?
きのこ
先日紹介したものですが、なめこ?傘はネバネバ、でも色が鮮やかすぎ。わからないのでスルーしておきます。

他


エゾサンショウオ













 men
men