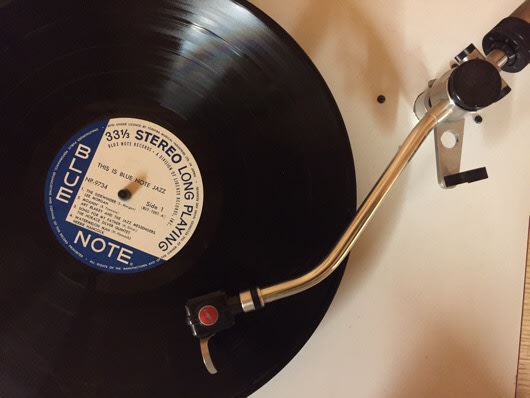『どれが良い? フォノイコライザーアンプの方式 vol.2』の続きです。
次はデジタル方式です。
この方式は斬新です。
カートリッジからの信号をA/Dコンバーターでデジタル化し、
DSPへ入力します。
DSP内でRIAAカーブを作り出すものです。
いくつかのメーカーで実験的に行っています。
当社でも実験しています。
よい所は完璧なRIAAカーブを作ることができます。
位相の問題を考えなくても良いです。
出力もデジタル信号ですので、そのままWAVやMP3ファイルにするこも可能です。
問題点は、
A/Dコンバーターの入力レベルはカートリッジの出力に対して高いので
初段でアナログ的に増幅しなければなりません。
結局はアナログアンプが必要です。
また、24ビットのA/Dコンバーターを使用しても
20Hzの低音域では24ビットで動作しますが
20KHzの高音域では17ビット相当になってしまいます。
また、大きな問題として
アナログレコード特有のダイナミックで味のある音質が再現できるのか?
ということがあります。
しかしながら、今後PCオーディオが発達していく中で
いずれ考えなくてはならない方式だと思います。
当社で実験したときの音質はとても『スマート』で『クール』でした。
次はハイブリッド方式です。
次回に続きます・・・
お問い合わせの多いアウトレットモールはこちらです。
ご質問がありました。
『小型ブックシェルフなので低音を補うため低域増強アダプターを使っていますが
現在連載中の12dB/oct 2WAYチャンデバと併用して使えるのでしょうか?』
ありがとうございます。
低域増強アダプターは小型スピーカーの低域を補うもので
チャンデバとは異なる機能です。
併用してもまったく問題ありません。
私の知り合いでチャンデバの調整によって低域を補っている方がみえますが
この場合4WAY以上でないとうまくいきません。
低域の補強は専門の回路に任せたほうがうまくいくと思います。
次はデジタル方式です。
この方式は斬新です。
カートリッジからの信号をA/Dコンバーターでデジタル化し、
DSPへ入力します。
DSP内でRIAAカーブを作り出すものです。
いくつかのメーカーで実験的に行っています。
当社でも実験しています。
よい所は完璧なRIAAカーブを作ることができます。
位相の問題を考えなくても良いです。
出力もデジタル信号ですので、そのままWAVやMP3ファイルにするこも可能です。
問題点は、
A/Dコンバーターの入力レベルはカートリッジの出力に対して高いので
初段でアナログ的に増幅しなければなりません。
結局はアナログアンプが必要です。
また、24ビットのA/Dコンバーターを使用しても
20Hzの低音域では24ビットで動作しますが
20KHzの高音域では17ビット相当になってしまいます。
また、大きな問題として
アナログレコード特有のダイナミックで味のある音質が再現できるのか?
ということがあります。
しかしながら、今後PCオーディオが発達していく中で
いずれ考えなくてはならない方式だと思います。
当社で実験したときの音質はとても『スマート』で『クール』でした。
次はハイブリッド方式です。
次回に続きます・・・
お問い合わせの多いアウトレットモールはこちらです。
ご質問がありました。
『小型ブックシェルフなので低音を補うため低域増強アダプターを使っていますが
現在連載中の12dB/oct 2WAYチャンデバと併用して使えるのでしょうか?』
ありがとうございます。
低域増強アダプターは小型スピーカーの低域を補うもので
チャンデバとは異なる機能です。
併用してもまったく問題ありません。
私の知り合いでチャンデバの調整によって低域を補っている方がみえますが
この場合4WAY以上でないとうまくいきません。
低域の補強は専門の回路に任せたほうがうまくいくと思います。