先日たまさかアルゼンチン人ナレーターと仕事をしたばかりである。スタジオで待っていたら、そのナレーター氏Dと、スペイン女性Cがやって来た。この女性はマネージャーではなく、スペイン語の指導係だという。アルゼンチンだって母語はスペイン語なのだから、スペイン語指導は必要ないというのは認識不足である。われわれ門外漢の耳でも、アメリカ映画とイギリス映画の英語の違いくらいは分からぬでもない。ブラジル映画とポルトガル映画を見ていても、同じポルトガル語でもずいぶんと違うことに気づかずにはいられない。
アルゼンチン人のスペイン語は、やや語尾の母音が豊かに伸びすぎるきらいがあると思った。首都ブエノスアイレスを中心にイタリア系住民のプレゼンスが高いことも関連しているかと思われる。スペイン語の堪能な人に言わせると、アルゼンチン人のスペイン語はひどく聞きづらいそうである。メッシやアグエロの訛りは非常に聞き取りにくいとのこと。
 それと、スペイン語で最も特徴的と言ってもいい「lla」「lle」「llo」について。パエリア Paella、あるいはセビリア Sevilla、あるいは作家のバルガス・リョサ Vargas Llosaくらいは挙げたらいいだろうか? これは「ジャ」「ジェ」「ジョ」と発音してもいいし、昔はもう少し上品に「リャ」「リェ」「リョ」と発音した。バルセロナなどカタルーニャ地方では、もっと軟弱に「ヤ」「イェ」「ヨ」に聞こえる。つまり、これらの中間的な音である。首都マドリーで上の単語を聞くかぎり、それぞれ「パエージャ」「セビージャ」「バルガス・ジョサ」と聞こえる。
それと、スペイン語で最も特徴的と言ってもいい「lla」「lle」「llo」について。パエリア Paella、あるいはセビリア Sevilla、あるいは作家のバルガス・リョサ Vargas Llosaくらいは挙げたらいいだろうか? これは「ジャ」「ジェ」「ジョ」と発音してもいいし、昔はもう少し上品に「リャ」「リェ」「リョ」と発音した。バルセロナなどカタルーニャ地方では、もっと軟弱に「ヤ」「イェ」「ヨ」に聞こえる。つまり、これらの中間的な音である。首都マドリーで上の単語を聞くかぎり、それぞれ「パエージャ」「セビージャ」「バルガス・ジョサ」と聞こえる。
以前、バルガス・リョサの故郷ペルーのカメラマンと仕事したことがあって、ロケの移動途中でバルガス・リョサの写真展が開催されている看板を見た私がその名を言うと、「そうだね、バルガス・ジョサだ」と答えていた。ペルー本国でもバルガス・リョサではなく「バルガス・ジョサ」に近いらしい。アルゼンチン人ナレーター氏Dも、この「LL-」の音を「ジャ」行で発音していたが、スペイン女性C(アストゥリアス自治州ヒホン近郊出身、とのこと)は、これを「ヤ」に近い音に訂正していた。彼女いわく、「パエーイャ」「セビーイャ」みたいな音感である。
もうひとつ報告しておくと、「z」の音について。Martínezはマルティネス、Suárezはスアレス、Gonzálezはゴンサレスである。「z」はスペイン語では「ザ」行にならない。濁らずに「サ」行で発音する。もちろんD氏もそのように発音していた。ところがC女史が「ちがう」と言ってきた。単なる「サ」行ではなく、スペイン本国では、英語の「th」のように舌の先っちょを軽く噛んで、[θ] のように無声音で発音するとのこと。ゴンサレスの「サ」の部分と語末の「ス」の部分を [θ] 音で言ってみると、たしかにぐっとスペイン人ぽい音になる。
このレコーディング作業をおこなった4日後に、ヒューマントラストシネマ有楽町でアルゼンチン映画『人生スイッチ』を見た。注意深く聴いていたが、たしかにアルゼンチン人のスペイン語そのものだと納得した次第である。「z」の音は舌を噛んでいなかった。
アルゼンチン人のスペイン語は、やや語尾の母音が豊かに伸びすぎるきらいがあると思った。首都ブエノスアイレスを中心にイタリア系住民のプレゼンスが高いことも関連しているかと思われる。スペイン語の堪能な人に言わせると、アルゼンチン人のスペイン語はひどく聞きづらいそうである。メッシやアグエロの訛りは非常に聞き取りにくいとのこと。
 それと、スペイン語で最も特徴的と言ってもいい「lla」「lle」「llo」について。パエリア Paella、あるいはセビリア Sevilla、あるいは作家のバルガス・リョサ Vargas Llosaくらいは挙げたらいいだろうか? これは「ジャ」「ジェ」「ジョ」と発音してもいいし、昔はもう少し上品に「リャ」「リェ」「リョ」と発音した。バルセロナなどカタルーニャ地方では、もっと軟弱に「ヤ」「イェ」「ヨ」に聞こえる。つまり、これらの中間的な音である。首都マドリーで上の単語を聞くかぎり、それぞれ「パエージャ」「セビージャ」「バルガス・ジョサ」と聞こえる。
それと、スペイン語で最も特徴的と言ってもいい「lla」「lle」「llo」について。パエリア Paella、あるいはセビリア Sevilla、あるいは作家のバルガス・リョサ Vargas Llosaくらいは挙げたらいいだろうか? これは「ジャ」「ジェ」「ジョ」と発音してもいいし、昔はもう少し上品に「リャ」「リェ」「リョ」と発音した。バルセロナなどカタルーニャ地方では、もっと軟弱に「ヤ」「イェ」「ヨ」に聞こえる。つまり、これらの中間的な音である。首都マドリーで上の単語を聞くかぎり、それぞれ「パエージャ」「セビージャ」「バルガス・ジョサ」と聞こえる。以前、バルガス・リョサの故郷ペルーのカメラマンと仕事したことがあって、ロケの移動途中でバルガス・リョサの写真展が開催されている看板を見た私がその名を言うと、「そうだね、バルガス・ジョサだ」と答えていた。ペルー本国でもバルガス・リョサではなく「バルガス・ジョサ」に近いらしい。アルゼンチン人ナレーター氏Dも、この「LL-」の音を「ジャ」行で発音していたが、スペイン女性C(アストゥリアス自治州ヒホン近郊出身、とのこと)は、これを「ヤ」に近い音に訂正していた。彼女いわく、「パエーイャ」「セビーイャ」みたいな音感である。
もうひとつ報告しておくと、「z」の音について。Martínezはマルティネス、Suárezはスアレス、Gonzálezはゴンサレスである。「z」はスペイン語では「ザ」行にならない。濁らずに「サ」行で発音する。もちろんD氏もそのように発音していた。ところがC女史が「ちがう」と言ってきた。単なる「サ」行ではなく、スペイン本国では、英語の「th」のように舌の先っちょを軽く噛んで、[θ] のように無声音で発音するとのこと。ゴンサレスの「サ」の部分と語末の「ス」の部分を [θ] 音で言ってみると、たしかにぐっとスペイン人ぽい音になる。
このレコーディング作業をおこなった4日後に、ヒューマントラストシネマ有楽町でアルゼンチン映画『人生スイッチ』を見た。注意深く聴いていたが、たしかにアルゼンチン人のスペイン語そのものだと納得した次第である。「z」の音は舌を噛んでいなかった。










 駿台予備学校(東京・お茶の水)で物理を教える山本義隆の新著『原子・原子核・原子力』(岩波書店)を読んでみた。不肖私が学参以外の理系本をみずから買うのは、恥ずかしながら生まれて初めてのことである。山本義隆という人は、駿台のおもに東大理系・医系コースの物理を教えていたと記憶している。私は私立文系志望でノホホンと過ごしたので、あまり縁がない。ただ、高2の夏休みに夏季講習を受けた際、どういうわけか各教科の東大コース主力級が教壇に立ったので、山本の物理も受けることができた。
駿台予備学校(東京・お茶の水)で物理を教える山本義隆の新著『原子・原子核・原子力』(岩波書店)を読んでみた。不肖私が学参以外の理系本をみずから買うのは、恥ずかしながら生まれて初めてのことである。山本義隆という人は、駿台のおもに東大理系・医系コースの物理を教えていたと記憶している。私は私立文系志望でノホホンと過ごしたので、あまり縁がない。ただ、高2の夏休みに夏季講習を受けた際、どういうわけか各教科の東大コース主力級が教壇に立ったので、山本の物理も受けることができた。 チャールズ・ラム(1775-1834)の『エリア随筆』は、随筆と戯曲の国イギリスを代表する名著で、遠く明治以来、日本の読書人のあいだでも愛読されてきた。私は作者チャールズ・ラムについて、南條竹則 著『人生はうしろ向きに』(集英社新書 2011)で一章を割いて論じられているのを読んで、がぜん興味を抱いた(そしてこの南條『人生はうしろ向きに』じたい、珠玉の随筆にほかならぬのだが)。そして、昨年より満を持して、南條による邦訳で『完訳 エリア随筆』全4巻の刊行が始まったのである(国書刊行会)。
チャールズ・ラム(1775-1834)の『エリア随筆』は、随筆と戯曲の国イギリスを代表する名著で、遠く明治以来、日本の読書人のあいだでも愛読されてきた。私は作者チャールズ・ラムについて、南條竹則 著『人生はうしろ向きに』(集英社新書 2011)で一章を割いて論じられているのを読んで、がぜん興味を抱いた(そしてこの南條『人生はうしろ向きに』じたい、珠玉の随筆にほかならぬのだが)。そして、昨年より満を持して、南條による邦訳で『完訳 エリア随筆』全4巻の刊行が始まったのである(国書刊行会)。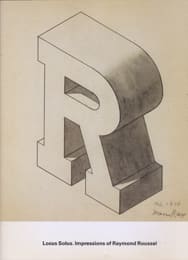 日本国内の美術展や博物展は、すでに海外でキュレートされた展示の並行輸入が多く、世界規模に通用するオリジナルの企画が少なすぎると批判されている。また、私も同じような批判を書いたこともある。しかし、問題は並行輸入が多いことではなく、並行輸入すべきものがされないという点にもあるように思う。世界には、より多くの視線を集めるべきすばらしい美術展があるのに、そうならない。だからこそ、地球の反対側に旅をする理由も生まれるのであるが。
日本国内の美術展や博物展は、すでに海外でキュレートされた展示の並行輸入が多く、世界規模に通用するオリジナルの企画が少なすぎると批判されている。また、私も同じような批判を書いたこともある。しかし、問題は並行輸入が多いことではなく、並行輸入すべきものがされないという点にもあるように思う。世界には、より多くの視線を集めるべきすばらしい美術展があるのに、そうならない。だからこそ、地球の反対側に旅をする理由も生まれるのであるが。