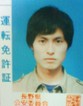2/2(火)、ユナイテッド・シネマ新潟で「ズーム 見えない参加者」を観てきました。
予告編はこちら。
ロックダウン中のイギリスで、Zoomで興味本位で交霊会を始めた若者達が、次々と異変に襲われ犠牲となっていくというホラー。
やはりホラーは時代を映す鏡で、邦画でも「真・鮫島事件」というホラー映画にZoomが登場したけど、本作は全場面がPC画面で表現され、新時代のPOVホラーにもなっていたところも見所の一つでした。
ホラーってリアルな物語の中に恐怖が起こるからまるで自分の身に起こりそうで怖いわけだけど、本作も冒頭の異変が起こる前からZoomならではの画質や音質、Zoomあるある的な展開がリアルに作りこまれているからこそ引き込まれるものがありました。
そして、途中から連発する異変の一つ一つも、Zoomという設定だからこそ可能なホラー表現に挑戦していて、そのアイディアが豊富で驚かされました。
Zoomの限られた映像の中で「見えない何者かに襲われる」という物語を表現するアイディアが本当に豊富なんですよね。
中には「透明人間」という映画にも登場したような表現も登場するけど、それもZoomという決して画質がいいわけではない設定の中で表現されると、本当に見てはいけないものを見てしまったという心霊写真的な新たな恐怖がありました。
他にもSnowのような顔加工アプリが見えない何者かに反応してしまうという表現も登場し、これはSnowの持つポップさとのギャップや、同時にSnowが実は持っている不気味さとも相まって、この映画ならではの絶妙なホラー表現になっていました。
また、冒頭で何気なく登場した録画映像が中盤に再び登場し「あれ?」と思わせておいてそれは実はフェイクで、その直後に恐怖映像!という、ホラーのための伏線回収も見事でした。
Zoomって画面上で何が起きても閉じない限り映し続けてしまうものであり、さらに本作では主人公が見ているPCの画面が最初から最後までスクリーンに映り続けるため、自分も本当にPCの画面を見続けているような気持ちになり、結果的に恐怖表現から目が背けられなくなってしまうという、恐怖への引き込み方が凄かったです。
だからこそ、映画の中でどんな恐怖表現もしつこいくらいスクリーンに映り続けてしまうし、映画を観ている僕が「もうやめてー!」と思っても止まらないという、本当にこの「強制的に見させられてしまう体験」こそホラー、というか、そもそも映画ってそういう文化だよねという、特殊な設定の中で実は映画の根本的なものを表現した作品になっていたような気がします。