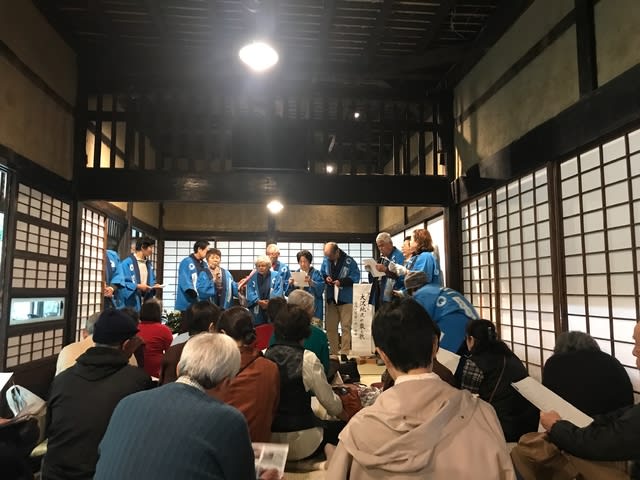昨今、障害者の水増しや就職差別が横行している。なんのために法律を作ったのか。破るために法律がある?

ルーテル学院大学の公開講座で、「障害者福祉論」(高山由美子先生)を受講している。今回の事件が起こる中でちょっと本気度が出てきた。でも、法律は難しく書かれていたなかなか理解できない。その中でも「合理的配慮」がすっと心の中に落ちてこなかった。
誰のための合理的な配慮なのか?国民のための、障害者のための、自分の保身のための、忖度するための・・・。
わかりやすい新聞記事があるので紹介する。
11月2日(金)、朝日新聞朝刊の
(耕論)「配慮」が「排除」に? 平井康之さん
https://digital.asahi.com/articles/DA3S13750878.html?ref=pcviewer
■対話し理にかなう調整を 平井康之さん(九州大学大学院教授)
日本では「配慮」という言葉は気遣いを意味し、特別に心を配るというニュアンスがあります。配慮する側とされる側が対等でなく上下の関係になりがちで、迷惑でも断りづらい。だから育児しながら働く女性への配慮にも齟齬(そご)が生じるんだと思います。
しかし近年よく言われる「合理的配慮」は本来もっとドライな概念です。英語では「reasonable accommodation」と表現され、異なる事情を抱える人たちが同じ機会を得るために「理にかなった調整をすること」を意味します。しかし日本で「合理的配慮」と訳されたため、少々誤解されている側面があります。
製品や建物のデザインの世界は、常にこの「配慮」の問題を考えてきました。最初に対象になったのが身体の障がいやけがといった物理的な不自由さです。米国では1950年代に傷病軍人らが働きかけ、建物にスロープを設置するなどの「バリアフリー」の基準が制定されました。
ただバリアフリーでは、車いすの人を通常の入り口ではないエレベーターへ案内するなど、特定の人を区別して扱う時があります。これを排除と感じる人もいるでしょう。
米国で始まり90年代に普及した「ユニバーサルデザイン」はこの問題意識に応え、年齢や性別、障がいの有無に限らず、全ての人が使いやすいデザインを提唱しました。
例えば、幅の広い改札や、目をつぶっても判別可能なシャンプーとリンスの容器などです。誰もが使いやすいということは、顧客も多いということ。商業的な利益とも合致し、日本でも多くの商品が作られました。東京五輪を前に、国はこのデザインを広めようとしています。
近年、注目を浴びているのが、欧州発の「インクルーシブデザイン」です。ユニバーサルデザインが目指すものとゴールは一緒ですが、アプローチの仕方が異なります。世の中には物理的な障壁だけでなく、性差や国籍・言語の違い、貧困、デジタルアクセスなど様々な「壁」に直面する人たちがいます。彼らに初期の段階からデザインに参加してもらうことで「誰も排除しない」ことを目指します。
九州大が共同研究でデザインした小児用服薬ツールは、子どもたちや薬剤師と話し、服薬のストレスを和らげるハートや魚の形のゼリーで包んだデザインにしました。ここで大切なのは「対話」です。機能性だけでなく、一人ひとり異なる気持ちに耳を傾け、ともに模索するのです。
日本でも、社会や職場で誰かに配慮する時はもっと対話をした方がいいと思う。その人が何を必要としていて、自分は何ができるのか。それが把握できれば、配慮が排除につながることはないと思います。(聞き手・藤田さつき)
*
ひらいやすゆき 1961年生まれ。米デザインコンサル会社IDEOなどのデザイナーを経て現職。専門はインクルーシブデザイン。