戦国時代末期を生きた江村専斎(えむら・せんさい)という老人が語った話を聞き書きした『老人雑話』というものがあるのは「本能寺の変」研究者にはよく知られた話です。そこには通説とは少しずれた話が書かれており、研究者が引用する場合にも極めて遠慮した使い方がされています。本能寺の変の当時に十八歳だったという老人からの聞き書きを私も信憑性がないとこれまで全く無視していました。
とはいえ、最近少し気になって原文を読んでみました。活字化されたものは四十ページ程度のもので、様々な話の断片が順不同で書き連ねられています。何でこうも乱雑に脈絡も無い様々な話の断片が書き連ねられているのかとあきれてしまいます。恐らく老人が思いつくままに話すいろいろな話をそのまま書き留めたものなのでしょう。
あきれると共に、これは軍記物と本質的に違うと直感しました。軍記物は面白おかしい話を創って広く売ろうという商業主義で書かれています。江戸時代に発達した木版印刷での出版事業に乗っていたのです。ですから面白いストーリーが上手に書かれているのです。ところが『老人雑話』にはストーリーが全くありません。軍記物の世界とは明らかに全く無縁の書き物です。
そこで江村専斎という人がどういう人か調べてみました。時間もないのでインターネットでの調査です。調べてみると、加藤清正、細川藤孝、羽柴秀吉と交際があり、医者として名声が高く、天皇より長寿の祝賀をもらった人物のようです。
★ Wikipedia「江村専斎」記事
★ デジタル版日本人名大辞典「江村専斎」
『老人雑話』には本能寺の変や明智光秀に関する記述が秀吉や家康に関する記述に混じって10箇所ほど出てきます。その部分を特に注意して読んで驚きました。拙著『本能寺の変 四二七年目の真実』で見い出した真実と合致する記述が何箇所かあるのです。いずれも通説とは全く異なる記述です。以下にそれをご紹介します。
1.光秀は初め細川藤孝に仕えていた。
拙著の45頁から47頁に書いたことです。私は奈良興福寺多聞院院主の日記とイエズス会宣教師ルイス・フロイスの報告書の記述からそうであると書きました。従来の歴史研究家はこれは彼らの勘違いだと否定してきましたが、江村専斎が細川藤孝と親しい関係にあったとすると勘違いということはないといえます。
2.穴山梅雪は一揆に殺されたとも、家康に殺されたとも言われる。
拙著の167頁から169頁に梅雪は家康に殺されたと書きました。家康の家臣である松平家忠の日記の記述からそうであると書きました。現代の歴史研究家は通説を頭から信じ込んでいて、そんなことはあり得ないと言いますが、当時の人々はその可能性があるとみていたことを示しています。
3.信長は家康を堺遊覧に送り出したが、隙を見て家康を討つ企てだった。光秀謀反がなければ家康は命がなかった。
これこそ拙著で書いた「本能寺の変とは本当は信長による家康討ちだった」という122頁から146頁に渡って丁寧に説明した真実を裏付けるものです。重要なことは細川藤孝や秀吉とも交際のあった人物がこのような記述を残したということです。現代の歴史研究家は「あり得ない!」と言下に否定してしまうことが、本能寺の変当時を生きた人物にとっては「あり得る!」どころか確信を持って言い切っていることです。
「あり得ない!」と言い切っている歴史研究家にも2チャンネルの本能寺の変論者にも、是非『老人雑話』の信憑性の再評価をお願いしたいと思います。
四百年の時を隔てて、それこそ全く無縁の二人の人物(専斎と私)がそれぞれ個別に得た情報から語ったことが3つも合致する、しかもその内容は通説と全く異なる、という事実の重大性を是非感じ取っていただきたいと思います。江村専斎という人物や人脈について情報がありましたらお知らせください。
【歴史研究の落とし穴をのぞくシリーズ】
江村専斎『老人雑話』の歴史研究
『甲陽軍鑑』の歴史捜査(その1)
『甲陽軍鑑』の歴史捜査(その2)
『甲陽軍鑑』の歴史捜査(その3)
とはいえ、最近少し気になって原文を読んでみました。活字化されたものは四十ページ程度のもので、様々な話の断片が順不同で書き連ねられています。何でこうも乱雑に脈絡も無い様々な話の断片が書き連ねられているのかとあきれてしまいます。恐らく老人が思いつくままに話すいろいろな話をそのまま書き留めたものなのでしょう。
あきれると共に、これは軍記物と本質的に違うと直感しました。軍記物は面白おかしい話を創って広く売ろうという商業主義で書かれています。江戸時代に発達した木版印刷での出版事業に乗っていたのです。ですから面白いストーリーが上手に書かれているのです。ところが『老人雑話』にはストーリーが全くありません。軍記物の世界とは明らかに全く無縁の書き物です。
そこで江村専斎という人がどういう人か調べてみました。時間もないのでインターネットでの調査です。調べてみると、加藤清正、細川藤孝、羽柴秀吉と交際があり、医者として名声が高く、天皇より長寿の祝賀をもらった人物のようです。
★ Wikipedia「江村専斎」記事
★ デジタル版日本人名大辞典「江村専斎」
『老人雑話』には本能寺の変や明智光秀に関する記述が秀吉や家康に関する記述に混じって10箇所ほど出てきます。その部分を特に注意して読んで驚きました。拙著『本能寺の変 四二七年目の真実』で見い出した真実と合致する記述が何箇所かあるのです。いずれも通説とは全く異なる記述です。以下にそれをご紹介します。
1.光秀は初め細川藤孝に仕えていた。
拙著の45頁から47頁に書いたことです。私は奈良興福寺多聞院院主の日記とイエズス会宣教師ルイス・フロイスの報告書の記述からそうであると書きました。従来の歴史研究家はこれは彼らの勘違いだと否定してきましたが、江村専斎が細川藤孝と親しい関係にあったとすると勘違いということはないといえます。
2.穴山梅雪は一揆に殺されたとも、家康に殺されたとも言われる。
拙著の167頁から169頁に梅雪は家康に殺されたと書きました。家康の家臣である松平家忠の日記の記述からそうであると書きました。現代の歴史研究家は通説を頭から信じ込んでいて、そんなことはあり得ないと言いますが、当時の人々はその可能性があるとみていたことを示しています。
3.信長は家康を堺遊覧に送り出したが、隙を見て家康を討つ企てだった。光秀謀反がなければ家康は命がなかった。
これこそ拙著で書いた「本能寺の変とは本当は信長による家康討ちだった」という122頁から146頁に渡って丁寧に説明した真実を裏付けるものです。重要なことは細川藤孝や秀吉とも交際のあった人物がこのような記述を残したということです。現代の歴史研究家は「あり得ない!」と言下に否定してしまうことが、本能寺の変当時を生きた人物にとっては「あり得る!」どころか確信を持って言い切っていることです。
「あり得ない!」と言い切っている歴史研究家にも2チャンネルの本能寺の変論者にも、是非『老人雑話』の信憑性の再評価をお願いしたいと思います。
四百年の時を隔てて、それこそ全く無縁の二人の人物(専斎と私)がそれぞれ個別に得た情報から語ったことが3つも合致する、しかもその内容は通説と全く異なる、という事実の重大性を是非感じ取っていただきたいと思います。江村専斎という人物や人脈について情報がありましたらお知らせください。
【歴史研究の落とし穴をのぞくシリーズ】
江村専斎『老人雑話』の歴史研究
『甲陽軍鑑』の歴史捜査(その1)
『甲陽軍鑑』の歴史捜査(その2)
『甲陽軍鑑』の歴史捜査(その3)










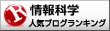















専門の?研究者には受けいられないでしょうが、十分に有りえた話とは思います。
とりあえず、信長が家康を討つ必要性というか可能性の確認をしっかりすれば、話は進んで行くのでないでしょうか。
自分なりにいろいろと考えているところではあります。
フロイス・2さんが藤本本についてまとめておられるのが非常に明解で参考になるので自分の感想も。
藤本本は確かに「家康黒幕説」というようによくある陰謀本と同じような誤解をされている印象がありました。
主な主張点は「密談は不可能」「機密漏洩」ということでしょうが、前者は「普通ならそうでも普通ではない内容、無理すれば機会は作れたであろう」と反論は可能、後者も「大化の改新以来現場にのこのこと当事者がやってきて変事が起きるのはよくあること、寸前まで最低の関係者のみの機密なら秘匿も可能」、と反論は可能とはおもいます。
特に家臣レベルならともかく、トップ同士の機密ゆえにこれも「通常とは違う」という意味で一般的な意味での「不可能だろう」という論では反論の根拠としては少し弱いようにも感じます。
明智説の優れてる点は、フロイス・2さんの言われるように「結論がスタート」となっていることで、今までなら「電話もない時代に事前相談は不可能」となっているのを、信長ー光秀、光秀ー家康ともに、寸前に会談しているという事実があること、単に油断とか一般的に語られていたことに、「明解な理由がある」と説明できること、にあると思います。
こういった論に対して藤本氏がどのように回答されるのか、とても関心のあるところではあります。
藤本氏が私の真実を家康黒幕説と誤解していることは大変残念です。インターネットの掲示板には拙著が家康黒幕説だとか一次史料をもとにしていないだとか、およそ正反対のことを声高に書いている人がいます。まさか藤本氏がこのような声に惑わされているとは思いませんが、果たして拙著をどの程度読み込んでいただけたのかと疑問には思います。読んでいただければ、私が藤本氏の研究スタンスと極めて近いスタンスに立っていることはおわかりいただけると思います。家康黒幕説など拙著のどこにも書かれていないことは拙著を読まれた方にはよくご理解いただけていることです。
是非、議論を低レベルに引きずられること無く、先へと進めたいと思います。
話が多少前後しますが、歴史研究では 「何がどうなったか、あるいはどうだったか」という事実の認定と、「なぜそうなったか」という真相の解明とが、コインの裏表ないし車輪の両輪のような関係で本来は共存すべきと考えます。 邪馬台国のように事実認定のレベルのみに議論が集約されているケースはむしろ稀です。 自分のコメントの繰り返しになりますが、藤本説、明智説はこの事実の認定においては極めて近いもので、従って有効な議論の前提は整っているように拝察します。 そこで争点として鮮明に浮かび上がってくるのが「信長の家康討ち」です。 家康黒幕説批判は、そもそもその前提が存在しませんし、一般論としての機密漏洩の危険については、まいさんご指摘の通り個別の事象に必ずしも該当しません。 「信長の家康討ち」に関しては明智さんを中心にこのブログサイトでもより濃密な議論が展開されることと楽しみにしていますが、少なくともこのことの蓋然性を実名で証言している者がもう1人増えたことに大いに興味をそそられています。
http://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/exhibit/t176/image/1/t176s0034.html
以下、改行位置も同じ。
"明智乱の時は、東照宮は堺に御座す。信長は羽柴藤五郎
に命じて家康に堺を見せよとて付けて遣す。実は(先にて?)隙
をみて害する謀なりとぞ"