先日、真冬のフィンランドの教育視察から帰国をしました。
冬の寒い時期を選んで行ったのは、一番厳しい気象条件を知り、人々の暮らしを見つめながら、
いまや世界に冠たる教育改革を成し遂げた行政主導の成果の一端を、実際に見たい、触れたいとの強い思いからでした。
到着時の首都ヘルシンキは気温マイナス5度で海沿いのため風が強く大変寒く、大変なところに来てしまった!と思いました。

まず最初に、ご好意により在フィンランド丸山大使を表敬訪問させていただきました。
ひっきりなしに日本からの教育視察が行われていること、フィンランドと日本のかかわりなどが話の中心でしたが、
私の父親が現役の頃は東芝のエレベーター設計の技術者で、
池袋のサンシャインシティのエレベーターの設計に携わったお話をしたところ大変喜ばれ、
現在ヘルシンキにある会社と技術提携をして東芝のエレベーターをヨーロッパに
輸出しているという話をうかがうことが出来ました。
さすがに世界を俯瞰してご覧になっている大使のお話はどれも興味深いものでした。
人口約500万人の国、フィンランドの首都であるヘルシンキの人口は約70万人、
世田谷区と同規模の都市ですが、国民の8割近くが平均して1日に1時間以上読書をするといわれ、
図書館の数は50以上もあるそうです。
ソマリヤからの移民を政策として受け入れており、その課題も出てきているとのこと。
ヘルシンキでは現役で子育て中のママと、日本語補習校の会長をしている方にもインタビューを
させていただきました。日本人の目から見た教育体制の違いをたっぷりとうかがいました。
フィンランドの教育はとにかく手厚い。
子供のペースを知った上で習熟度を見極め、解るまで教える、おちこぼれを出さない、とのこと。


トラムに囲まれたヘルシンキの人々は穏やかで、トラムの車内もその空気感に包まれていました。
そしてヘルシンキから北東に3時間半電車で移動をして、人口4万人強のミッケリ市に教育の現場を訪ねました。

ミッケリ市の市長さんと教育長さんとの面談、お部屋に伺うとフィンランドと日本の国旗の前に私の席が用意されていてびっくりしました。
今回の訪問は非公式、プライベートでと伝えてあったのですが、遠い日本から来てくれたと歓待してくださいました。


市長さんは40歳の元弁護士、多弁ではなくこちらの話をじっくりと聞いてからはにかみながら
補足するように教育の実情をお話してくれました。なかなかのハンサムタイプ。
人口4万人強、面積は杉並区の70倍、周囲を森と湖に囲まれているというミッケリ市に市議は58人と多く、
大多数の方が兼業しているとのこと。市議会と市民の距離感はかなり近いという印象を受けました。
上の写真は議場内の市長の席と市議会議員の席ですが、これがまた近い。より密な議会での様子が伺えました。
ミッケリ市では公立の小中学校の見学をさせていただきました。



まずは、国の教育政策と市独自、そして学校独自の教育方針のガイダンスをミッケリ市の教育長と学校の先生が
スライドを見ながらしてくださいました。
フィンランドでは日本の小学校1年生入園前に1年間のプレスクールが義務付けられ、
数字や文字とはどのようなものかといった概念の教育を通して、学校で勉強することへの準備が始まります。
そして小中一貫校が標準、サポートが必要な障害者のクラスも一緒です。
生徒それぞれのペースを大事に9年間で習熟度が達しない生徒には留年もあるそうです。
大学まで教育に関しては授業料は無料ですが、進学率は低いそうです。
本当に学問を探究心を持ってしていくという学生にしか門戸が開かれていないとのこと。
上の写真右はこの学校のシンボルマーク、国と市と先生と親、
そしてなにより重要な子供が一環となって学校が成り立つという思いを形にしたと話してくれました。




上の写真の左上は物理の授業、右上は英語の授業、左下は英語のリスニングの授業、そして右下は技巧の授業の特別室です。
生徒は20人強の少人数制で、学校の先生になるためには多数の実地研修を積んだ上で大学院を卒業し、
市の面接や学力試験、心理テストなどを合格してやっとなれるという難関コース、生徒は先生を尊敬したまなざしで見ていました。
英語の先生は5ヶ国語を話せるとのこと。エキスパートです。
国の教育改革の一環としてパソコンなどの電子機器類は充実していました。
生徒は科目によっては思い思いに歩き回る姿も見受けられ、皆靴下姿でリラックスしながらの授業です。




左上の写真は音楽の授業風景、右上は着替えるためのクローゼット、外用の車椅子やスキー、防寒具を置くコーナーが充実し、
介護者同伴で行きかうための十分なスペースが確保されています。
左下は室内用の移動用の用具置き場、右下は障害のあるお子さん専用の家庭科のためのキッチンです。
障害のある生徒は同じ建物の一角に専用のスペースが大変充実していて、生徒は授業を教える先生と、
それを受ける生徒の身の回りをサポートするスタッフの方に囲まれていました。



上の写真は家庭科の風景。教科書は実際に教える先生が作り上げるとのこと。やはり靴下姿です。



カラフルな図書室の様子です。北欧のインテリアは穏やかながらも長い冬を明るくするためにカラフルに多色使いをするのが
特徴です。ウッドの色は殆どがライトブラウン。ここには日本のアニメコーナーもありました。




小中一貫校のランチタイムは食堂で時間をずらして行われていました。
ミルクとパンとスープ。スープはお肉が入ったものとベジタリアン専用のものが用意されていました。
これまで小学校低学年から中学校高学年までが一同に学校で学ぶということのイメージがつかめずにいましたが、
違う学年がお互いを近い関係と感じながら一緒に学ぶということは、生活面や勉強においてもお互いを意識し
より良い影響を受けながら過ごしているのだと感じました。
上の写真の右下は中学生の家庭科の部屋から見える校庭の景色です。
この写真を撮って程なく、小学校低学年が外遊びを始めました。
高学年の生徒は小さい頃遊んだ校庭や、教えてもらった先生に囲まれて、改めて成長の過程を振り返ることが出来るのでしょう。
そして低学年の生徒は自分の将来の様子を身近に感じながら、一歩一歩確実に成長していくことへの安心感を得ながら
学校生活を送るのでしょう。
小中学校の先生同士の情報共有は日常的に図られ、より良い体制作りがとられるのでしょう。
長々としたブログになってしまいましたが、
現在、今回の視察を杉並区政へ活かすべく、次のステップを計画しています。
まずは視察の報告会を杉並区役所で4月中旬に開催をさせていただく予定です。
日時が決まりましたらブログにアップいたしますので、
ご興味のある方は是非お運びくださいませ。
















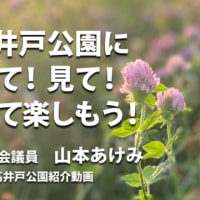






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます