この時期は、保育園の待機者と共に、特養待機者と表していました。
でも、特養に関しては、全ての人が待機をしている状況では無く、他の介護サービスで充足している方や、中には高齢者施設に既に入居している方なども含まれているのでは無いのか、そういった疑問から質問を致しました。
今では、特養に関しては待機者では無く、申込者と表しています。
この違いは大きく、きめ細かく需要を把握して行かなければ本当に必要としている方の入居は叶わず、また、真の需要を超えて施設整備がされれば、維持の為の運営費が必要以上に嵩んでいく事になります。
介護サービスに関しては、需要をきめ細かく把握し、施設整備に活かすよう要望を続け、また、区内特養の医療的なケアが必要な方の受け入れが施設によって違う条件を出来るだけ統一を図り、特定の施設に申し込みが集中し無いようになど、提言を続けています。
動画と議事録を掲載いたしますので、是非ご覧になってください。

平成29年第2定例会一般質問(平成29年5月31日)
動画:http://suginami.gijiroku.com/voices/g07_Video_View.asp?SrchID=4686
「高齢者介護施設について」
「学校図書館について」
「グリーンインフラについて」
◆12番(山本あけみ議員)
私は、区民フォーラムみらいの一員として、区政一般についてお尋ねをいたします。 テーマは、高齢者介護施設について、学校図書館について、グリーンインフラについてです。
最初に、高齢者介護施設についてお尋ねをいたします。
平成27年4月の介護保険制度変更により、特養へ新たに入所する方は、基本的には要介護3以上に限定されましたが、現在でも当区の特養の待機者は約1,000名であり、本年4月末現在で、優先度Aは540名、優先度Bが298名、優先度Cが141名と聞いています。

こうした状況において、特養の整備が喫緊の課題であることは認識しているものの、待機者の中には、既に他施設などに入所している方や、在宅介護支援施設の利用により介護が必要な状態が充足している場合、また、場合によっては他界された方も含まれているのではと考えています。特養入居を1つの選択肢として考えている状態であると推察しますが、より現状を言いあらわした言葉としては、特養待機者というより特養申込者とすべきと考えますがいかがかお尋ねをします。
ここでは、いわゆる待機者を申込者と言いあらわして質問を続けます。
昨年の決算特別委員会の資料請求で、現在の特養Aランク申込者の介護度と介護場所別の人数、率の資料をいただきました。それによれば、816名のうち、最も緊急度が高いと思われる要介護5で在宅の方が142名で全体の17%、また、既に特養に入居されている方が6名いらっしゃることがわかりました。
なぜこの資料の提示を求めたかというと、特養申込者の個々の現状を細かく把握していくことで、より困った人が優先される制度となっていかなければ、ただ漠然と申込者数1,000人という極めて大きな数字だけを把握していても、必要な人に支援の手が届かず、真の福祉向上にはつながっていかないだろうと考えてきたからです。
これまでの答弁では、今後特養整備を進めるに当たり、特養申込者の実態把握をしていくとあったと記憶をしています。区では特養申込者の現状把握はどれくらい進んでいるのか、お伺いします。
当区では、本年3月に特養入所判定基準の変更が行われました。これまでの判定基準では、本人の状況が要介護度のみであり、在宅であるのか、既に他自治体の特養に入居しているのか等、本人の状況が判然としなかったこと、また、介護者がどれくらい介護を担える状況にあるのか、詳細を知ることができないことが大きな課題だと感じていました。今回の改定で、これまでの申込者の詳細な現状把握の取り組みをとの要望に対して、真摯な御対応をいただいたことを大きく評価するとともに、また感謝も申し上げる次第です。
改めて今回の基準変更の趣旨について確認をいたします。また、どのような検討が行われ、課題意識等の共有などどのようにしたのか、経緯もお尋ねいたします。
次に、第一次評価指標の具体的な内容についてお伺いします。
待機場所の把握、点数配分をどのような論理づけで決めたのか。また、区民ではない場合と他の特養入所者の場合は加点ゼロにした理由は何か。
さらに、介護度が高く、在宅介護等を多用している方など、自宅での介護の大変さを示す指標はあるのでしょうか。
介護者の状況を細かく設定していますが、意図は何か。また、本人の日常生活状況の把握は、これまで一次評価指標にはなかった項目ですが、追加された意図についてお伺いします。
次に、特養申し込みの有効期限を提出から2年としていますが、今回期限を決めた理由と、なぜ2年にしたのか、お伺いをします。
広く高齢者の介護を支える社会を目指すためには、こうした内容をケアマネジャーから当事者への説明に任せるだけではなく、利用者自身や家族、また、広く一般の区民に対しても御理解いただけるようにすべきと考えますが、今後の区民周知への工夫があればお伺いします。
次に、入居順位の決定は、日次処理または月次処理、どちらで行われるのでしょうか。
入居順位の決定後、申込書の有効期限を待たずに条件が変更になり、緊急を要するようになった場合に、提出し直しは可能か、また逆に、緊急を要することがなくなった場合に、申し込みを辞退する書類の提出義務はあるのか、お尋ねをいたします。
新たに申し込む方は新しい基準が適用になりますが、これまでの申込者への対応はどのようにするのでしょうか。
次に、今回の入所申し込みのしおりに添付されている区内外の特養での徘回、医療処置が必要な方の受け入れ状況を拝見しますと、大きくばらつきがあり、特養ごとに特色があることがわかります。人工透析や中心静脈栄養、気管切開に関しては、おおむね受け入れができない状況は一緒ですが、区内特養においては、それに加えて、経管栄養や在宅酸素が必要な方の受け入れには消極的である状況がうかがえます。これでは、たとえ区内の特養入居を望んでも入れない方も多いのではと推察します。今後は地域医療との連携が進み、医療処置が必要な方の受け入れをふやしていく方向性はあるのか、お尋ねをします。
また、こういった状況下では、区内施設と区外協力施設において、特養申込者の希望が特定の施設に集中する傾向があると考えますが、いかがでしょうか。あるとすれば、区はその理由をどのように分析しているのか、お尋ねをします。
次に、特養の申し込みのしおりには、区内施設、区外協力施設以外に、独自に申し込みができる特養ホームの案内がありますが、ホームページを参照してくださいとのみアナウンスされており、情報を得る手段が限られていると感じます。もっと広く知ってもらう工夫をしてはどうかと考えますが、いかがでしょうか。
重要なのは、特養の申込者の実態をしっかり分析し、本当に必要な人の支援を行うことだと考えます。利用者の実態や多様なニーズに合った医療と福祉のマッチングなど、今後の区の施設整備のあり方について見解をお伺いいたします。
さきの決算特別委員会の資料請求では、介護保険サービス別、介護度別の利用状況の件数、金額の過去5年間の推移に関しての資料もいただき、どのサービスの需要が伸びているか等を把握することができました。これによると、在宅介護を支える訪問介護の実数は8万7,925人から8万9,153人と、1.4%増で微増、これに対して訪問看護数は2万4,783人から3万3,321人と、34.5%と大きくふえ、伸び率を比べれば、今後は訪問看護の需要がふえていくと予測されるなど、さまざまなことが見えてきます。
国においては、来年度は6年に1度の医療の診療報酬と介護報酬の同時改定の年に当たるとともに、医療介護総合確保方針等、医療と介護にかかわる関連制度の一体改革にとって大きな節目であり、それを目前にした今年度は、医療及び介護サービスの提供体制の確保に向け、さまざまな視点からの検討が重要となる年です。当区においても、区民の生活を足元で支える基礎自治体の使命として、まずは現状把握をしっかりとすること、そして一歩先を見据えた支援のあり方の議論の成熟を図ることを要望しまして、次の質問に移ります。
学校図書館についての取り組みをお伺いします。
杉並区子ども読書活動推進計画においては、学校図書館図書標準100%を達成した学校の割合は、平成29年度の目標を小学校、中学校ともに80%としていますが、現在の状況はどのようになっているのか、お尋ねします。
また、この目標達成に向けて、区としてどのような取り組みを行っているのでしょうか。100%達成も大切ではありますが、図書資料の蔵書内容の充実も重要と考えます。学校ではどのような取り組みを行ってきたのか、お尋ねをいたします。
本年3月、文部科学省は、学校図書館図書整備等5か年計画を取りまとめ、図書標準の達成を目指すとともに、計画的な図書の更新、学校図書館への新聞配備と学校司書の配置拡充を図るための地方財政措置について取りまとめをしました。
背景として、各学校で新聞を活用した学習を行うための環境が十分には整備されていない現状を踏まえ、平成27年6月の公職選挙法等の改正による選挙権年齢の18歳以上への引き下げ等に伴い、児童生徒が現実社会の諸課題を多面的に考察し、公正に判断する力をつけることが一層重要になっており、発達段階に応じた学校図書館への新聞の複数紙配備が必要であるとしています。当区では財政措置は受けないものの、今回の措置において、新聞の配備が小学校においては1紙、中学校では2紙という目標が示されたことを念頭に置くべきと考えます。
新聞各社には伝え方に特徴があり、複数紙をそろえることによって、児童生徒が多様な知識や情報に接することができ、みずからが情報を取捨選択しながら自分なりの考えを形成していくといった教育に生かすという視点を重視していくことも必要であると考えます。
同じ事柄であっても、新聞社ごとに伝え方には違いがあります。例えば先週の5月24日の朝刊には、組織的犯罪処罰法改正案の衆院本会議での可決に関してのニュースが、各紙の1面に掲載されました。見出しを挙げますと、朝日新聞では、「『共謀罪』衆院通過 自公維賛成、参院へ 29日審議入り 会期内成立厳しく」と伝え、副題として、「『何が罪に』不明確なまま」と疑問を呈しています。これに対して読売新聞では、「テロ準備罪衆院通過 自公維賛成 今国会で成立へ」とし、副題としては、「野党抵抗 与党会期延長も視野」に加え、「不安あおらず冷静な議論を」とし、野党の動きに対して、あおるという表現をつけ加えています。また、日本経済新聞では、トップニュースではなく、1面のやや端に、「『共謀罪』法案が衆院通過 29日にも参院審議入り」と事実のみを伝えています。同じ国会での出来事を伝えてはいるものの、共謀かテロ準備か、文言が違う上に、世論の一部に対して見解を大きく示すなど、法案の捉え方によって紙面構成が違い、見出しの言葉も違います。
一口に新聞といっても、どの新聞を読むかによって受ける影響は違うと考えます。教育の現場においては、その違いを知り、みずからの考えを培う力をつけることが目的なのだろうと考えますが、当区での認識も同じであることを望みながら質問をいたします。
図書資料に関連して、調べ学習には、図書資料の蔵書内容の充実及び新聞も活用すべきと考えますが、学校の活用状況はどのようになっているでしょうか。
また、さらなる新聞活用に向けた取り組みについて、教育委員会の見解をお伺いします。
当区においても、全国的な取り組みを確認しながら、子供の教育に資する環境を整えていく視点をより一層持っていただけるよう要望いたしまして、次の質問をいたします。
次に、グリーンインフラについてお尋ねをいたします。
去る4月26日の日本経済新聞に、「都市緑化で浸水被害減 神田川上流、効果100億円」という見出しの記事がありました。日本政策投資銀行などが、神田川上流域の豪雨を想定したシミュレーションで、緑化を進めた場合に、浸水する建物が減少し、100億円を超える効果が得られる試算をまとめたとのことです。大型下水設備など従来の社会インフラは老朽化が進むため、財政に与える影響が心配される中、いわゆるグリーンインフラとする都市緑化への投資を自治体に提言するとしています。神田川上流域の自治体とは、イコール杉並区のことで、本文には、シミュレーション対象は杉並区の神田川上流域約23平方キロメートルとあり、細かな試算がされています。
当議会でも、浸水被害を低減させるためには、被害が想定される住宅の建て方を工夫することで効果が出るのではないかといった議論がありましたが、今回のように広範囲での取り組みの効果額を示されると、格段にインパクトは大きいと感じました。
さて、この記事の中にあるグリーンインフラとは、米国で発案された社会資本の整備手法であり、自然環境が有する機能を社会におけるさまざまな問題解決に活用しようとする考え方です。日本においては、平成27年度に閣議決定された国土形成計画、第4次社会資本整備重点計画の中にあり、国土の適切な管理、安全・安心で持続可能な国土、人口減少、高齢化社会等に対応した持続可能な地域社会の形成といった課題への対応の1つとして、取り組みを推進していくことが盛り込まれました。
それを受けて、国土交通省総合政策局環境政策課では調査を行い、実は新たな考え方であり概念ではあるものの、既にグリーンインフラの要素をおおむね兼ね備えた取り組みがあるとの結果を得たとのことです。
翻って当区の取り組みを眺めてみても、緑地の整備には力を入れ、その恩恵を生活に生かすためにさまざまな工夫をしているところです。
そこで、確認のため質問をいたしますが、例えば国土交通省の調査結果に事例として挙げられている浸水被害を軽減するための取り組みとしてはどのようなものがあるのか、お伺いします。
また、昨年度取りまとめられた玉川上水・放射5号線周辺地区地区計画の中には、既にこのグリーンインフラの概念が盛り込まれていると考えています。既存の住宅街を今後の変化に合わせて新たに生まれ変わらせるための地区計画の策定に当たっては、将来を見据えた課題解決が図られていくようなものにすべきと考え、本地区計画においては、地域の緑化の推進、住宅の建て詰まりの防止により、ひいては省エネのまち、低炭素のまちを標榜できる内容となっていると考えていますが、当区の見解をお伺いします。
戦後の高度経済成長期を経て、日本のインフラ整備は着々と進んできました。まさしくその真っただ中に生まれ育った私の世代は、目に見える形でインフラが整備され、利便性が高まっていくことを体感してまいりました。そして、順次更新期を迎える今、既存のものを全てそのまま建てかえをしていくことがこれからの需要に応えるものでは決してなく、また財政的にも困難であるということを、さまざまな生活の場面からも感じるようになってまいりました。
今回質問で取り上げたグリーンインフラという概念はまだ日本では定着をしていませんが、人工構造物をつくることばかりに腐心してきたインフラ整備とは対照的に、自然環境が持つ力を活用することで代替していくという、この動きの潮流をしっかりと捉え、積極的に調査研究を進め、当区で先駆けて実践をしていくことによって、次世代にできる限りの負担を残すことなく安全・安心なまちをつくっていけると考え、当区での今後の力強い取り組みを要望いたしまして、私の質問を終わります。
○議長(富本卓議員) 理事者の答弁を求めます。
区長。
〔区長(田中 良)登壇〕
私からは、山本あけみ議員の高齢者介護施設に関する御質問のうち、利用者の実態や多様なニーズに沿った今後の施設整備に関するお尋ねにお答えをいたします。
御指摘のとおり、超高齢社会が進展する中、介護施設を必要とする高齢者の実態はさまざまでございまして、幅広いニーズにきめ細かく対応していくことが重要であると考えております。そうした考えから、医療的ケアを必要とする方やみとりを希望する方へ対応するために、平成33年度の開設を目指して、天沼3丁目に特養を整備していくほか、多様な住まい方の選択肢を広げる観点から、自然豊かな南伊豆町に、自治体間連携によります区域外特養を来年1月開設に向けて整備をしております。
今後の整備に向けましては、入所希望者や御家族の心配事、御希望などを把握するために、今年度、実態調査を行うよう私から指示をいたしております。この調査によりまして、標準的な仕様に加えて、どんな機能を付加する必要があるのか、住まう場所をどこに望まれているのかなど細かく分析をして、今後の整備内容に生かしていく考えであります。このほか、施設運営事業者などからも幅広く意見をいただきながら、区民の皆様が真に安心して心豊かに高齢期を過ごすことができるよう知恵を絞っていく所存でございます。
私からは以上です。残りの御質問につきましては、関係部長より御答弁申し上げます。
○議長(富本卓議員) 高齢者担当部長。
〔高齢者担当部長(田中 哲)登壇〕
私からは、高齢者介護施設に関する残りの御質問にお答えいたします。
まず、待機者という呼び方に関する御質問ですが、介護保険制度以前の措置時代の呼び方でございます。現在の特養の入所に際しては、措置から契約へ移行し、正確には、待機者から入所希望者に呼び方が変わっております。
次に、特養入所希望者の現状把握の進捗状況ですが、これまでも、「入所申込みのしおり」に日常生活状況の項目を加え、介護者の状況の項目を細かくするなどの変更を行い、申込書による入所希望者の状況把握に努めてまいりました。
さらに、今年度は新たに検討組織を立ち上げ、実態調査の実施に向け、入所希望者の状況や御家族のニーズなどを把握するために、調査内容の検討を始めます。こうした調査の分析結果につきましては、今後の施設整備計画や第7期介護保険事業計画に反映をしてまいります。
次に、入所判定基準の変更についての御質問にお答えいたします。
特養は、法改正により平成27年4月から、要介護3以上の中・重度の要介護者を支える施設になりました。こうしたことを踏まえ、区におきましても、入所が必要な事情を一層きめ細かく把握し、より優先度が高い人が入所できるように、入所判定基準を見直すことにいたしました。見直しの検討に際しては、評価案を検討の各段階で特養側の代表と協議し、昨年の8月には、全ての特養と入所判定基準について協議や意見集約を行い、第一次評価の点数配分や項目の考え方を整理した上で、新評価基準を作成いたしました。
次に、第一次評価項目の一連の御質問にお答えいたします。
まず、待機場所の点数配分は、常に見守りがあるかを基準に判断をしております。
次に、区民優先とするため、区民でない場合等はポイントに差を設けました。
また、小規模多機能型居宅介護の利用者は、待機場所を在宅と位置づけ、ポイントを高くしてございます。
次に、介護者の状況に関しては、さまざまな同居家族の実情を今まで以上に把握するため、さらに細かく第一次評価項目を設定いたしました。
続いて、本人の日常生活の状況を新たに設けた理由ですが、要介護度が低くても、認知症などにより在宅生活、在宅介護が難しいケースが多くなっているため、今回追加をしたものでございます。
また、有効期限については、入所を希望している中でさまざま状況等に変化があっても、変更の届け出が提出されない現状があります。期限は設けましたが、これまでと同様に、状況が変われば、随時変更の届け出を提出していただいております。それ以外の事情の変更による更新は2年程度が妥当と考えました。
なお、区民周知については、内容を整理し、記入上の注意点や、特養に入所できるまでの案内などを別紙として作成するなど、さらに見やすくわかりやすいしおりの作成に努めてまいります。
次に、入居順位の決定に関する御質問にお答えいたします。
入居順位は、月次処理で行う区の第一次評価を踏まえ、各施設が第二次評価を行い、原則2カ月に1回開催する入所検討委員会において、優先度が高い方から順位を決めていきます。
また、緊急を要する場合や、以前の申し込み内容と状況が変わった場合は、随時変更の申し込みは受け付けております。辞退する場合は、原則取り下げ届を提出していただいております。
次に、新しい基準設定前の申込者への対応のお尋ねですが、平成29年2月に、初めての2年更新者と同時に、旧書式で申し込みされている全ての方に対し通知をし、入所希望を継続される方には、新書式で提出していただいております。提出されたものは全て新基準で評価し直し、新しい優先度を通知しております。
次に、徘回、医療処置が必要な方の受け入れ状況のお尋ねにお答えします。
特養における医療処置は、在宅酸素やペースメーカーのように、1度設置すれば特別なケアを必要としないものもあれば、人工透析のように、専門の設備と医療関係者が必要なものなど、その施設の設備や人員等に大きく左右されます。医療的ケアを必要とする入所希望者のニーズは増加傾向が見込まれますので、施設側や医師会を通じた医療機関との話し合いなどを通し、受け入れをふやしていく方向で検討していきたいと思ってございます。
次に、入所希望の集中に関する御質問にお答えします。
入所希望の傾向としては、区内施設におきましては、できるだけ早く入所できる定員数の多い施設、急病時の対応が迅速にできる病院が近接している施設、利用料が安い従来型の施設といった施設に申し込みの希望が集中してございます。区外協力施設においても同様の傾向がございます。
私からの最後に、独自に申し込みができる特養の案内に関する御質問にお答えします。
区内施設や区外協力施設以外の特養への入所を希望される方には、情報の豊富な東京都のホームページを案内するとともに、窓口で施設一覧を配布し、御案内ができるよう準備をしております。今後も窓口で、毎月更新されるホームページ情報等を入手しつつ、必要な情報を提供していきたく思ってございます。
私からは以上です。
○議長(富本卓議員) 土木担当部長。
〔土木担当部長(吉野 稔)登壇〕
私からは、グリーンインフラにつながる、浸水被害を軽減する取り組みについての御質問にお答えいたします。
区では、水害に強いまちづくりのため、また地下水の涵養など自然環境の保全のため、雨水の流出抑制対策に取り組んでいます。道路や公園、学校などの公共施設で透水性舗装や雨水の浸透・貯留施設の整備を積極的に進めるとともに、民間施設へも浸透ますの設置をお願いしています。東京都豪雨対策基本方針に示す時間10ミリの降雨相当分となる58万8,000立方メートルを目標としており、平成27年度末で約50%の達成率となってございます。
また、樹林地や緑地では雨水が地中に浸透しやすく、緑化を進めることも治水対策につながります。区では新たな公園の整備や屋敷林、農地などの保全に取り組むとともに、民間の建物についても、新築や建てかえの際に一定の緑地面積の確保を指導するなど、緑化の推進に取り組んでいるところでございます。
私からは以上でございます。
○議長(富本卓議員) まちづくり担当部長。
〔まちづくり担当部長(松平健輔)登壇〕
私からは、玉川上水・放射5号線周辺地区地区計画についてのお尋ねにお答えいたします。
本年3月に決定した玉川上水・放射5号線周辺地区地区計画は、玉川上水の緑と景観などを生かしつつ、沿道の緑化や大規模敷地における環境緑地の創出を誘導することなどにより、新たな道路環境や地域の課題に対応した一体的、総合的なまちづくりを進めるものでございます。これは、地域の自然環境が有する機能をまちづくりの課題解決に活用する取り組みでございまして、御指摘のグリーンインフラの趣旨にも合致するものと考えてございます。
私からは以上でございます。
○議長(富本卓議員) 教育企画担当部長。
〔教育企画担当部長(白石高士)登壇〕
私からは、学校図書館に関する一連の御質問にお答えします。
まず、学校図書館図書標準100%を達成した学校の割合は、小学校では平成26年度の59.5%が平成28年度は70.7%に、また中学校では同じく43.5%が60.9%になり、それぞれ上昇してきております。これは、平成27年度に新たに実施した学校図書館活用実践事業等による成果と受けとめており、引き続き平成29年度目標の達成に鋭意取り組んでまいります。
次に、図書資料の充実に向けた取り組みですが、各学校では毎年度の予算による蔵書の購入のほか、区立図書館の団体貸し出しや学校図書館相互の貸し出しにより、学校司書と教員が調整の上、子供たちの調べ学習や読書活動に資する図書資料の充実を図っているところです。
また、新聞につきましては、小学校では記事の見比べや紙面構成の特徴をつかむ学習などで、また中学校では記事の論理展開や表現方法等を議論する学習などで活用しておりますが、これらの学習は他の図書資料やインターネットの情報を活用して行うこともできるため、新聞を購入していない小中学校も、全体の4分の1程度ございます。教育委員会といたしましては、御指摘の新聞の活用を含め、今後とも各学校の実情等に応じた取り組みを支援してまいります。
私からは以上でございます。













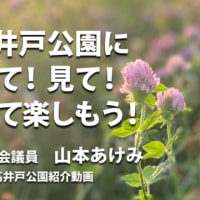






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます