<全文>
わたくしは、民主社民クラブの一員として、区政一般について質問をさせていただきます。
質問項目は、
「電柱の地中化について」「国内外の交流について」
「震災救援所について」です。
「電柱の地中化について」
さて、皆様は日本全国に桜の木がどれくらいあるかご存知でしょうか?答えはおよそ3,600万本と言われていますが、ではこの数と同じくらい全国津図浦々のまちにあるものは何か、それが電柱です。ここ数年は毎年7万本増え続けていると言われ、電柱のみならず、電線においては電気・電話・ケーブルテレビ・光ファイバーなどの種類は増え続け、その電線をなんとか電柱に取り付けるために日本人特有の器用さで何段にも何列かにもわたり取り付けられているのが現状ではないでしょうか。
この電柱は都市景観の大変な悪化を招いており、何よりも重要な歩行者の安全性を阻害し、災害時には倒壊や電線の切断が人命等への直接的な被害、救急活動や物資輸送の妨げとなり、復旧活動に支障が生じる原因となると考えます。そこで改めてお伺いします。
質問1.区内には現在どのくらいの電柱があるのでしょうか。また道路上の電柱は災害時の安全上支障があると考えますが、改めて地中化の目的をお伺いします。
一方で海外に目を向けますと、欧米の主要都市では戦前からの取り組みでロンドンやパリでは無電柱化率が100%と電線の地中化が標準となっています。アジアの国々でも進んでおり、ソウルは46%、北京は34%である一方、日本ではいずれも道路延長ベースで東京23区が7%、大阪市が5%、京都市が2%と極めて低い数字になっていると報告がされていますし、わたくしの元へは、人見街道等、地域の電柱を無くし、安全性を確保して欲しいという要望が多数寄せられているのが現状です。
そういった中、当区においてもこれまで取り組みを進めてきたと考えます。
質問2.永福町北口商店街通りの電柱の地中化が完成したところですが、改めてどの様な課題があったのかお伺いします。
完成した永福町の商店街を歩いてみると、日常の中に抜けたように高い秋の青空を感じる事が出来るようになり、今までのまるで障害物競走のように電柱を避けて通っていたのが嘘のような、安心して明るい気持ちで歩く事ができる素晴らしい空間が広がっています。当区の取り組みに改めて感謝をする所です。
現在、東京では2020年のオリンピック・パラリンピック開催に向けての様々な準備が進んでおります。都では平成19年に国内候補地に選ばれたのを受け、センター・コア・エリアという、山手通りと荒川で囲まれた地域の主要道路、このエリアの幹線道路や主要な駅のまわり、オリンピック関連施設周辺、文化財庭園や歴史的な施設を鑑賞する上で重要な眺望を保全する必要がある地域の無電中化を推進してきました。その結果、平成24年度末現在でセンター・コア・エリアにおいては80%の整備率となっています。
つい先日、11月10日の無電柱化の記念日制定発表会というものがありました。3つの1並びを電柱に見立て、最後のゼロで電柱をゼロにする、というゴロ合わせで出来た記とのことですが、豊島区のホームページにはセンター・コア・エリアのひとつに含まれる同区の高野区長が大変前向きな宣言をした事が発表されていました。それは、都市計画道路はもちろんのこと、将来的には生活道路の無電柱化にも取り組み、『防災力の向上』、『景観の向上』を図ることにより、『人間のための空間を取り戻す』ことが最終的な目標とし、将来的には、区内全域で無電柱化を実現し『電柱ゼロ都市宣言』をしたい、というものでした。
大変残念ながら、杉並区はセンター・コア・エリアには含まれておらず、2020年のオリンピック・パラリンピック開催のための整備が進められても目覚しく無電中化が進むとは考えられません。わたくしはオリンピック・パラリンピック終了後には、現状から遥かに整備が進む地域と、取り残されたように電柱が残り続ける地域との差が広がり、追いつけないほどになってしまうのでは無いかと危惧しています。そこで質問を致します。
質問3.今後、当区においては区道の電柱の地中化をどの様に進めていくのでしょうか見解をお伺いします。
緑豊かで区民の定住志向が高い杉並区が、都内でこれから進むと思われる無電中化の取り組みに遅れることなく、今後とも良好な住宅街であり続ける事が出来るよう、今後の区の積極的な取り組みを要望いたしまして次の質問に移ります。
「国内外の交流について」
当区では現在、国内で9自治体、国外の都市とは、オーストラリアのウィロビー市や大韓民国の瑞草区の2都市との友好都市の提携をしています。
国内交流都市の協定締結の時期からは、いわゆるバブル景気が続いた1980年代後半から1990年代初頭にかけて名寄市と東吾妻市及び国外2都市との締結がされ、その後阪神淡路大震災の10年後から国内4自治体、そして田中区政が始まり東日本大震災後には自治体間の相互援助が災害時には大変重要との認識から3自治体が災害時には相互に援助をしていくための協定が結ばれたと理解しています。これによって当区の防災力の増強がされたと考えていますが、ここで改めてお伺いします。
質問4.現在の国内外の交流自治体が決定される迄の経緯についてお伺いします。
質問5.また、交流自治体の交流の現状をどのように区は評価しているのかも
併せてお伺いします。
振り返ると、私が大学卒業後社会人となった1988年はちょうどバブル時代にあたり、好景気に支えられ、海外旅行者や留学希望者が大変多かった時代に当たります。その後、世界を一変するほどの情報のデジタル化が進み、仕事も効率的になったと思う反面、実体験を伴わなくてもインターネットを通じて何でも情報を得たような気持になる事も多くなってきたと感じています。
当区では、次世代の育成のために中学生の海外留学事業を実施していますが、中学生たちも出発の前にはインターネットを通じて情報を得る、調べ学習を十分にしている事と思いますが、実際に現地で体験する中で得る情報は想像をはるかに超える実りあるものだったと感じているのではないかと考えます。こういった実体験を通じての教育的見地からの質疑はこれまでもして参りましたが、今回は自治体間の交流をお尋ねします。
質問6.中学生海外留学事業を通して、ウィロビー市と杉並区との交流は深まっているのかをお伺いします。
これまでの一般質問での質疑においても、区からは国外の都市との交流事業について、まずは友好都市締結都市との交流を基本に交流事業を進めるとありましたが、今後は
質問7.青少年健全育成のためには、友好都市締結都市との交流だけに係らず、海外との交流を進めていくべきと考えるがいかがか。
インターネットが普及した今の時代だからこそ、青少年の健全な育成を推し進めるためには、幅広い知識を得、人格形成にも大きな効果が期待できる、実体験を通しての実りのある交流を要望いたします。
文部科学省は本年9月、大学の国際競争力を高めるために重点的に財政支援する「スーパーグローバル大学」に、国公私立大37校を選んだと発表しました。 海外から優秀な教員を獲得し世界大学ランキング100位以内を目指す「トップ型」に東京大や京都大など13校、大学教育の国際化のモデルを示す「グローバル化けん引型」に24校を選定し、トップ型には年約4億2千万円、けん引型には同約1億7千万円を補助するというもので、財政や影響を受ける学生数の規模は大変大きく、この政策の成果が将来の日本にとって大きな実りとなるよう期待するところです。
グローバル化けん引型には当区にキャンパスを持つ私立大学も含まれています。この大学では日本にいながら国際感覚を磨く学びの場を提供するとして、これまでの取り組みに加えて、「外国人留学生・日本人学生が共に暮らす」定員200名規模の混住型学生宿舎を平成28年に和泉のキャンパス隣接地への新設を決定しています。
こういった取り組みを大学内だけに留まらず、是非とも立地自治体である杉並区においても区内の青少年の健全育成に向けた団体などとともに、国際交流の推進に向けての政策に活かしていけないものかと考えます。そこでお伺いします。
質問8.区内の私立大学に海外からの留学生のための宿舎建設が進んでいる中、こうした機会を捉え国際交流等の連携を図っていってはどうかお伺いします。
「震災救援所の運営について」
当区が進める震災対策の基本的な考え方である自助・共助・公助の考え方に関しては、日々の区民の方々との会話の中から、少しずつですが周知が進んでいると感じています。今後は地域防災力をより一層高める事が杉並区全体の防災力を高めていく上で最も重要であると考えています。しかしながらその担い手である防災市民組織が成熟していく為には様々な施策を少しずつ着実に積み上げていく日々の努力が必要であり、またその進捗を区が把握し必要なサポートをしていく事が重要だと考えています。
区で作成した標準のマニュアル類がどの様に区民に受け止められ、理解され、周知が進み、今度はそれを礎にして実行力を高めていくか。そのため、どの様なステップを踏めばよいのかを常に念頭においた、粘り強い取り組みを望むところです。
実行力を高めるための施策の一つに震災救援所運営の独自マニュアル作成があると認識していますが、これはそれぞれの震災救援所の建物や人的配置などを鑑みてそれぞれに応じたマニュアル作成をしていくものとのことですが、
質問9.区ではこの震災救援所運営の独自マニュアル作成の進捗状況をどのように把握しているのでしょうか。また、実際にどのように作成が進められているのかお伺いします。
私が区内のいくつかの震災救援所訓練を拝見して最も大きく感じたのは、地域によって防災力に大変な差があるのでは無いかという疑問でした。短時間で震災救援所を立ち上げる力を持った救援所がある一方で、防災倉庫の内容の確認や災害時のトイレの組み立てなどの立ち上げる為の一部の訓練のみに留まり、最後の立ち上げにまで至らないままの訓練が続いている地域など、区民の皆様方の努力をもってでも中々順調に進んでいるとは言いがたい救援所もあるのが現状では無いでしょうか。
先日、わたしが防災サークルとして参加をしている震災救援所の訓練の一環として、HAGという避難所運営ゲームを30人ほどで行いました。
避難者の年齢や性別、国籍、それぞれが抱える事情が書かれたカードを参加者に配り、避難所施設に見立てた平面図にどれだけ適切に避難者を配置できるか、また避難所で起こるいろいろトラブルなどにどう対応していくかを模擬体験するゲームでした。
これは住民が避難所運営を主体的に考えるためのツールだという知識はありましたが、実際に震災救援所を運営するであろう校舎の中でその担い手が集まりゲームをしてみると、大震災が起きたときに地域の人々を救援するというのが絵空事ではなく、大変重大で難しい事であるという実感がわいてきました。
訓練が終わった後、参加者のひとりからは、「地域からもっと防災リーダーを輩出していく事を考えなければいけないのではないか?」という大変前向きなご意見を聞く事が出来たのは、大きな成果であると感じました。
一口に震災救援所といってもその成り立ちや抱えている課題・問題点は様々であろうと思います。それをひとつずつ解決し、力を付けていく為にはそのサポートをする為に区による活動実態の把握が必要でしょうし、一律ではない対応も求められてくるのではないでしょうか?
そこでお尋ねいたします。
質問10.各震災救援所の活動実態に即した支援は行われているのでしょうか、
区の見解をお伺いします。
また、こういった訓練の参加者からは区政に反映すべき様々な課題点をご指摘いただくことが多くあります。その一つに、訓練の全体像が分からないまま参加をしており、自分がいったいどの様な立場、役割で参加をしているのかさえ分からず、大変なジレンマがあると訴える方がいらっしゃいます。こういったお声は至極納得が出来るものです。何故なら、学芸会の練習にしても合唱の練習にしても、完成したものが想像出来るからその中の一部の練習に関しても納得をしながら取り組む事が出来るというのと同様であると考えるからです。そこで提案を含めての質問となりますが、
質問11.震災救援所の立ち上げから運営まで全体がわかるDVDを作成し、それぞれの訓練において参加者の認識を高めるために活用してみてはいかがか、区の見解をお伺いします。
私が参加をしている震災救援所は本年4月に新しい校舎が完成しました。
学校施設であるからには第一義的には教育の現場としての機能が盛り込まれており、設計に取り掛かる前には学校施設のほか、必要な防災設備に関してのヒアリングもあったでしょうし、これから長く使用していく校舎には最新のものが備わっているのだと思います。しかし、実際に防災サークルのメンバーで完成した建物の中を歩き回って防災設備を探し出すのは大変に難しいと感じています。
新校舎設計の際には震災救援所になる事を前提として使う側にとっても分かりやすい設計をすること、また震災が起き、停電で暗い中携帯も通じず、情報も無い中、震災救援所を開設することを考えると、少しでも予め出来る事があるならば準備をしておくという事も必要だと考えています。具体的な事例を申し上げれば、救援所へ来られる人の把握をする為に、出入りする門を1箇所に限定する事になると想定されるのであれば、通常時でもその門にわかりやすく表示をしておいたり、一度も校舎に足を運んだ事が無い人であっても校舎の全体の間取りが分かる様な案内図を分かりやすいところに掲示をしておくなどが考えられると思います。これらはアイデアとして持っていたとしても、耐久性を考えた案内板を製作するとなると大きな費用がかかる事もあり、市民組織で取り組む事は難しいと考えます。
また、避難が長期に亘る場合には、体育館のみならず校舎内も使用して避難者を受け入れる事になると思いますが、新校舎は従来と違って個別学習室やエレベーターへの導入路など、複雑な間取りとなっているため、どの様に避難者を誘導していくかは本当に難題です。
そこでお尋ねします。
質問12.新校舎建設時に震災救援所の設置運営を想定した校舎設計をすべきと考えますが、区の見解はいかがかお伺いします。
区立施設の更新の時期を迎える中で、設計時により多くの震災時の配慮を盛り込んでおくことは必要であり、それを利用者が日常的に認識していける事も地域防災力向上策のひとつとして重要であると考えます。
そういった観点においての取り組みを求めて質問を終わります。













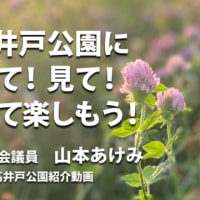






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます