少子・高齢化というのは、
少ない人で、社会の実働をし、
より多い高齢者が、その不足を補う必要がある。
今、政府の’事業仕分け’は
高度成長期の事業の仕方を洗い出しと考えられる。
成長期の量的拡大にともなった事業の細分化による量的拡大体質の改変だ。
企業体質が変わらなければ、
補填しようが、利子補給しようが、融資モラトリアムしようが、
企業業績は良くならないし、就業者は増やせないし、適用力不足でで消滅する。
’就職難’は、
経済(貨幣での交換活動)成長が鈍っているから。
企業活動が変動にたえる余力がなくなれば、
非常勤・派遣社員を減らすことは、合理的だった。
中高年労働者は、自身の体質を変えないかぎり、
企業活動には残れない。
近代までの家族と国家という両極のセーフティーネットはほころびてきた。
蓄積のない者は、企業の残らなければ、住むところも失いホームレスとなる。
市民活動もまた、
’市民階級’という近代の資産家に支えられた奉仕活動の体質を残している。
そして、社会意識による’ボランティア’活動という、'良心’に依存した
過渡期も終わろうとしている。
それは、
企業活動=拡大事業活動と
行政活動=先払い地域事業と、
必要時に組織される地域・テーマ活動の三種類。
事業仕分けの対象は、
企業活動:これが出来ない企業は停滞・倒産へ
行政活動:これが出来ないと不可欠サービスまで不足
今、政府の事業仕分けは、将来の借金を増やすか、余分なサービスを削るか
を問われている。政府・行政の外部組織の整理、天下りのチェックなどと
並行することで、少子・高齢化・縮減社会に対応できる。
少子・高齢化で資産拡大社会を求めれば、地域外との資産交換のひずみが犯罪・テロ呼ぶ。
持続できる企業・行政事業は、絞り込まれ、隙間ができる。
事業は、差別化できる専門的なスキルをもつ人が持続的に活動できる分野・対象に限られる。
持続しない活動・臨機応変な活動を抱える余地はない。
しかし、生活が豊かになるということは、より多くの選択と共感が必要となる。
村社会では、深い関係のなかで、一人一人に合わせられた活動が行われていた。
村八分といえども、二分は別。治水・治安・防災などは協働だった。
しかし、生産量・蓄積が少なかった故に、子堕ろし・姨捨、侵略・強奪などが常態だった。
今、近代を超えた現代、成長期を超えた成熟期には、
近代市民活動もまた、組織化の方法と活動の仕分けが必要となる。
従来の奉仕、任意のボランティアではなく、
緩く義務と権利を伴う、地域・テーマ活動に再編される必要がある。
だから、市民活動も活動仕分けの時代になった。
その再編の道具は、発達・普及した交通・通信・情報ネットワークだ。
臨機な地域・テーマ内の課題・話題が共有され、、
その場・その時・持っているスキルの範囲で行動でき、
その成果が持続・蓄積・再利用できるような仕組みができる。
それは、地域・テーマに絞ったメディアと促進ポイントだ。
メディアによって課題・話題に対して人が組織化される。
個別の活動に対してと促進ポイントの応報の仕組みが、
個人の持続的な活動と、活動同士の関係を深めてゆく。
対象活動よりも、組織を維持する活動の方が多いことが少なくないのでは?
課題・話題の共有化と組織化と持続かの仕組みがあることで、
市民活動の活動仕分けが可能になる。
少ない人で、社会の実働をし、
より多い高齢者が、その不足を補う必要がある。
今、政府の’事業仕分け’は
高度成長期の事業の仕方を洗い出しと考えられる。
成長期の量的拡大にともなった事業の細分化による量的拡大体質の改変だ。
企業体質が変わらなければ、
補填しようが、利子補給しようが、融資モラトリアムしようが、
企業業績は良くならないし、就業者は増やせないし、適用力不足でで消滅する。
’就職難’は、
経済(貨幣での交換活動)成長が鈍っているから。
企業活動が変動にたえる余力がなくなれば、
非常勤・派遣社員を減らすことは、合理的だった。
中高年労働者は、自身の体質を変えないかぎり、
企業活動には残れない。
近代までの家族と国家という両極のセーフティーネットはほころびてきた。
蓄積のない者は、企業の残らなければ、住むところも失いホームレスとなる。
市民活動もまた、
’市民階級’という近代の資産家に支えられた奉仕活動の体質を残している。
そして、社会意識による’ボランティア’活動という、'良心’に依存した
過渡期も終わろうとしている。
それは、
企業活動=拡大事業活動と
行政活動=先払い地域事業と、
必要時に組織される地域・テーマ活動の三種類。
事業仕分けの対象は、
企業活動:これが出来ない企業は停滞・倒産へ
行政活動:これが出来ないと不可欠サービスまで不足
今、政府の事業仕分けは、将来の借金を増やすか、余分なサービスを削るか
を問われている。政府・行政の外部組織の整理、天下りのチェックなどと
並行することで、少子・高齢化・縮減社会に対応できる。
少子・高齢化で資産拡大社会を求めれば、地域外との資産交換のひずみが犯罪・テロ呼ぶ。
持続できる企業・行政事業は、絞り込まれ、隙間ができる。
事業は、差別化できる専門的なスキルをもつ人が持続的に活動できる分野・対象に限られる。
持続しない活動・臨機応変な活動を抱える余地はない。
しかし、生活が豊かになるということは、より多くの選択と共感が必要となる。
村社会では、深い関係のなかで、一人一人に合わせられた活動が行われていた。
村八分といえども、二分は別。治水・治安・防災などは協働だった。
しかし、生産量・蓄積が少なかった故に、子堕ろし・姨捨、侵略・強奪などが常態だった。
今、近代を超えた現代、成長期を超えた成熟期には、
近代市民活動もまた、組織化の方法と活動の仕分けが必要となる。
従来の奉仕、任意のボランティアではなく、
緩く義務と権利を伴う、地域・テーマ活動に再編される必要がある。
だから、市民活動も活動仕分けの時代になった。
その再編の道具は、発達・普及した交通・通信・情報ネットワークだ。
臨機な地域・テーマ内の課題・話題が共有され、、
その場・その時・持っているスキルの範囲で行動でき、
その成果が持続・蓄積・再利用できるような仕組みができる。
それは、地域・テーマに絞ったメディアと促進ポイントだ。
メディアによって課題・話題に対して人が組織化される。
個別の活動に対してと促進ポイントの応報の仕組みが、
個人の持続的な活動と、活動同士の関係を深めてゆく。
対象活動よりも、組織を維持する活動の方が多いことが少なくないのでは?
課題・話題の共有化と組織化と持続かの仕組みがあることで、
市民活動の活動仕分けが可能になる。










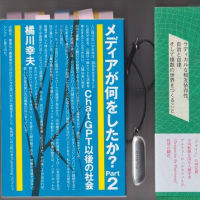

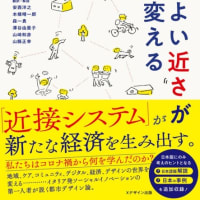

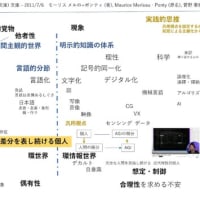
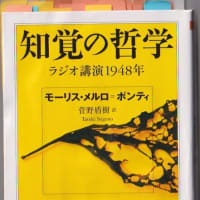
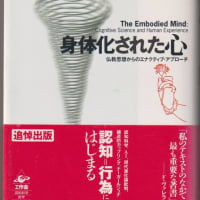
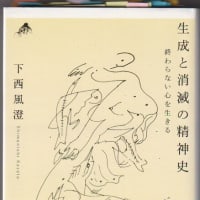

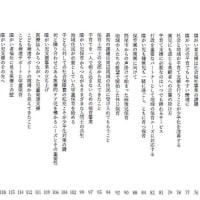
野党も政治家の腕の見せ所なのに・・・・
やはり、政治資金という入りの方が興味ありそで、税金の使い道の方はおざなりだ。