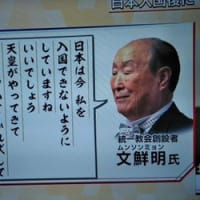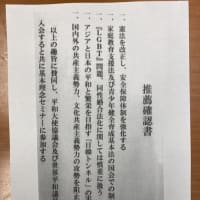|
あの頃映画 「事件」 [DVD] |
| SHOCHIKU Co.,Ltd.(SH)(D) |
この間、『仁義なき戦い』における渡瀬恒彦の顔と声をふいに思い出したので、その流れで『事件』を見た。
これは本当に素晴らしい映画だとずっと思ってる。でも作品として地味だし、ミステリーまたはサスペンスとしては、最初から犯人も犯人を取り巻く環境もあらかた分かっているので、その点では面白くないという人がいても不思議ではない微妙な作品なのかな。
しかし、そのあからさまに分かりきった話が、実はもっと奥が深いのだというのを映画として見せるという点で、なにかこう、熟達した作品だなぁなど思う。
ひとつは、問題となっている永島敏行演じる犯人の青年と、被害者ハツ子(松坂慶子)、その妹ヨシ子(大竹しのぶ)の関係が表面にみえるより一層どろどろだったという示唆が何気なく処理されている。実はいろんな関係があり件の殺人はその氷山の一角で、裁判が裁くのはさらにその一角だと。
そして、もう一つ、この事件の背景にこれらの人々が住まう環境の変化、いや変化しつつある環境が不気味にそこに横たわり、この状況によって人々は成長し、ある事件として結実する-。つまり、氷山が二重にも三重にもなっているような感じ。高くはないが深い山は怖い。
で、その環境の変化の方は、山本圭(永島敏行を昔教えた地元の教師)に、彼らを囲む環境のせいで彼らは道徳的指針を失ってるんだ(概略)、みたいなことを言わせることでも一応目につくようにはなっている。しかし、この効果は、逆に、視聴している側からすれば、それは犯罪者を庇ういわゆる左翼先生らしい屁理屈に聞こえる。それはおそらく1978年の上映当時でもそうだっただろう。(そうだからこそ、そう聞こえてしまうようにあえて山本圭に言わせているのか、という気もする)
そう、裁判が裁くのは一義的にはその事件なのであって、生活環境因子の変化を考慮に入れて判断されるべきものではないだろう。なぜなら大多数の人がその同じ変化の上に乗っているのだから。(革命期の政治裁判でもない限り)
しかし、それから30年たってこの事件を見れば、環境の変化は確かに人に影響を与えたのだろうし、それに適応するのも大変だっただろうなと思わざるを得ない。
端々に微妙に敗戦を引きずり、その上に高度経済成長が重なり、知らず知らずのうちに、留めようもなく人の一生のパターンが変化していく。こういう時代はもうないだろうなぁという時代がそこにある。(一言でいって、人々が今から考えるとネガティブに逞しい。これに比べれば己の欲に忠実な『仁義泣なき戦い』はなんと誠実なのだろうと思う。)
そんなはずはないような気もするが、野村芳太郎監督は、1978年において既に多少過去になってきた敗戦後の日本の変化を記録しておきたいと考えたのではないかなどと思ってみたりもする。そう思っていなかったとしても、この映画の価値はそこにある。
 証言台に立つ宮内(渡瀬恒彦)
証言台に立つ宮内(渡瀬恒彦)
そんな中、裁判の進行にとって重要な役割を演じる宮内というチンピラを渡瀬恒彦が演じている。このチンピラは、表面的にみれば何もいいところがない。宮内自身が「俺の女だ」と言い放つハツ子にとってもいい男とはいえない男だ。少なくとも傍からみればそれ以外にいいようがない。しかし、それにも拘わらず、ハツ子という享楽と不幸にしか縁のなかったような女性の一生の中で本当に巡り合ったという人がいるとしたら、それはこの男なのだるろうと思わせる、愛と呼ぶのもこそばゆい、しかし何か深刻なものがそこに見え隠れする男として描かれている。宮内の軽口の中にではなく、むしろ語らないことの中に、その佇まいの中に織り成される余韻がそれを予感させる(そして渡瀬恒彦が見事なまでにその佇まいの構築に成功している)。
新宿のキャバレーでのハツ子との出会いから新大久保での同棲を経て、刑務所から出て厚木でハツ子と再会するまでが切れ目なく回想シーンで処理されているのだが、それをうすら寒い電車の中で思い起こす渡瀬の「やりきれねぇよ」と言わんばかりの表情が、このドラマのベストショットではないかと思う。(そういう意味では、愛の物語の範疇にあるとも言える。)
そして、30年後に遠くから眺めるように視聴する私は、このショットは1978年に生きる人々が敗戦からその後の立ち直り期を振り返ったときの、苦い過去への遠い視線だったのではないかなどと妄想したくなる。そうしなきゃ生き延びられない時代はあった、みたいな。
本作はそもそも時代を映す事件(大岡昇平原作)を扱ったものだが、その『事件』が時代を写し取ってくれているような気がする。
★DVDの特典映像では、渡瀬さんがこの映画撮影の思い出をお話している。78年は離婚したばっかりで云々と、なかなか興味深いことを言っている。