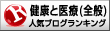以下も、このCD付属のパンフより、転載させていただいています。
『歌の翼 小池昌代
このCDには、誰もがよく知る日本の歌曲が収められている。わたしじしん、いつどこで習ったのかも記憶がないのに、体の方が、覚えている。
歌というのは不思議なもので、メロディを聴いた瞬間に、音に付随するさまざまな記憶が、いっせいに、うごめきだす。しかもそれはいつも、同じようにではない。生きている途上で、一度として同じ瞬間がないように、一度として同じように歌われ、同じように聞かれる歌もない。音楽は常に生きているのだ。
これらの名曲が、どれもわたしたち大人にとって、大切に思われるのは、それらの曲に、生きてきた時間が、長くしまわれているからだろう。
過去の量が、大人よりも極端に少ない子供たちは、いってみれば、それらの歌とあまりに一心同体なので、存在それ自体が「歌」なのだ。その意味で、ほんとうに意識を必要とするのは、一度、歌から離れて生き、歌を見失った大人のほうだろう。
例えば、「故郷」という曲を、わたしはどれほど聴き、歌ってきたことか。いや、実際は、歌うよりも、記憶のなかに、いつでも取り出せる曲として、しまわれていた時期のほうが長いような気もする。大人にとっての唱歌や童謡は、そういう意味で、宝石箱のなかの宝石に似る。しかもそれは、共有の財産であって、誰かが口ずさめば、それがすなわち、わたしの歌であり、わたしたちの歌になる。
しかし、時代は変化する。「故郷」のなかで歌われている内容は、現代日本において、すでに失われた、あるいは消えゆく運命にある風景であり志である。けれど山河が、そしてそこに宿る魂が、美しく在り続けてほしいという願いに変わりはない。この曲は、その祈りを担って未来へと運ばれる、手押し車のような名曲ではないだろうか。
「落葉松」は、このCDのなかで、わたしのもっとも好きな曲である。明るい曲調のなかに、時折差し込む陰影があり、哀切な感情を聴く者の心に抱かせる。ここに降る雨には、お天気雨のように光が差している。鎮魂歌のような名曲だと思う。
歌曲には、聴いているだけで満足な曲と、どうしてもいっしょに歌ってしまう、歌いたくなる曲があるが、その違いはいったい、どこから来るものか。「故郷」や「落葉松」そしてこのあとに続く、「浜辺の歌」「初恋」「この道」は、わたしにとって後者、つまり、どうしても歌いたくなる類の曲だ。そういう曲には、「あこがれ」をかきたてるものがある。歌うたびに、わたしのこころを、とても遠くまで連れていってくれるのだ。
「浜辺の歌」を聴いてみよう。打ち寄せる波の音のようなメロディは、わたしたちの記憶の壁を洗い、古への、たゆたうような、追憶の感情を目覚めさせてくれる。「初恋」はどうか。劇的な歌である。この曲を聴くと、思春期のころの、夢見る心が蘇ってくるだろう。啄木の短歌に曲をつけたものだが、砂山の砂に、砂に腹這いと、砂が三度、強調されて歌われる。わたしはそこがとても好きだ。
そして「この道」を歌うとき、わたしの目の前には、抜けるような青空の下、あたたかい道が、遠くまで伸びて行く。お母様と馬車で行ったという風景などは、私の生活感覚から遠いものだが、メロディのなかに、あたたかな異国、一つの懐かしいユートピアが出現する。白秋は、言葉でそういう異空間をつくった、絢爛たる才能の詩人である。
これら日本のすぐれた歌曲は、多くが、大正、昭和初期に生まれた。みな、メロディが美しく、ロマンがあり、詩情がある。微妙な陰影のニュアンスがある。明るいのに、みな、どこか哀しい。そして独特の香気がある。西洋音楽の優れた富を、驚くほどうまく日本の感性にとかしこんだという印象を受ける。
CDでは、このあと、野口雨情の詩の世界が展開するが、そこでは、いっしょに歌うよりも、ただ、アンネットさんの声に身を委ねたいという気持ちになった。
「青い眼の人形」や「赤い靴」が歌われていた当時、日本では、アメリカ大陸への移民が盛んだったそうだが、そのアメリカで、日本移民を排斥しようとする移民法制定の動きがあり、それを懸念したアメリカ市民から、日米友好を願った平和使節人形が、日本へ送られたという。もっとも、「青い眼の人形」は、その人形をモデルにしたものではない。曲はすでにあった。太平洋戦争が始まったのは、この曲が世に出てから、およそ20年後のことである。
「赤い靴」も雨情の代表作だが、モデルがいたという説がある。雨情が札幌で記者をしていたとき、一緒に暮らしていた同僚がいた。その彼が再婚した相手には娘がいたのだが、再婚に際し、女性はやむなく、その子をアメリカ人宣教師夫妻に養女として託したのだという。娘は岩崎きみという名で、その後、東京で病死したらしい。
『歌の翼 小池昌代
このCDには、誰もがよく知る日本の歌曲が収められている。わたしじしん、いつどこで習ったのかも記憶がないのに、体の方が、覚えている。
歌というのは不思議なもので、メロディを聴いた瞬間に、音に付随するさまざまな記憶が、いっせいに、うごめきだす。しかもそれはいつも、同じようにではない。生きている途上で、一度として同じ瞬間がないように、一度として同じように歌われ、同じように聞かれる歌もない。音楽は常に生きているのだ。
これらの名曲が、どれもわたしたち大人にとって、大切に思われるのは、それらの曲に、生きてきた時間が、長くしまわれているからだろう。
過去の量が、大人よりも極端に少ない子供たちは、いってみれば、それらの歌とあまりに一心同体なので、存在それ自体が「歌」なのだ。その意味で、ほんとうに意識を必要とするのは、一度、歌から離れて生き、歌を見失った大人のほうだろう。
例えば、「故郷」という曲を、わたしはどれほど聴き、歌ってきたことか。いや、実際は、歌うよりも、記憶のなかに、いつでも取り出せる曲として、しまわれていた時期のほうが長いような気もする。大人にとっての唱歌や童謡は、そういう意味で、宝石箱のなかの宝石に似る。しかもそれは、共有の財産であって、誰かが口ずさめば、それがすなわち、わたしの歌であり、わたしたちの歌になる。
しかし、時代は変化する。「故郷」のなかで歌われている内容は、現代日本において、すでに失われた、あるいは消えゆく運命にある風景であり志である。けれど山河が、そしてそこに宿る魂が、美しく在り続けてほしいという願いに変わりはない。この曲は、その祈りを担って未来へと運ばれる、手押し車のような名曲ではないだろうか。
「落葉松」は、このCDのなかで、わたしのもっとも好きな曲である。明るい曲調のなかに、時折差し込む陰影があり、哀切な感情を聴く者の心に抱かせる。ここに降る雨には、お天気雨のように光が差している。鎮魂歌のような名曲だと思う。
歌曲には、聴いているだけで満足な曲と、どうしてもいっしょに歌ってしまう、歌いたくなる曲があるが、その違いはいったい、どこから来るものか。「故郷」や「落葉松」そしてこのあとに続く、「浜辺の歌」「初恋」「この道」は、わたしにとって後者、つまり、どうしても歌いたくなる類の曲だ。そういう曲には、「あこがれ」をかきたてるものがある。歌うたびに、わたしのこころを、とても遠くまで連れていってくれるのだ。
「浜辺の歌」を聴いてみよう。打ち寄せる波の音のようなメロディは、わたしたちの記憶の壁を洗い、古への、たゆたうような、追憶の感情を目覚めさせてくれる。「初恋」はどうか。劇的な歌である。この曲を聴くと、思春期のころの、夢見る心が蘇ってくるだろう。啄木の短歌に曲をつけたものだが、砂山の砂に、砂に腹這いと、砂が三度、強調されて歌われる。わたしはそこがとても好きだ。
そして「この道」を歌うとき、わたしの目の前には、抜けるような青空の下、あたたかい道が、遠くまで伸びて行く。お母様と馬車で行ったという風景などは、私の生活感覚から遠いものだが、メロディのなかに、あたたかな異国、一つの懐かしいユートピアが出現する。白秋は、言葉でそういう異空間をつくった、絢爛たる才能の詩人である。
これら日本のすぐれた歌曲は、多くが、大正、昭和初期に生まれた。みな、メロディが美しく、ロマンがあり、詩情がある。微妙な陰影のニュアンスがある。明るいのに、みな、どこか哀しい。そして独特の香気がある。西洋音楽の優れた富を、驚くほどうまく日本の感性にとかしこんだという印象を受ける。
CDでは、このあと、野口雨情の詩の世界が展開するが、そこでは、いっしょに歌うよりも、ただ、アンネットさんの声に身を委ねたいという気持ちになった。
「青い眼の人形」や「赤い靴」が歌われていた当時、日本では、アメリカ大陸への移民が盛んだったそうだが、そのアメリカで、日本移民を排斥しようとする移民法制定の動きがあり、それを懸念したアメリカ市民から、日米友好を願った平和使節人形が、日本へ送られたという。もっとも、「青い眼の人形」は、その人形をモデルにしたものではない。曲はすでにあった。太平洋戦争が始まったのは、この曲が世に出てから、およそ20年後のことである。
「赤い靴」も雨情の代表作だが、モデルがいたという説がある。雨情が札幌で記者をしていたとき、一緒に暮らしていた同僚がいた。その彼が再婚した相手には娘がいたのだが、再婚に際し、女性はやむなく、その子をアメリカ人宣教師夫妻に養女として託したのだという。娘は岩崎きみという名で、その後、東京で病死したらしい。